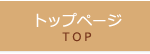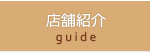先日新聞に「高齢者の使用中止求める薬」が発表された旨の報道ありました。高齢者は代謝能力他が衰えているためやたらと薬を服用しない方が良い、という話です。その使用中止すべき薬の中に漢方薬が挙げられていました。なんでも生薬”甘草”を含む処方は浮腫、高血圧、不整脈、低カリウム血症をきたし易いので使用を控えるべきとの主旨です。
しかし甘草は市販されている漢方薬の7割近くの処方に配合されているので、高齢者は大抵の漢方薬を服用すべきではないことに。
そんな馬鹿な話はありません。確かに甘草には副作用があることは業界ではよく知られた話ですし、証を間違わなければ理論上副作用は起きにくいはずです。
この業界に身を置くこと30年ですが、甘草の副作用と思われる症状はほとんど経験したことがありません。
気になるので先の記事の情報源である「日本老年医学会」を調べたところ、確かに高齢者に甘草を含む漢方薬は上記副作用が懸念されるため、使用には十分に注意すべき、と記されていました。ただ条件も記されており「対象となる患者群:腎機能の低下した患者、ループ利尿薬使用患者」とありました。この部分は報道では抜け落ちており、まるで高齢者には甘草を含む漢方薬を使用してはいけない、と報道では読めました。
大丈夫です。高齢者の皆様!! 安心して漢方薬を服用してください。
ただし専門家に相談してから!!
大新聞とはいえ鵜呑みにしてはいけないことを改めて認識した次第。先の朝〇新聞のように。
大新聞といえども鵜呑みは危険です
長全堂薬局 (山口県萩市)
| ツイート |
|
更新日: 2015/04/03 |