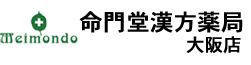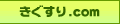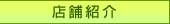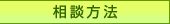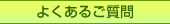本格的に寒くなり、風邪やインフルエンザが流行り出してきたとニュースでも取り上げられていますね。
こういう時、西洋医学に頼るだけではなく東洋医学を使ってみませんか?
現代医学における風邪の原因はウイルスへの感染ですが、東洋医学における「風邪」の原因は『環境』と『人』。東洋医学では、風邪を引く原因を病原菌やウイルスにではなく、人をとり巻く外的環境や、風邪を引く人そのものと考えていました。
今回は、特に前者である外的環境にスポットを当てて、東洋医学の考える風邪の原因について、分かり易くお伝えしたいと思います。
まず人が風邪を引いたり体調を崩したりする外的な要因を、東洋医学では「邪(ジャ)」と呼びます。そして、邪には六種類あり、「風・火・暑・湿・燥・寒」となり、これらをまとめて「六淫(リクイン)」と呼びます。六淫は『風などの自然現象、湿気や乾燥、寒冷刺激などの温度変化』のことを指します。
“かぜを引く”の「かぜ」を漢字で書いたら「風邪」ですよね?
『風邪(かぜ)』の語源は『風邪(ふうじゃ)』
「風邪を引く」の「風邪」とは「カゼのジャ」であり、つまり「ふうじゃ(風邪)」なのです。体調を悪くする環境や外的刺激の中でも、特に自然界に吹く風が体に与える悪影響を指して言う言葉だったのです。
『風(ふう)』は、体表の熱を奪い皮膚や粘膜を乾燥させる
「風」で「風邪を引く」と聞いても、すぐにはピンとこないと思います。しかし、想像してください。体に風が当たり続けると、徐々に体表の熱を奪い、皮膚や粘膜が乾燥する。皮膚や粘膜が乾燥したら次に何が起こるか。体内にウイルスや細菌が侵入しやすくなりますよね。免疫力が下がってしまい、容易に細菌やウイルスの侵入を許すようになってしまいます。
その他にも、六淫の中の「寒」が、特に皮膚や粘膜が冷やし血行を悪くします。その結果、免疫力が下がってしまいます。
そう考えると、春先の風が強く吹く頃、秋から冬にかけて空気が乾燥する頃、真冬の冷えが厳しい頃に風邪を引く人が多いのもうなずけると思います。
東洋医学が考える「風邪」の原因のひとつ。それが季節それぞれの気候、または、風や乾燥、気温の変化などの外的要因だという事です。
次回は風邪をもう少し詳しく分類し、漢方薬をご紹介したいと思います。
風邪には漢方
命門堂漢方薬局 大阪店 (大阪市都島区)
| ツイート |
|
更新日: 2016/12/16 |