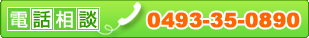カゼは万病のもと
カゼくらいと思って侮ると、カゼは万病のもとと言われるように違った病気の原因となることがあります。
特に老人では肺炎を起こし急逝される方もいるぐらいですから、油断できません。
2011年の人口動態表に死亡原因の第三位に今までの脳血管疾患をこえて、肺炎が三位に出てきました。
日本の高齢化がより進んだものと考えられます。(一位癌、二位心疾患、三位肺炎)
もともとカゼを引く体調そのものが抵抗力の落ちている状態ですので、気をつけたいものです。
カゼ薬にも西洋薬と漢方薬がありますが、一体どちらがより効くのでしょうか。
ここに興味深い調査があります。
北海道の本間行彦医師が行った「漢方療法と西洋医学治療の比較」によると初診時に37℃以上の発熱がある患者にそれぞれ漢方薬(35名)と解熱鎮痛消炎剤(西洋薬・45名)を投与したところ、漢方薬を投与したほうが早く熱が下がり、更に熱の再発は漢方薬群が0%だったのに対し、西洋薬群は11%でした。
出雲市で医院を開業していた阿部勝利医師は、初診患者を漢方群と西洋薬群に交互に振り分けて調べたところ(漢方386名、西洋397名)、冬季のインフルエンザでは漢方群のほうが重症化は少ないとの報告を学会で発表しています。
カゼに関しては漢方薬のほうが西洋薬に勝るという科学的な裏付けの一つですが、なぜそうなのでしょうか。
カゼと言う病気と薬の関係を考えて見ましょう。
私たちがカゼと称している病気は医学的には「感冒」と呼ばれ、様々な細菌やウイルスが原因となって起こります。
一方インフルエンザ(流行性感冒)は全てウイルスが原因ですが、こちらも様々なタイプのウイルスが存在します。
カゼもインフルエンザも、感染して体内で病原体が増殖して様々な症状を引き起こすわけですが、病原体が体内にいる限り、治癒には至りません。
そして体内に侵入した病原体を殺す薬は、実は漢方薬にも西洋薬にもありません。
では何のために、カゼ薬はあるのでしょうか。
一口で言いますと、西洋薬は、発熱、痛み、炎症などカゼの個々の症状を和らげる働きを期待して投与されます。
「あなたのカゼはどこから?」というフレーズがそれを象徴的に表しています。
一方、漢方薬は、体が本来持つ自然治癒力が活発になることを期待して投与されるのです。
で、その治癒力は「発熱」として発揮されます。
カゼを引いて熱が出るのは、体がカゼの病原体と戦っている証です。
高齢者がカゼで命を落とすのは、この発熱の力が失われているからに他なりません。
漢方薬は効率よく発熱させて、早く治療体制に持っていこうとする薬ですから西洋薬より約1日、熱の持続時間が短いのもうなずける話ですね。
ただし、カゼと言う病気は引ききってしまう(体の中に病原体が増殖しきってしまう)と、丈夫な人でも約1週間はいろんな症状を引きずるものです。
大切なのは引かないように予防すること、そして引きはじめを賢く察知して、その時点で食い止める(漢方薬を服用)ことです。
例えば「ゾクゾク」「クシャミ3回」の時点。
この時点なら数時間以内で病原体を体外へ押し戻すいい漢方薬があるのです。
漢方薬は体質や体力に応じて選び分けなければなりません。
一般的には、カゼに葛根湯と言いますが、それが全てではありません。
体の虚実の判断が必要ですが、一般人にはなかなか出来かねます。
体の体質、虚実の程度に合わせた漢方薬は、カゼを引いたかなと思ったときに服用し、体を温めるようにすると数時間後には、もとの健康体に戻ります。
さて、この体質・体力は同じ人が虚になったり実になったりと言う具合に変動することはほとんどありません。(加齢や過労が原因でまれに変わることがあります)。
ですから一度、漢方の専門家に診てもらって、自分にはどんな漢方薬がいいか知るのもいいと思います。
かぜには、自分に合う漢方薬を携帯していて、カゼかなと思ったときに、すぐ服用するのがカゼに罹らぬ最善の方法なのです。
惠木 弘・著 『冬こそ若返る! 四季の養生法』より