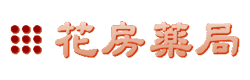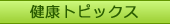【質 問】
27歳女性。高校時代から花粉症で悩んでいます。目のかゆみ、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、皮膚がひりつくように痛くなり、今年は3から4回くらい風邪も引き、微熱が出たり下がったりしています。
【答 え】
顔が隠れるような深い帽子をかぶり、花粉症用の眼鏡をかけ、マスクをして顔が全く見えない状態で来店されたのは、今から3年前のことである。
花粉症は外傷と内傷に分けられる。外傷とは、くしゃみ・鼻水・鼻づまり・目のかゆみの段階である。だるさ、発熱、鼻水が黄色くなる、発疹などの症状が出る人は、内傷と呼び体の中に原因がある。外傷から内傷に移行するにはそれほど時間を要しない。3日もあれば十分で、花粉とは無関係に症状は持続し、寝不足や疲れで悪化する人は内傷である。雨が降ると治ってしまう人は外傷に留まっていると判断できる。
この女性の場合はさらに感冒がからみ、内傷を悪化させた状態である。まず、微熱の改善に「柴平湯・さいへいとう」を服用してもらった。去年、今年と内傷の改善、いわゆる体質改善に「半夏白朮天麻湯・はんげびゃくじゅつてんまとう」を11月から服用し、花粉の時期に備えてもらっている。去年と今年は花粉の量は少ないが、春先に帽子をかぶらず外に出られるのが大変うれしいという。
|
【質 問】
わたしは22才になる女性です。アルバイトをしているお店が寒くてすぐに持病の喘息が出てしまいます。小さい頃よりアトピー性皮膚炎と喘息に悩まされていました。熱はあまり出ませんが、寒さを感じると透明な鼻水が出て、体がだるくなります。2、3日すると咳が出て透明な痰がやがて黄色くなって息苦しくなり、ぜいぜいし始めます。来年には結婚する予定なので体を丈夫にしておきたいのです。 【答 え】 中医学には、風邪を症状によって六つに分類した六経弁証という物差しがあります。その五番目の少陰病という分類の中には、いつも寝たい、胸苦しい、激しい悪寒を伴う、時に下痢をともなうなどは四逆湯(しぎゃくとう)とあります。この症状に加えて、節々が痛むものには、附子湯(ぶしとう)を使い、全身のだるさをともない、時に腹痛と下痢があるものには真武湯(しんぶとう)を服用します。吐き気と下痢があり、頭痛し、手足が冷えて温まらないものには呉茱萸湯(ごしゅゆとう)、皮膚がひりついたり、のどの痛みをともなうものには麻黄附子細辛湯(まおうぶしさいしんとう)等を使います。 >この女性は普段より冷えやすく、手足も冷たい体質でしたので、血行を良くし、体を温め、風邪を予防し、体を丈夫にする上薬、大蒜の製剤を日常から服用していただきました。これに加えて、真武湯を服用してもらい2週間もすると、凄く元気になりましたとお礼を言いに来られました。現在、真武湯はたまに服用するだけで、元気に上薬だけを服用し、身体を丈夫にしています。 |
| ツイート |
|
更新日: 2011/05/13 |
|
【質 問】
70歳の女性です。今は特に病気もなく元気ですが、病気で不自由な生活をするがいやです。別に、いたずらに長生きはしたくないのですが、何か良い養生法はないのですか。 【答 え】 黄帝内経には、養生法が記されている。春は夜更かしをしても良いが、朝は早起きをする。夏には遅く寝て、朝早く起きる。秋は鶏と同じように早寝早起きすべきである。冬には、夜早く寝て朝はゆっくりと起きる。体内の陽気をもらさないように、寒い刺激を避け身体を温かく包む。これに逆らうと災難に遭う。従えば自然の変化に順応し元気で長生きできる。 過労を避け、激怒しないよう努める。美食、過食はしない。病気を長引かせない。酒を飲み過ぎない。力を出しすぎない。 五味と言われる酸味・苦味・甘味・辛味・鹹(かん)味をバランス良く食べ、一つだけを取りすぎないように気をつけることとある。しかし、我々が生きていくうえで黄帝内経の聖人の生活はなかなかできない。そこでこの不摂生を補う上薬がある。 |
| ツイート |
|
更新日: 2011/05/12 |
|
【質 問】
お正月にお屠蘇(とそ)をする習わしはいつごろから、どのような理由があるのですか。 【答 え】 お屠蘇とは新年の元旦、2日、3日の三ガ日の朝、屠蘇散という処方を、みりんまたはみりんと酒に一晩浸して、延命長寿を願って飲む薬酒のことである。この風習は約1700年前、中国の三国時代の名医・華佗(かだ)が一年間の災難厄よけのため十数種の薬草を調合したのが始まりといわれる。 日本へは奈良時代後半(約1200年前)に伝わり、平安時代初期に宮中儀式に取り入れられました。後に平安貴族に広がり、時代と共に武士や上流家庭に普及、婦女子にも口当たりの良いみりんなどを用いて現在に至りました。 中国・明の時代の書物によると、三角に縫った絹の袋に入れて大晦日の夜から井戸の内につるしておき、元日の朝に取り出して酒に浸す。一家そろって雑煮の前に祝い、来客にも初献する習わしです。松の内が過ぎると残りかすは井戸に投じ、この水を飲むと水あたりしないと伝えられてきました。息災を祈る意味で年少者を先にし、順次年長者にと定められています。 一般には薬種五味のものが多く販売されています。一晩浸しておくと苦味が出て飲みにくいことがあり、浸す時間を20分から40分にするだけで味、香り、色合いがほど良く仕上がります。 |
| ツイート |
|
更新日: 2011/05/11 |
|
【質 問】
72歳になる父は長い間、咳(せき)をしています。毎朝たんを切るために、大きな咳と咳払いをしてとても苦しそうです。夕方になると多少悪化し、昼間はさほどでもありませんが、たばこを吸うと咳き込みます。本人は年だからと余り気にしていませんが、治るものなら治してあげたいのですが。 【答 え】 咳をして、しわがれ声になり、喀痰がしにくく、時折血を吐く。硬いものが食べれなくなる。ふらつきがあり、目がかすみ、耳鳴りがする。のどが渇き、乾燥し痛む。口や舌が割れて傷になる。汗が出やすく、のぼせて寝汗をかく。ときに便に血が混じり、元気が無くなる。微熱がやまず、腰から下が軟弱になる。小便の出が悪く、勢いもなくなるなどの症状を他に伴うことが多い。 この人は明の時代につくられた、腎を温め水分代謝異常を調整し、活力を益し咳を止める八仙長寿丸(はっせんちょうじゅがん)が良いでしょう。また、咳は長期間に及んでいるので、開豊瓊玉膏(けいぎょくこう)と一緒に服用すると良い結果を生みます。 この漢方薬は宋の時代に登場し、腎を養い若返りをすることで有名で、陰分を補い、肺を潤す働きがある。肺の活力を増し、空咳を治す。好酒を好み長年咳をしている人、息が切れ、体力が落ちてきた人、身体がかさつきやせてきた人には最適の薬である。 |
| ツイート |
|
更新日: 2011/05/10 |