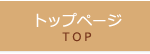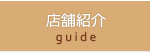感染性胃腸炎は、多種多様の原因による症候群を指します。原因となる病原体は、細菌、ウイルス、寄生虫などがあります。
症状は発熱、下痢、悪心、嘔吐、腹痛などが主に見られます。
原因となる細菌とウィルスには腸炎ビブリオ、病原性大腸菌、サルモネラ、カンピロバクター、ロタウイルス、腸管アデノウイルス、ノロウイルスなどがあります。
感染患者に直接接触したり、吐瀉物や汚染された水や食品を介して感染します。冬期はウイルス性の胃腸炎が多くなり、一般的には「お腹にくる風邪」と言われています。
ノロウイルスの流行が晩秋から増加してきて12月にピークを迎え、次いでロタウイルスによる乳児嘔吐下痢症の流行が2月から3月にかけてピークを迎えた後も初夏まで流行は続き、その後、夏期は細菌性のものが増加してきます。
近年、ノロウィルスやロタウィルスによる感染性胃腸炎が増加して来ました。
これは私が考えるに胃腸が弱っていて免疫力も低下しているので、どんどん発症するのではないでしょうか。
昔も感染性胃腸炎はあったでしょうが、おなかを壊して下痢をしたら、絵も自然に治っていたので、あまり注目を浴びなかったと思います。
東洋医学的に原因を考えると胃に熱があり、水の過剰である水毒もあります。
気候が涼しくなって、気温が下がり体表面が寒くなり、その逆に体内には熱を持ちやすく胃に熱がこもることになります。
現代の日本人は季節に関係なく、とかく水分の過剰に摂取していて、夏場も汗をかいて水分が出ていかないのも水毒を作り出す原因ではないでしょうか。
とにかく日頃より水分の取りすぎに注意しましょう。
ただの水はいらないけど、お茶だったら飲もうかなと思う場合は取る必要がないので、控えてください。良く効く、漢方薬がありますのでご相談ください。
感染性胃腸炎にかからないために
ケンコウ薬店 (三重県津市)
| ツイート |
|
更新日: 2013/12/27 |