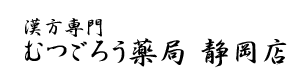何事もやりすぎは良くないといいますが、これを上手く言い当てたものに「中庸」という言葉があります。やり過ぎではない、つまり「し過ぎない」「適当」といった意味合いを持ちます。
適当とは、決していい加減ということではなく、いい塩梅ということです。
西洋医学の考え方に当てはめると、数字が重要視されるので平均値という形で捉えられがちですが、漢方ではそのような考え方はしません。
一人一人の証が異なるように、その人にとっての中庸だと思われる部分があり、そこがちょうどバランスが取れて健康だとされているのです。
日常生活における、自律神経の変化をとってみてもそうですよね。
日中は多くの場合、心身が活発になり多くのストレスを抱えています。そういった状態は交感神経が優位となり、心拍数の増加や血圧が上昇しますが、その反面、消化器官の動きが鈍くなっています。
そして、仕事を終えた後や入浴後などリラックスすると、今度は副交感神経が優位となります。それまで緊張していた身体は次第にほぐれて心拍数は減りますが、一方で胃腸の働きは活発になり休息の時間へと移り変わります。
これが、交感神経や副交感神経にばかり比重が偏っていてはどうでしょう。
自律神経の乱れは、多くの疾患や不定愁訴をもたらします。そのバランスは、万人にとってベストな状態というものはなく、その人の体質やこれまでどのようなライフスタイルを送っていたかによっても、ちょうど良い加減が異なるものです。
このような考え方は、わたしたちの生活にも取り入れることができます。
他人や物、お金に対して興味や執着はあって当然のことですが、それが度を越してしまうと、様々なリスクを生み出します。そして時には、マイナス面しか残らずに幸せを逃してしまっていることだってあるのです。
自分にとっての中庸、バランスの取れた状態を知るためには日頃からよく自分自身を知っておくことが大切ですが、それに加えて、かかりつけ医や相談できる薬局などがあればより良い環境だといえるでしょう。