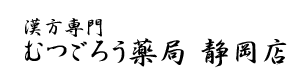「気」や「血」と同じく身体をめぐる「水(すい)」は、無色の液体を指します。リンパ液など、血液を除いた体液のことを表していると捉えて良いでしょう。
正常に循環している場合には問題ないのですが、一度、その流れが滞ってしまうと様々な症状を引き起こしてしまいます。
このような、水にかかわる不調は水毒(すいどく)と呼ばれ、水分の取りすぎや冷えによって代謝が落ち、水とともに老廃物を溜め込んでしまうことが主な原因だとされています。
●水毒によって引き起こされる症状とは?
通常の食事や水分を摂取しているにも関わらず、次のような症状が出る場合は水毒が原因となっているかもしれません。
・尿量が少ない
・頭痛
・めまい
・むくみ
・アトピー
また、空腹時にお腹辺りを軽くたたくとチャプチャプという水の音が聞こえる場合も要注意です。
●水毒になったときにすべきこととは?
日常生活の中で気をつける点は、水分を取りすぎないようにしたり、身体を冷やしすぎないことです。代謝を良くして、余分な水分の排出を促しましょう。
また、新陳代謝を上げるための軽い運動や入浴、あたたかい食事や飲み物などもオススメです。食材に根菜やにんにく、生姜などの薬味を加えても良いでしょう。
●水毒に効果を発揮する漢方薬とは?
食生活やライフスタイルの改善では良くならない場合や、症状が重く辛いときは漢方薬が味方になってくれます。
利尿薬として知られる五苓散(ごれいさん)は水毒に対する代表的な漢方薬で、水分の代謝を改善してくれます。尿量が少ないなどの症状に加え、喉の渇きがある場合などによく用いられます。
また、五苓散に胆汁の分泌を促す作用のある茵蔯蒿(いんちんこう)を加味した茵蔯五苓散(いんちんごれいさん)も水毒症に使われる漢方薬です。尿量が少ないなどの症状に加え、肝炎や肝機能障害に対しても用いられます。
しかし、下痢など消化機能が低下した水毒に対しては対症療法にしかなりませんので、併せて、原因に沿った漢方薬も必要となります。