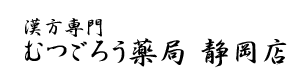どれも目的とする効果を狙って考えられた剤型ばかりですので、今回は様々な種類の剤型について取り上げてみたいと思います。
●丸剤
煎じ薬のように手間をかけることができないとき、非常に重宝する剤型です。
即効性よりも持続した効果を求める時などにも用いられます。
丸材は、粉末状の生薬を蜂蜜等で丸めることで味や香りもマスクされているので、漢方薬独特の風味を苦手とする人にも飲みやすくなっています。
代表的な漢方薬に、桂枝茯苓丸や八味地黄丸があります。
●散剤
漢方薬の材料となる生薬を、そのまま粉末状にしたものです。
煎じるという過程をたどると、有効成分が抽出されにくい生薬に向いている剤型です。
即効性は煎じ薬ほどではありませんが、丸剤よりも早い効果が期待できます。
代表的なものに当帰芍薬散があります。
●エキス顆粒剤
比較的よく目にする漢方薬は、エキス顆粒剤という剤型なのではないでしょうか。
生薬を煎じた液を乾燥させ、でんぷんや糖などを添加して作られた剤型です。その使い方や製造としてよく例えられるのがインスタントコーヒーで、必要な時に必要な分だけお湯に溶かして使えるという手軽さがあります。
エキス顆粒剤は、持ち運びが容易であるというメリットがあります。
また、一度に煎じて有効成分を抽出して作られているので、成分の同一性を保てることも利点としてあげられます。
●外用薬
漢方薬としての外用薬はいくつか存在し、よく知られたものとして紫雲膏などの軟膏があります。
紫雲膏は華岡青洲が考案したものであり、乾燥を種とした皮膚の疾患に効果を発揮する薬です。
また、火傷の場合に使うと、ケロイド状になることを防ぐことができるとされています。
このほか、坐薬や点鼻なども漢方の外用薬として使われています。
このように意外と知られていないのですが、漢方薬には実に数多くの剤型が使われています。
例えば、ひとつの剤型をしばらく飲んでいても、効果の発現が感じられない場合は、同一生薬を含む他の剤型に変えてみることでより期待する効果を生むこともあるのです。
注意したいのが、西洋薬と一緒に処方されたときに服用するタイミングですが、この場合は一緒のタイミングで服用するのではなく、少し間を空けてから飲むようにしましょう。