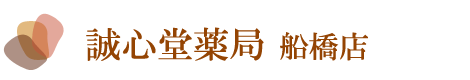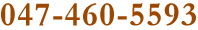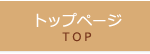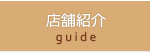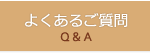今回は、不妊の原因を探る方法の一つであるPGT-Aについてまとめてみたいと思います

PGT-Aとは、着床不全や流産に関わる胚盤胞の染色体数の異常を調べる検査です。
染色体数は46本が正常ですが、それよりも多い、もしくは少ないと着床しにくかったり、流産しやすかったりすることがわかっています。
PGT-Aの方法は
採卵した受精卵➡胚盤胞まで培養します。
胎盤になる部分から5か所くらい生検してDNAを抽出し、染色体数に異常がないか調べます。
対象者は
①胚移植をしても2回連続で着床しなかった方
②2回の流産歴がある方
です。
※②の流産歴のある方は、ご夫婦の染色体数や構造の異常がないかを調べる夫婦染色体検査が必要です。
着床不全や流産の原因の約8割は受精卵の染色体数の異常だと考えられているようです。
そのため、PGT-Aのメリットは正常な胚の移植により、胚移植あたりの妊娠率が向上し、流産率が低下することが期待されています。
現在は、大規模な臨床研究が進行中なので結果はまだ出ていないのが実情のようですが、これまでわかった結果を示すと、以下のデータになります。
〇胚移植をしても2回連続で不成功だった方
・PGT-Aを利用していない方の妊娠率は30%
・PGT-Aを利用した方の妊娠率は70%
と高い結果がでています。
〇流産された方では
・PGT-Aを利用していない方の流産率は45%
・PGT-Aを利用した方の流産率は12.5%
に低下するという結果がでています。
染色体数の異常は、年を重ねるごとに増加します。
30代後半になると見た目が良好な胚盤胞であっても3個中2個は染色体異常と言われています。その点で、PGT-Aを利用して移植することで不必要な胚移植の回数を減らすことが期待されています。
ただ、デメリットもないわけではありません。
第一に生検をするため、胚盤胞へのダメージが懸念されます。
また、染色体数が正常であっても、30%は妊娠できず、流産率も10%程度あります。
5つの細胞を採取した際に2個が正常、3個が異常であっても正常な子供が生まれた例があるため、可能性のある胚盤胞を廃棄してしまうことも考えられます。
これらを踏まえた上で、判断が非常に難しいですが
PGT-Aの検査の有無を検討して実際に取り組んでいくかどうかの参考にしてもらいたいと思います。