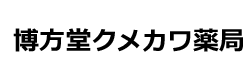花粉症は季節性アレルギー疾患のひとつで、花粉の飛ぶシーズンになるとアレルギー反応を引き起こし、特有のアレルギー症状を発症します。このアレルギー反応は過敏性反応とも言われ、通常多くの人にとっては無害である花粉などの抗原に対して過敏に反応して鼻、のど、目、皮膚などに炎症を起こして、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目の充血、痒み、皮膚の痒みなどの症状が発生します。現在は一般に原因である花粉を避ける、防ぐ、クスリでアレルギー反応を抑えることが行われています。
花粉症は、大気汚染や飛散するスギ花粉量の増大といった外的要因があることは確かですが、漢方では、この過敏性反応の根本に鼻や目、のど、皮膚など体表部の皮膚、粘膜の弱りがあることを重視しています。皮膚が弱いとかぶれやすく、赤くなったり、カユミ、炎症を起こしやすくなるのと似ています。この体表の皮膚や粘膜の機能を保ち細菌、ウイルス、花粉などの外敵から身体を護っているのが「衛気」とよばれる気で、「衛気」のパワーが不足すれば皮膚、粘膜は弱り過敏性反応を引き起こします。ストレス、運動不足、夜型生活また「労即傷気」といいます。過労は気を消耗し「衛気」の働きを弱めます。とくに身体を冷やす環境、飲食はできるだけ避けなければなりません。低体温の方に花粉症が多い傾向にあります。 このような視点から見れば花粉症は生活習慣病ということができます。「衛気」は飲食物から作られます。弱っている「衛気」のパワー強化には先ず、バランスのとれた食事が大切で、特にご飯、もち米、ヤマトイモ、じねんじょ、里芋、そら豆、納豆などの穀類、いも類、豆類などが胃腸を元気にして消化吸収能力を高め不足した気を補ってくれます。外の「衛気」を強めるには内の弱りを立て直す必要があります。また緑豊かな自然のなかでウォーキングや運動によってパワーのある大気を取り入れることは肺の機能を高め「衛気」を強化することになるのでお進めです。毎年この時期辛い方は避ける、抑えるだけでなく、強力に「衛気」を補い、温かい丈夫な粘膜を取り戻すため漢方薬の力を借りることがお進めです。一度ご相談ください。
| ツイート |
|
更新日: 2016/03/18 |
|
年内は、12月31日(木) まで営業 いたしております。
(30日(水)は、午後7時まで、31日(木)は、午後5時まで 営業いたします) 1月1日(金) ~ 1月4日(月) までお休み をいただき、 年始は、1月5日(火) より営業 いたします。 本年中のご来店に感謝し、来る年が良き年となりますようお祈り申し上げます。 |
| ツイート |
|
更新日: 2015/12/24 |
|
風邪はカゼと読みますが、漢方ではフウジャと読んでカゼなどの病気の原因となる病邪を意味します。風邪がひきおこす病気は、発病が急で症状の進行が速いのが特徴です。カゼの治療では、この風邪による病気は風寒、風熱、風湿などもう少し細かく分類されます。風寒によるカゼは発病の初期にゾクゾクと寒気があるのが特徴です。その他発熱、頭痛、鼻水、咽痛などの症状が出ますが、インフルエンザでは全身の関節にこわばり痛みが現れます。漢方ではこの時、病気はまだ身体の浅い所にあると考え、発汗により体表の風寒邪を発散し症状を改善します。葛根湯や麻黄湯はこの代表です。しかし汗はダラダラ流れるほどかいてはいけません。汗と一緒に元気も消耗されてカゼは改善されません。また汗が出ていても発熱などが改善しない場合や、横になっていたい、倦怠感が強いなどのカゼでは身体の元気が衰えているため、無理に発汗剤などで発汗すると、さらに元気を衰えさせて、カゼをこじらせてしまうので注意が必要です。この場合は元気を補いながら風寒邪を発散する薬を使います。またこのような時は薬を服んだ後に熱いお粥を食べるなど薬の働きを助けてあげることも大切です。身体を暖かく安静にし、胃に負担のかかるものは避けて、消化がよく暖まるものをとりましょう。
悪寒、発熱などのカゼ症状は、病気に勝つために身体が治ろうとする治癒反応ですが、不快な症状でもあります。しかし強い薬で一気にウイルスと戦うための発熱を下げてしまうと、免疫力は低下してダラダラと治りが悪くなったりします。一気に症状を取るのではなく、人間が本来持っている病気を治す力、治る力を高め、治せる身体にしてあげることが大切です。漢方薬はカゼ治療において一日の長が有ります。カゼは年齢や体質の強弱、食生活などの違いにより症状は様々です。その時の病態に合った漢方薬を選んで服用することが大切です。ご相談ください。 |
| ツイート |
|
更新日: 2015/11/19 |
|
四季の気候が人間や生物に与える影響を研究する生気候学という分野が今日ありますが、人と自然のつながりを重視してきた漢方では、昔から春(風)、夏(暑熱)、長夏(湿)、秋(燥)、冬(寒)という四季の気候変化が人や動植物の生命活動と深く関連していると考え、さらに”水はよく舟を浮かべるも、またよく舟を覆す”の例えがあるように、生命を育むこれらの気候変化は、場合によっては病気の原因である邪にも成ることを重視してきました。
日本の梅雨時もジメジメ、ジトジトして湿気の多い気候ですが、体が外の湿邪の影響を受けると、ある体質の人に、だるい、疲れる、眠い、胃がもたれ食欲が無い、浮腫、下痢、筋肉のこわばり、引きつり、頭重、関節痛などの症状をひきおこします。逆に梅雨時にこれらの症状が現れたら原因として湿邪を疑い、湿邪を取り除くことを考えます。 ではどのような体質の人が湿邪の影響を受けやすいのでしょうか。この湿邪は特に内臓の”脾”の働きを障害する特徴があります。”脾”はからだの中心にあり飲食物から栄養を取り出し全身に送り届けたり、水分の代謝も司っています。また”脾”の元気は全身の元気の源で”後天の本”といわれています。日頃、食事が不規則であったり、冷たい物をとり過ぎてお腹を冷やしたり、脂っこい物、甘いもの、酒などを暴飲暴食して”脾”が弱ると水湿が体に停滞して、お腹の元気が損なわれ、体表に元気が届かなくなるため、外の湿邪に犯されやすくなるのです。さらに”脾”が弱り湿が停滞していると、本格的な夏の暑さがおとずれると、熱を発散するためのエネルギーが不足して熱が体の中にこもり熱中症発症の原因となります。先人は「体に水湿の滞っている人は、必ず脾の元気が弱く夏の暑さにも犯されやすくなる」といっています。 日本は回りを海に囲まれていて潮湿の影響を受けやすく、胃腸の弱い人が多く見られます。さらに最近は自動販売機がどこにでもあり、冷たい飲み物が買えますが、脾虚体質の人では特に冷たい緑茶やビールのがぶのみはお腹を冷やし、脾虚となりやすいので注意が必要です。この時期の健康にはあたたかいお腹を保つことが大切です。 |
| ツイート |
|
更新日: 2015/06/18 |