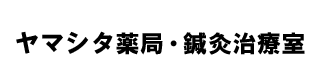今年の夏は暑くて、秋は台風で持っていかれ、そろそろ冬の寒さもやって来ようとしています。
前回のトピックスにも書かせて頂きましたが、こんな時には筋肉の疲労をベースにした「痛み」を伴う病気が多くみられます。
10月中ごろ、Nさん(76才、女性)から電話で相談がありました。
「脊柱管狭窄症なのだが、鍼で治るでしょうか」との事。何だか言いたい事がたくさんあるようで、「腰椎すべり症で手術と言われた事があるが関係あるか?」「貼り薬で治るか?」などなど、ちょっと混乱しているようです。
電話だけではさっぱり判らないので、来店してお話を聞かせて頂きました。
数年前、腰痛で病院に掛かったところ「腰椎すべり症」と診断されました。また、他の病院では「脊柱管狭窄症」と言われ、どちらの病院でも「根治するなら手術しかない」と言われたのに、貼り薬しかくれないそうで、どうしたら良いのかと思い悩んでいたそうです。
では、現在の症状はと言うと、腰痛があり左足全体(後面と概則)にしびれと鈍痛があるとのこと。確かに場所的には坐骨神経領域のようですし、SLR(下肢伸展挙上)テストは陽性でしたが、痛みの程度はそれ程強くは無いようです。
そこで、治療はごく普通の「腰痛のツボ」と「坐骨神経に沿ったツボ」を使いましたが、3回(週1回)の治療で腰痛、下肢痛、しびれなどの症状はほぼ消失、今後は調子が悪くなりそうな時にだけ治療することになりました。
最近、この手の相談が多いのですが、どうも勘違いされている方がいるようです。
そもそも”脊柱管狭窄症”とは加齢に伴い、脊柱管(椎弓と椎体に囲まれた神経の通る管)の内側にある後縦靭帯や黄色靭帯が緩んできて内腔が狭くなってしまう疾患です。
そのために下肢のしびれや痛み、および間歇性は行(少し歩くと痺れて歩けなくなるが、しばらく休むとまた歩ける)が起こります。
最近ではMRIなどで容易に画像診断する事が可能になりましたが、ではその治療法は?と言うと、何せ”老化現象”ですのでね、根本的な治療法はないのです。
また、”腰椎すべり症”は腰椎のひとつが前方にずれてしまうもので、中年以降の肥満体型(太鼓腹)の方に多い疾患です。この”腰椎すべり症”も根本治療はありませんし、実際には症状が無い人も多いのです。
※これらの疾患による症状が強く、手術が必要になる場合も確かにありますが、全部がそうではありません。
医学の進歩によって、身体の内部を一切の苦痛も無く見ることができるようになりました。
脊柱管狭窄症も腰椎すべり症も画像診断が可能です。
しかし、我々にとって、こういった疾患名は判断の参考にはなりますが、必要不可欠というものではないのです。
「どんな病気でも治す!」と言うつもりはありませんが、東洋医学(漢方薬や鍼灸)の効く疾患・症状はたくさんあります。根治できなくても良い疾患も多くあるのです。
「病名」「診断」にだけとらわれず、苦痛なく生活することを考えていきましょう。
| ツイート |
|
更新日: 2013/11/11 |
|
ようやく暑い夏も終わり、一年で最も心地よい季節”秋”になりました。
さあこれから、旅行やスポーツなどの外出の機会も増えてきます。 でも、まず先に身体のメンテナンスをして下さい。 夏は汗をかき、クーラーに当り、暴飲暴食をし、夜更かしをしていましたね? 皮膚のすぐ下の筋肉は慢性的な疲労状態になっているのです。 例えば皆さんは”ギックリ腰”って冬に多いと思っていませんか? 確かに寒くなると痛みの疾患が起こりやすくなりますが、ギックリ腰は秋に発症することが多いのです。 またこの時期、五十肩や寝違い(急に首が回らなくなる)も多く発生しています。やはり「筋肉の慢性疲労」が原因です。 軽いギックリ腰や寝違いは鍼治療に即効性があります。寝違いなら1~2回、ギックリ腰(何とか歩けるくらい)も3~4回くらいで治ってしまいます。 ただ、五十肩については、後になって拘縮や運動障害が残らないようにするために十数回の治療が必要になります。 同時に漢方治療として、消化吸収を助ける薬方(筋肉の栄養状態を改善)、ストレスを解消する薬方(筋肉の過剰な緊張を改善)、身体の冷え(全体および局所)を取り痛みを和らげる薬方、筋肉の痛みやコリを改善する薬方などを適宜併用していきます。 このような時、鍼灸と漢方は相乗的に効果が高まるようです。 最後にお願いです。 「痛いところ」は絶対に揉まないで下さい。必ず次の日は「揉み返し」で痛くなります。 何日か経って「コリ」がある場合は、少しずつ(思いっきりじゃ無いですよ)さすったり揉んだりするのは構いませんが、それでも「もっと強く、もっちもっと」と揉んではいけません。 だいたい筋肉の損傷が起こって、後から痛くなってしまいます。どうやら「揉み返し」というのはこれが原因のようです。 「痛いところ」は過剰に暖めないで下さい。 確かに温泉などにはケガや痛みに良く効く場合がありますし、何となく暖めると治りそうな気がします。 ただ、新鮮なケガや痛みは局所の冷却(アイシング)が原則です。炎症が大きくなってしまうと大変なのです。 秋から冬への身体のメンテナンスは「睡眠」と「食事」です。 良い「睡眠」は自律神経系を整え血行を改善し、しっかりした「食事」は夏の間に低下した体力を回復させるのです。 結果として身体のメンテナンス(筋肉のリフレッシュ)に効果があるのです。 さあ、秋はこれからです。 楽しみましょうね。 |
| ツイート |
|
更新日: 2013/10/25 |
|
今年は猛暑・残暑に続いて、秋になってもなかなか気候が落ち着いてくれませんね。
こんな時は「胃腸の不調」を訴える方が多く来られます。 さて私、昨日台風26号接近のニュースを横目に地元の研修会「消化器疾患の診断と治療のポイント」に行ってまいりました。 内容的には予想通り(良い意味で)でしたが、最近の新しい考え方「機能性疾患」についての講演は興味深いものでした。 つまり消化器疾患を「悪性(ガンなど)」と「良性」に分け、「良性」を”器質性”(臓器に病変があるもの)と”機能性”(臓器に病変が無いもの)に分けて考えるのです。 この中で気になったのは「良性」の”機能性”疾患です。 消化器は大きく①食道②胃③腸に分かれていますが、それぞれの部位で「良性」の”機能性”疾患があるのです。 例えば、①食道では「逆流性食道炎」のうちごく初期のもの(非びらん性胃食道炎)、②胃では「機能性ディスペプシア」、③腸では「過敏性腸症候群」が当てはまります。 「機能性ディスペプシア」の定義は、”特に原因が無く、胃のもたれ、膨満感、胸やけ、胃の痛みがあるもの”です。 また「過敏性腸症候群」についても”器質的な病変が無く、下痢・軟便、便秘を繰り返すもの”とされています。 これらの疾患に共通しているのは、これと言った原因が特定できず、個々の体質に加えてストレスによって誘発されることです。治療は対症療法で行われるようですが、お医者さんにとっても「治した!」「治った!!」という実感が無く、言い方は悪いですが「気合の入らない」疾患のようです。患者さんが焦れてしまって、いわゆる「ドクターショッピング」が多いのも特徴です。 そのために、これまで病院に行っても「気のせい」とか「安静にしていればそのうち」と言われ、薬物療法にも決め手が無く「消化剤と整腸剤しか出してくれない」「全然治らない」と来店される方もおられます。 しかしまあ、こんな症状こそ漢方の出番です。 この夏もこういうお客さんが何人かいましたが、何とか”食欲の秋”を迎えることができました。 昔からこれらの胃腸症状は人びとを苦しめてきたのです。 これまで数千年に亘って「漢方薬」が愛され、飲み続けられて来たのは、これらの症状を一つも切り捨てること無く、決して「気のせい」にせず真摯に向き合ってきたからでしょう。 皆さんの症状に合う漢方薬は必ずあります。 ご相談ください。 |
| ツイート |
|
更新日: 2013/10/16 |
|
母は今年83才。20数年来の橋本病はあるものの大変元気であります。
普段から体調管理のために漢方薬を服用していて、風邪などの体調不良も当然漢方薬で治してしまいます。 また、変形性膝関節症や腰痛、首の痛みなどには時どきに鍼灸治療を行っています。 そんな訳で、いわゆる”かかりつけ医”というものが無かったのです。 今日の朝の出来事です。 毎年のインフルエンザの予防注射などは家族や孫が行く時についでに済ませていたのですが、そろそろ「肺炎球菌ワクチン」を打つ時期かしらねえ、でも、いきなりと言うのも何だし予約でも取りにと、近隣の開業医に行ったところ「予防注射だけはしない」「うちの患者さんの分しか無い」「”かかりつけ”に行ってくれ」と言われたそうで、大変ご立腹の様子です。 「”かかりつけ”って言ったって、元気なんだから病院なんかに行きゃあしないよ!」 「これまで健康に気をつけて、たまに医者に行けば邪険にされる。もう予防注射なんかしないで死ねばいいんだろ?」 「そりゃあ注射(薬)だもの副作用があったり、老人は何が起こるか分からないよ。でもねえ、そんなに”元気な老人”ばっかりじゃあ無いだろうに」 確かに最近こういう話を良く耳にします。 どこに行っても予防注射ができない。どうしたら良いんだ・・・!? 最近では医院だけで無く薬局でも「かかりつけ」を唱えていますが、本当の「かかりつけ」って何なんでしょう。言葉だけが先走っているように思えてなりません。 とは言え、予防注射はやっておいて損は無いんだから、どこかでやろうよ。 ちょっと遠いけれど、連絡しておくからね。 まあ、あちらさんにも都合があるのだろうし、そこだけがお医者さんじゃ無いでしょ? 予防注射なんて”掛け捨ての保険”みたいなもので、インフルエンザの予防注射をやっていても罹る人はいるし、「肺炎球菌ワクチン」だって肺炎の40%位を予防するだけなんだから。でも、やっておいた方が良いんだからね、とお茶など飲みつつなだめましたが朝っぱらからえらい騒ぎでしたよ、まったく。 |
| ツイート |
|
更新日: 2013/10/07 |
|
そう言えば思い出しました。
去年の今頃も残暑が続いておりまして、”変な鼻炎”の人がいましたっけ。 その人はちょっとメタボなヒロシさん。 睡眠時無呼吸症候群でC-PAP(持続陽圧呼吸療法)を行っています。 残暑厳しいある日「鼻炎に効く漢方薬あるかな?」との事。 まあ、色々な薬方がありますけれど、何で今頃鼻炎かなあ、ブタクサアレルギーとかありましたっけ? 「いやいや、C-PAPのせいでさ、喉と鼻の奥がムズムズするのよ」 ほう、そんな事もあるのですね。 最近は保温・保湿装置の付いている装置もあるそうですが・・・? 「もうそれ使っているんだけどねえ」とお困りの様子。 実は私の友人にもC-PAP使っている薬剤師がいまして、まあ”大酒のみ”なので自業自得なんですが・・・。 彼が言うには「前は飲んだ翌日(酒が)残って辛かったが、C-PAP始めてからアルコールの分解が早くなったみたいで薬になったんだよね。」とは、まったくふざけた奴なのでございます。 それはさて置き、彼も喉と鼻は辛いと言ってましたね。 困っているヒロシさんに「二日酔い治るんだから良いんじゃない?」とは言えません。 そこで、「肺」の冷えを取る”甘草乾姜湯”と「表」の虚証を治す”玉屏風散”を差し上げたところ、程無く症状は回復しました。 その後ヒロシさんに、鼻は大丈夫?と聞くと「うん、全然。あれ何だったんだろうね」と不思議顔です。 どうやら、夏から秋に変わる「季節の変わり目」に一過性に起こる症状のようです。 今年もそろそろそんな季節です。 |
| ツイート |
|
更新日: 2013/10/01 |