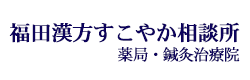ガン、リウマチ、糖尿、痛風、慢性腰痛、
神経痛、パニック障害、うつ病、・・・・・
長期に渡って付き合っていかないといけない病気は多い。
例えば、ガン。
血液検査などで数値が高いが、
エコーや内視鏡、組織検査で異常が見つからないケース。
あるいは、ガン細胞はあるけど
経過を見ながらいきましょう というケース。
こんな人は、絶えず不安と闘いながら
生きていかないといけないのがしんどい。
完全にガンを撲滅させることに必死になりやすい。
しかし、そうすることは
強い抗がん剤や放射線を使う事になる事が多く
正常細胞もやられてしまって
肉体的精神的ダメージが逆に大きくなってしまう。
そこで、ガンと「共同生活」をするという考え方。
「今、元気に生きている」という事実。
これを継続することに全力を尽くす。
感受性のある低用量の抗ガン剤で、
あるいは、医薬品に近い免疫活性のサプリで、
あるいは、漢方で、
あるいは、鍼灸で、
ガンを撲滅するのでなく
ガンの成長を妨げこれ以上ガンが大きくならないように、
いつまでたっても
余命○年を目指す。
無くなりそうで無くならない
40年前から、「あと40年分の備蓄」の石油のように。。。
例えば、リウマチ
血液検査はいい事ないけど
体の調子はいい!
そういうケースは多い。
血液検査も大事だけど、
当人が気持ち良く日々を過ごせるのが一番。
必要最小限の薬にして
副作用軽減して、快適ライフを。
例えば、うつ、気分の落ち込み、パニック、・・・
てんこ盛りの薬で
副作用に悩まされるケースも少なくない。
まさに、減薬のススメ!
「薬を止めれば病気は治る」
という人もいるが、
そこまでとは言わないが
薬を整理して 徐々に減薬していく方が良い。
俗に言う医源病だってある。
長期戦には、
快適ライフのお手伝いが必要。
そういう立位置に東洋医学やカウンセリングは最適と思う。
是非、一緒に歩みましょう。
不健康だけど健康?病気と付き合うという事
福田漢方すこやか相談所 薬局・鍼灸治療院 (奈良県吉野郡)
| ツイート |
|
更新日: 2013/11/21 |