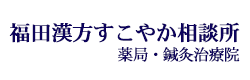2011年11月4日 台北医科大学にて
日本臨床食物機能研究会海外研修会が行われました。
台湾と日本、両国の代替補完医療関係者の情報交換を目的として
台北医科大学の協力で開催されたものです。
産業技術総合研究所の分子複合医薬研究グループ主任研究員 辻 典子 氏より
経口免疫寛容と制御性T細胞、それらを支える腸内環境について発表があった。
どうやら、免疫システムは抗炎症と感染防御の両方が必要でそのバランスをとるために
GALT(消化管免疫組織)が免疫恒常性の任を担っているとのこと。
ちょっと難しいですが、
如何に腸管免疫が大事かという事です。
で、オリジン生化学研究所の前田所長の発表では、
臨床病期Ⅲ期とⅣ期ガン患者36名に対して
オリザロース(スーパーオリマックス)の摂取を含む代替補完医療を実施し5年間、
生存期間の調査を行ったところ、Ⅳ期患者22名中14名生存63.6%と
日本における統計の20.8%を大きく上回った。
との報告でした。
スーパーオリマックスには
今後も期待したいです。
ガン 台北医科大学にての発表より
福田漢方すこやか相談所 薬局・鍼灸治療院 (奈良県吉野郡)
| ツイート |
|
更新日: 2011/12/17 |