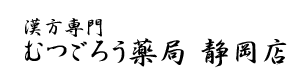受精卵を育てる力をさまたげている要因は?・・・漢方で体質改善を
赤ちゃんを授かっても、残念ながら流産を繰り返してしまう不育症。流産や不育症で相談にいらっしゃるかたは、
①血行が悪くて卵に栄養が届かず、きちんと育たないタイプ
②体内に悪い血のかたまりなどがたまっていて、悪いものに栄養分がとられてしまい、卵が育
たないタイプ
の大きく2つに分かれます。
①のタイプは冷え性で顔色が悪く、体はどちらかというとヤセ型、運動不足。②のタイプはどちらかというと太っていてむくみやすい、顔がのぼせやすいという傾向があります。
いずれのタイプも、妊娠はできるけれど、実はまだ体が赤ちゃんをはぐくむ準備ができていないという状態。女性が排卵していて精子が元気であれば、運よく受精・着床まではするもの
の、そこから受精卵を育てていく力がないのです。こういうかたたちには、漢方薬を使っての体質改善が有効です。
①のタイプのかたには、冷えをとり、血行をよくする処方、
③のタイプのかたには、体の中にたまった悪いものを体外に出す少し強めの薬を処方します。
また、私たちが見た限りでは、不妊症と同じように、不育症に悩むかたたちには基礎体力が弱っているかたが多いようです。特に足腰が弱いかたは流産しやすいという印象があります。 赤ちゃんは臨月には3Kg近い体重になりますし、羊水などを入れたら4~5g以上の重さになりますね。それをしっかりと支えるには、腹筋、背筋、腰、足など下半身を総動員しなければなりません。最近の若い女性の中には腹筋が1回もできない人も珍しくないとか……。そんなに体力がなくては、1カ月間赤ちゃんをおなかの中で育てるのはやはりむずかしいのでは……と思ってしまうのです。
ですから、私たちの薬局では不妊症や不育症のご相談にいらしたかたに、漢方薬を処方するだけでなく、基礎的な体力をつけるため「ぜひ、なわ跳びをしてください」と指導しています。治
療は赤ちゃんができれば終わりではありません。めでたく妊娠したら、健康な妊娠生活を送り、母子ともに無事に出産を迎え、その後は母乳でしっかり子育てをする。そこまでいって初めて治療が完結すると私たちは考えて、お話させていただいています。
せっかくがんばって不妊治療をして赤ちゃんができたのに流産してしまうのはとても残念ですし、精神的なダメージも大きいでしょう。赤ちゃんが授かったら、その大事な命をおなかの中
でしっかり育てられるよう、そして元気な赤ちゃんを産み育てられるだけの体力を妊娠前からの今からつけておくことが大事です。
また、仕事は心身ともに大きなストレスがかかります。不育症のかたには、次回、妊娠なさったら、できるだけ仕事をセーブすることをすすめています。
あたためる処方と甘いものを断ちプラス運動で、無事出産
今回ご紹介するのは8才、身長160㎝、
体重や営のスラリとした女性です。妊娠しやすいタイプではあるのですが、残念ながら過去に4回もの流産を経験なさっています。そのうちの1回は妊娠5カ月目に入ってからの死産という悲しい結果でした。体格は、パッと見た感じではそんなにやせている印象はありません。が、顔色は青白く、目の下にはっきりとくまが出ていてとても疲れているように見えます。体質は冷え性で腰やおなかのあたりがいつも冷たい感じ。冬は電気毛布を使用することもあるそうです。また、甘いものが大好きでクッキーやケーキを食べない日はないとか。
このかたの場合、妊娠しても出産まで妊娠状態を維持するだけの体力がなく、また冷えも強いので、本来あたたかく赤ちゃんにとって居心地のいいはずの子宮環境がととのっていないのではないかと考えました。
そこでまず下腹部をあたため、下半身の出血を改善するヨモギや当帰の入った漢方薬を
妊娠前から服用していただきました。同時に冷えの原因にもなる甘いものをいっさい控える、毎日適度な運動をする、腹巻をする、を実行していただき、4カ月後に妊娠。出産まで同じ処方を継続していただき、無事に3000gの女の子を出産されました。