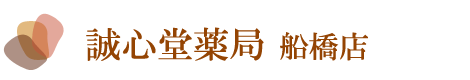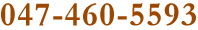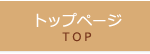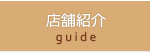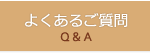無排卵を防ぐためには、
しっかりと睡眠をとり、十分な睡眠をとるなど生活のリズムを整え、規則正しい生活をすることが重要です。
食事制限を伴う過度のダイエットや太りすぎ・過食を控えることです。
心と体が元気であるように、自分にあったストレス対策を上手に取り入れて、ゆったりと過ごせるようにしましょう。
卵子の栄養となる気血を生み出す脾胃(胃腸)を常に良い状態にしておくことが大切です。
西洋での治療法:
妊娠を希望されている場合は、排卵誘発剤で排卵を促すことが多いです。妊娠をすぐに希望されていない場合は、ピルなどのホルモン剤でホルモンバランスを整えます。
漢方の治療法:
正しい生理周期を作っていくことを目標に、からだ全体のバランスを整えていきます。
ピルなどの薬を使っている場合でも、漢方薬を併用しながらからだの状態を整えていくこともあります。
無排卵は、
卵子が排卵できる大きさにまで成長していなかったり、
卵巣から飛び出るための力が不十分な事で起こりやすい状態です。
漢方では、卵子の栄養である気血の不足した『気血両虚』、
排卵を起こす力となる気血の流れの滞った『気滞瘀血』、
さらに卵子の質を左右する子宮や卵巣の機能低下や女性ホルモンと関係の深い『腎虚』
を考えます。
それぞれに対して『補気・補血』・・・十全大補湯など 『理気・活血』・・・芎帰調血飲第一加減など 『補腎』・・・六味地黄丸など考慮します。
高プロラクチン血症や多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)の場合、「気の乱れ」との関係が考えられるため、イライラなどの肝鬱気滞や精神不安定の心火亢進と捉え、逍遥散や焙じ麦芽、竜骨牡蛎を含む漢方を用いることがあります。
以上です。
| ツイート |
|
更新日: 2022/04/03 |