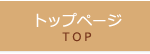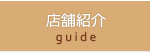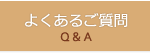花粉症はなぜ起きる
花粉が体内に入っても全ての人に花粉症の症状がでるわけではありません。それは粘膜に付着した花粉を取り去るために働く免疫反応に差があるからです。花粉が体内に侵入するとマクロファージに捕食されますが、このとき、花粉に対する抗体(IgE 抗体) を作り易い人ではIgE 抗体が多量に産生され、マスト細胞の表面に結合します。その後、花粉が体内に入ると、花粉とマスト細胞に結合しているIgE 抗体が反応してマスト細胞からヒスタミンやロイコトリエンなどの物質が粘膜に放出されます。これらの物質は鼻や目の粘膜に作用して鼻水、涙目、くしゃみ、鼻づまりなどを起こします。これが花粉症のつらい症状となっています。
花粉症の薬について
花粉症で現れる症状は人それぞれで、その中でもくしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみは4 大症状と呼ばれています。それらの症状を薬で抑える際には、症状、部位、使いやすさなどに応じたものが選択される必要があります。花粉症の薬には、くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどの鼻炎症状に小青龍湯、鼻づまりに葛根湯加川芎辛夷、くしゃみ、鼻水、目のかゆみに抗ヒスタミン薬、鼻づまりにロイコトリエン拮抗薬のように、
得意な症状があります。抑えたい症状について医師、薬剤師とよく相談しましょう。
小青龍湯
原典「傷寒論」 麻黄の青い色が小青龍湯の名前の由来と言われています。
構成生薬
麻黄(マオウ) 芍薬(シャクヤク) 乾姜(カンキョウ) 甘草(カンゾウ)
桂皮(ケイヒ)細辛(サイシン) 五味子(ゴミシ) 半夏(ハンゲ)
小青龍湯は三世紀頃に張仲景が編纂した「傷寒論」に収載されている8 種の生薬で構成された漢方
薬です。花粉症のほか、アレルギー性鼻炎、気管支喘息などのアレルギー症状にも効果があります。
葛根湯加川芎辛夷
原典「本朝経験方」 大陸から伝わった処方を基に、日本独自に加減された処方です。
構成生薬
葛根(カッコン) 麻黄(マオウ) 桂皮(ケイヒ) 大棗(タイソウ) 芍薬(シャクヤク)
生姜(ショウキョウ) 甘草(カンゾウ) 川芎(センキュウ) 辛夷(シンイ)
葛根湯加川芎辛夷は鼻づまりのほか、蓄膿症、慢性鼻炎にも効果があります。