目を通していただけると幸いです。
まず、最初にお伝えしたいことがあります。
私達のお仕事は「ただ漢方薬や商品を売ること」ではありません!
お話を伺う中でお薬が不要と考えられれば、ご相談の上でまずは何もご購入いただかず生活の中でできる養生法をお伝えしたり、必要に応じて適切な医療機関をご紹介することもまた、相談薬局としての務めです。

例えば先日、このような方が来局されました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「昨日引越しして、手を痛めたかもしれない。湿布をください」
お話を伺っていると痛みのある手は力が入りにくく、そして同じ側の足にも力が入りにくいことが分かりました。詳しくお話を伺った後、湿布薬の購入ではなく、脳外科のある病院をできるだけ早く受診するように勧めました。
しばらくして、その方は元気に再来局されました。
そして、約1〜2ヶ月の間、受診を勧めた病院で入院治療を受けられていたことを教えてくださいました。
診断された病名は、脳梗塞でした。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
よくある症状でも、そこには大きな疾患が隠れていることもあります。
薬局ではできない検査が必要な時等、専門の医師に診ていただいた方が良い場合もあります。
それを見極めるのも大切なお仕事です。
もちろん、漢方相談薬局を続けられているのは、お客様が商品や漢方薬をご購入してくださるおかげですし、店頭に並んでいるのは自信を持ってお勧めできる商品ばかりです。
しかし、私達は必要以上のものを売りつけることは致しません。
相談自体は無料でお受けしておりますので、お辛い症状のある方、お気軽にお越しください。
心身ともに生き生きとした毎日を送れること、そのお手伝いができることが私達の一番の喜びです

最後になりましたが、以下の言葉が、みどり薬局の信念をまとめたものです。
◇みどり薬局の信念◇
自信のある薬を差し上げたか
本当に親切であったか
充分に説明して差し上げたか
満足してかえられたか
努力に不足はなかったか
今年度も、皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。
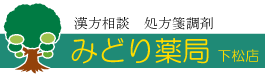
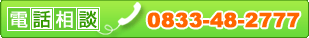

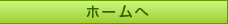
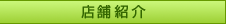
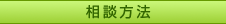










 」
」 」
」



