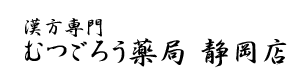私が高校生のときにアトピー性皮膚炎になったときに皮膚科の先生に教えていただきました。そこで「大学病院を紹介されるほどのひどいアトピー性皮膚炎だった方が、食事を徹底したことで、いつしか病院通わなくて良くなるほど改善した。」と聞きました。食事でそこまで良くなるとはと驚きました。
実際に極力甘いものと小麦の食べ物を控えたところ、3~4ヶ月あたりでアトピーの出る範囲は少なくなりました。また、食事が元に戻ってしまうと症状が悪化したので食べたものは体に大きく影響していることを実感しました。
砂糖と小麦がアトピーに良くない理由としては、腸内環境と血糖値が関係しています。砂糖と小麦をとると、血糖値の変動が激しくなります。そこで、血糖値を安定させるために、コルチゾールという副腎皮質ホルモンが分泌されます。コルチゾールは、アレルギーの治療に使われるステロイドと同じはたらきをするホルモンです。そのコルチゾールが血糖値を安定させるために使われてしまうと、アレルギーを抑えるはたらきができなくなるため、アレルギーの症状が悪化してしまいます。また、体の免疫の7割は腸で作られています。悪玉菌と善玉菌のバランスがいいと免疫機能が良く働きます。砂糖と小麦は悪玉菌のエサとなるため、腸内環境のバランスを崩し、アトピーを悪化させます。
私の経験からも、症状の軽減・悪化には食事は大きく関係しています。漢方では体に溜まった毒を出し、腸を立て直すことでアトピーを根本的に良くしていきます。アレルギーなどでお困りの方はお気軽に相談してください。
薬剤師 木村望実