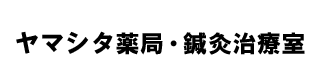今日は20年ぶりの大雪だそうで、昼間だというのに人通りもまばらで、まあ暇な訳なのでお付き合い下さい。
「傷寒論」という書物は、風邪などの感染症の初期からこじれてしまった状態までの治療法について、事細かに書いてある、我々漢方家のバイブルと言うべきものです。
ただ、何せ昔の本なので漢方理論の基礎「陰陽」「表裏」「虚実」を含めて非常に難解なのが欠点です。
そこで今回は”風邪をケンカに例えて”考えてみましょう。頭の中に特大スクリーンを広げて、3Dでビジュアル化してみて下さい。
場所は郊外の河原(これが「表」という場所)。”俺たち”の中学校と”外邪”の中学校は昔から因縁のある間柄です。今日も乱闘(感染症)が始まりそうな雲行きです。それでは、始まり始まり・・・!
この河原は俺たちの村と「外邪」の村を分けている。
外邪中学にはは乱暴なのが多いから、しっかり栄養を摂って体力つけてガードを固めておかなくちゃならない。
あ、外邪中学の奴らが攻めてきた!みんなに知らせろ!防衛線を作れ!
仲間がわらわらと集まって来る。さあ、戦いが始まる。
始め(太陽病期)は俺たちも力がみなぎっているので、フルボッコのシバキ合い、見た目は派手なケンカ(実証)になる。
もしも、普段から栄養が摂れなくて体力が無くガードが甘かったら、見た目の派手さは無いものの実はより深刻な状態(虚証)なのだ。
※この時期、実証には葛根湯などを、虚証には桂枝湯などが使われます。
そのうち、俺たちも傷つき疲れ、次第に戦いの場所はもっと山側の林に移る(少陽病期に移行)。始めの頃のような派手さは無く、もみ合い寝技の応戦になる。俺もだんだん疲れてきた。
※この時期、病気は呼吸器、消化器へと広がって行き、小柴胡湯、柴胡桂枝湯などが使われます。
外邪の連中しつこいなあ、なかなか手出しをやめない。争いの場所が大事な田圃(腸などの消化器系)に移ってしまった。俺たちはもうヘトヘトだが、泥んこの中で外邪の奴らを押さえこんでいる(陽明病期)。
※重症化して、熱が出て、汗をかき、便秘している時期。白虎湯などの清熱剤や、調胃承気湯や小承気湯などの瀉下剤を使います。
あれれ?外邪がしぶといなあ、村に攻め込まれてしまった。俺ももうだめかもしんないなあ。身体がしんどくて、うすら寒くて・・・。
※この時期(陰病期)、病状が更に悪化すると食欲が落ちたり下痢したりする。小建中湯で脾胃を補ったり、人参湯や真武湯で温めたり、病が治らず苦しんでいる時の最終的な手段として茯苓四逆湯などを使います。
私は「難しいことは何かに例えて理解しよう」という主義の人でして、どうでしょう、何となくイメージできましたか?
| ツイート |
|
更新日: 2014/02/08 |
|
いやはや、年を取るごとに年末年始は忙しくなるものです。
それも”クリスマス”とか”年越しカウントダウン”みたいな楽しいイベントに参加するとかならまだ良いのですが、義理を欠かせない忘年会や新年会に出なくちゃいけない。 また、今回は年末年始8連休で、普段は漢方相談・鍼灸治療の私にも休日・夜間診療の調剤にお呼びがかかる。 おまけに冬は体調を崩しやすい季節で「誰それが入院した」とか「もう危ない」とかスリリングな情報が錯綜するのであります。 そんなこんなで、ここに顔を出すのが遅れてしまいました。改めまして「あけましておめでとうございます。」 あ~新年の挨拶がすんでスッキリしました。 さて、今年最初のテーマは「冬のスキンケア」です。 皮膚は身体の一番外側の組織で、外界からの刺激や病原菌の侵入を防いだり、気温や湿度などを感知して体温調節をします。 東洋医学では「脾は肌肉を主る」と言われ、「脾=消化吸収機能」という内臓の働きがきちんと行われることが「肌肉=皮膚および皮膚の機能」を支配していると考えられていました。この辺が東洋医学(古典的な医学)理論の素晴らしいところです。 現代の医学は、皮膚は皮膚、内臓は内臓と考え、個々の疾患として捉えがちです。 「いくら塗り薬を付けても治らない」「一度良くなってもまた痒くなる」というのは、皮膚疾患を”皮膚だけの病気”と考えているからです。 例えば、子供のアトピー性皮膚炎に良く使われる黄耆建中湯や小建中湯は元々「脾胃」を補う薬方です。 また、成人型アトピー性皮膚炎は色々なストレスが原因になっていることが多いので「肝」の”気うつ(ストレス)”を調整する柴胡剤(柴胡を含む薬方)を考えます。 あるいは、老人に多い乾燥性皮膚炎には皮膚を潤す作用のある地黄剤(地黄を含む薬方)を使うのです。 こういった『治療』以上に大切なのが『スキンケア』です。 冬は気温が低く活動性が悪くなりがちです。そのため皮膚の血行が悪くなり皮脂(角質層を覆っている油性幕)が減少します。 加えて湿度が低いために皮膚の乾燥が促進され、皮膚の易刺激性(ちょっとした刺激で痒くなる)、皮膚の掻き壊しが起こります。このような状態を”ドライスキン”と言い、積極的なスキンケアが必要なのです。 当店では治療のための漢方薬に加えて、スキンケア用の薬局製剤を用意しています。 ドライスキン(入浴後肌がつっぱる、痒くなる、何となく粉が吹いたような)には『AEP軟膏』がお勧めです。 手足・指先のひび割れには『UHEクリーム』『UHクリーム』が良くききます。 あと、指先がぱっくり割れてジンジン疼くような時は紫雲膏を塗ってゴムサックで直接覆うと早く治ります。 何にしても、自前の皮脂を大切にして身体を洗い過ぎないことですね。ゴシゴシこすっちゃダメですよ。 まあ、最近の「清潔志向」は少々過剰ではないかと思いますね。 |
| ツイート |
|
更新日: 2014/01/23 |
|
いやはや、暑いだの寒いだの言っているうちに年末ですねえ。
放っておいても新年はやってきます。あまりジタバタしないで新年を迎えましょう。 無理をすると”寝たきり正月”になりかねませんからね。 11月頃から急に「ぎっくり腰」が増えてきました。 暑い夏、厳しい残暑、大型台風などの異常気象など、環境から受けるストレスは大変なものだったのでしょう。 体中の筋肉が疲労の極に達し、腰や背中の筋肉の一部分に「炎症」が生じ、次第に大きくなりついには筋肉全体の動きを止めてしまうのです。 ですから、ぎっくり腰の人は「腰が痛い」よりも「どうやったら立てるか分からない」とか「腰が板のようだ」とか言うのです。 治療の基本は、急性期(発症後1~2日)は疼痛局所のアイシングとサラシやテーピングなどによる固定です。絶対にやってはいけないのがストレッチやマッサージ、あるいは温泉や入浴による加温です。この時期、鍼灸治療は軽く、あくまでも補助的な選択になります。 痛みがひどい場合、消炎鎮痛剤や漢方薬でしたら芍薬甘草湯を使います。 亜急性期(発症後3~5日)からは鍼灸治療が有効です。できれば3~4日ごとに治療すると良いでしょう。 補助的な漢方薬として桂枝茯苓丸などを使います。 回復期(発症後2週間以降)には、軽い運動から始めて下さい。 腰の状態と相談しながら運動強度を上げていきます。疲労回復のための入浴、筋肉疲労の改善にマッサージなども良いと思います。 何度もぎっくり腰になる方には八味地黄丸、牛車腎気丸などが良いでしょう。 今年最後のお便りです。 皆さん、良いお年を迎えて下さい。 |
| ツイート |
|
更新日: 2013/12/25 |
|
寒くなると、いわゆる”古傷”が痛くなることがあります。
腰とか首とか、大きい関節が痛くなった場合はもちろんですが、たとえ小指1本痛くなったとしても何かと不便で、憂鬱なのは同じです。 美容師のK君、最近は出世してカットを任されているそうですが、仕事によって手首に慢性的な痛みがあります。 病院で湿布薬をもらったが治らないという事で相談に来られました。動作を確認してみると、手首の背屈(手先を上に曲げる)時に手首の中央付近に痛みが起こります。 ここはツボの名前で言うと「陽池(ようち)」なのですが、経絡とか陰陽五行などは余り気にせず、動かすと痛いところ、押すと痛むところを治療点とします。 使うのは”もぐさ(ヨモギの葉裏の細かい毛)”でも宜しいのですが、自宅でやれるように簡単なお灸(せんねん灸とかカマヤミニなど)を使いました。毎日1~2個、火傷しないように注意して続けてもらったところ、約2週間で痛みは治まりました。 元板金工のMさん、20年前に壊してしまった指が痛いとの相談です。見ると中指の第2関節が変形しており動きません。 本人は「仕事中に潰しちゃってさあ、放っておいたら動かなくなった」「冬になると痛くって」と言います。 こういう場合はツボとか一切考えず、痛むところを治療点にします。関節の裏と表にそれぞれ1~2個、毎日お灸(簡単なお灸)をしてもらいました。治療開始後約2週間で痛みは楽になったそうです。「ああ~あ、あの時きちんと治していればなあ」とMさん、後悔の日々だそうです。 上の例のような外傷によるもの以外に、”ヘバーデン結節”という関節が腫れて変形する病気もあります。原因は良く判っていないのですが、壮年以降の女性に多い疾患です。手の指(人差し指や中指の第1関節に多発)の起こり、初期には柔らかい腫れですが、次第に固くなり変形を起こします。 このようなものにも”お灸”は効果的です。 注意して欲しいのは、火傷をしないように、熱かったら我慢せずにお灸を取り去ってもらうことです。 慢性的な痛みに意外と効いてくれる治療法です。 毎日ちょっとずつ良くなっていきますので焦らずに。 |
| ツイート |
|
更新日: 2013/12/09 |
|
今年は異常気象や台風の当たり年で、いわゆる「気象病」が良く見られました。
「気象病」というのは、特定の気象状況や気圧配置などによって誘発される疾患のことで、例えば”低気圧が近づくと喘息発作が起こる”という現象は良く知られています。 東洋医学では気象状況などを含めた外部環境を”外邪(六淫:風、寒、暑、湿、燥、火)として、病気の原因としています。 日本には四季がありますが、ちょうど良い季節は短く、皆さん「夏暑く冬寒い」と言われます。 特に島国日本では、周りが海に囲まれており、雨量も全国的に比較的多いため、「湿」すなわち”水毒”による疾患が多いようです。 Yちゃんは23才のOLさん、中学生の頃からアトピー、生理不順、頭痛、胃腸のトラブル、社会人になってからは人間関係ストレスと、何だかんだと相談に来られます。 実は彼女のお母さんが大の漢方・鍼灸ファンでして、一緒に来ていた娘ちゃんも自然に治療の対象になってしまいました。 最初、お母さんは”むくみ”と”身体のだるさ”を訴えて来店しました。まずは鍼灸的な診察をしてみたところ、足のすねや手指などに目立つ”むくみ”はありません。腹部はやや膨満していますが服力は中くらい、表情が冴えない感じだったので聞いてみると「月に2~3回リンパ・マッサージに行って、顔や首、背中、脇を”流してもらう”とすっきりする」との事です。 確かに頭から背中、特に首の後ろ(鍼灸で言うところの”膀胱経”)あたりに”むくみ(筋肉のコリでは無い)があります。 これらの所見に漢方的な診察を加え、竜胆瀉肝湯(一貫堂)を中心とした薬方を使ったところ次第に症状は改善しましたが、時々いろいろな愁訴があり別の薬方を加えて対応してきました。 この方は元々”水毒体質”だったのでしょう、「めまい」「耳鳴り」「のぼせ」「食欲不振」「下痢・軟便」などなど、結果的に使った薬方は殆ど”水毒”関係のものばかりです。 そして娘のYちゃん、親子なんですねえ。めまいや動悸(ストレスかなあ?)には苓桂朮甘湯、生理不順や冷え性には当帰芍薬散、胃腸トラブルには人参湯と”水毒”対応が有効なのです。 しかしねえ、最近は二日酔いの早朝、開店前にもかかわらず「飲み過ぎちゃった、五苓散ちょうだい」と電話をかけてくる”強者”になっております。 ・・・・困ったものです。 |
| ツイート |
|
更新日: 2013/11/24 |