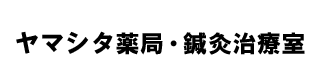やっぱり8月も暑いようです。
外で働く方々、熱中症には十分お気をつけ下さいね。
新聞、テレビなどで「こまめに水分を摂ってください」と言ってますが、具体的にはどうしたら良いのでしょう。
元々、私たちは余り暑くもなく、ジメジメしてもいない環境でも、気が付かないうちに身体の表面からの蒸発や呼吸中の湿気によって1日700~800mlの水分を失っています。
また、体内の老廃物などを排泄する尿や便によって1日1500~2000mlの水分が失われます。
これらを合わせると生命を維持するために、1日あたり(最低)約2000~2500mlの水分を摂取しなくてはなりません。
健康な人であれば、通常の食事とお茶、コーヒーなどで十分賄える量ですが、汗をかいた場合は、その分をこれに加えて水分補給を行う必要があるのです。
更に、胃腸の能力には限界があって、身体がカラカラになってしまってから慌てて水をガブ飲みしてもすぐには吸収できず、下痢をしたり嘔吐をすることもあるのです。よく夏場に子供がそんな症状を起こします。
夏場の水分補給のコツ
①経口補水液を用いる
コンビニなどで売られているスポーツドリンクは糖分が多すぎて「喉が渇く」とか「甘すぎる」と言われる方も多いようです。しかし、シュガーレス(砂糖不使用)だと、逆に水分の吸収が悪くなってしまいます。
そこで、ご自宅で簡単に作れる経口補水液のレシピをご紹介します。
水1ℓに対して食塩3g(ティースプーン軽く1杯)と砂糖40g(カレースプーン軽く3杯)、味付けとして濃縮レモン(ポッカレモンとか)、果実酢(飲むお酢)などを適宜加える。ただし、薄~い味付けにして下さい、へたに濃くすると逆に喉が渇いてしまいます。
②正常な人でも水の吸収能力は1時間で200~300mlと言われています。汗をかく前、汗をかいてる最中、汗をかいた後に意識的に、目安としては”ひと口”か”ふた口”ずつ補水を行って下さい。
③特にお子さんの場合、気が付かないうちに「脱水」「熱中症」になってしまいます。飲んだ量を確認するのではなく、尿の量をチェックしてみて下さい。おしっこが出ているうちは水分の不足はありません。
| ツイート |
|
更新日: 2013/08/05 |
|
いや、もう暑い日が続いています。
「ああ、かき氷が食べたい」「ぐう~っと冷たいビールを」なんて事を繰り返していると夏の終わりに『夏バテ』が待っています。 『夏バテ』とは一口で言うと”胃腸に持続的に過重な負担がかかって起こる機能低下症”です。 症状は多様で食欲不振、下痢、軟便、疲労倦怠、体重減少、不眠、嗜眠(眠くて堪らない)、微熱などの他、ぎっくり腰や膝痛の原因にもなるのです。 漢方薬にも『夏バテ』に使う処方は沢山ありますが、意外と効果的なのが胃腸薬(健胃消化剤)です。 いえいえ、毎日食後に3回飲む必要はありません。 「そんなに食べていないのに満腹」とか「前の食事が残ってる感じ」あるいは「食後1時間以上経っているのに消化していない」ような時にだけ服用して、胃腸の働きを助けてあげるのです。 胃腸が楽になれば消化吸収機能が温存でき体力低下も防げます。 お家の”薬箱”の中にある「○○胃腸薬「とか「××健胃消化薬」で結構です。 ただし、効果的に消化吸収を行うためには”消化酵素(炭水化物の消化酵素、脂肪の消化酵素、タンパク質の消化酵素)のバランス”が大切です。 加えて適切な漢方薬を使うことにより、『夏バテ』から早く解放されるのです。 一度お試し下さい。 |
| ツイート |
|
更新日: 2013/08/02 |
|
冬になると手足の先が冷える、お腹や背中全体が冷える。季節に関わりなく常に身体が冷える。足が冷えて頭がのぼせる。クーラーが嫌いで家族と喧嘩が絶えない・・・。
一口に「冷え症」と言っても色々なタイプがあるようです。 東洋医学では「気」「血」「水」の3要素が生理機能を動かしていると考えられており、これらに異常が起こると病気になるのです。 “冷え症“の原因となるのは「気虚」「気逆」「血虚」「瘀血」「水滞」などが考えられます。 「気虚」は元気が無く、疲れやすく、食が細い人です。冬になると“こたつ虫”になってしまいます。 「気逆」は気の巡りが悪くなり、頭がのぼせて手足が冷える方です。 漢方薬以外に鍼灸が効くことが多いタイプです。 「血虚」は乾燥肌、抜け毛、目眩、顔色不良、不眠などの睡眠障害のある人です。 「気虚」と併存することが多く、全身に冷えを感じます。現代医学の“貧血”と同じではありません。 「瘀血」は全身、あるいは局所に血液の流れが悪いところがある人です。 女性では生理不順、月経困難症の原因になります。血行不良による手足の冷えが現れることがあります。 「水滞」は生理的な水の出入りに異常が起こったものです。 組織中にいらない水分が溜まると「気」「血」の循環が妨げられ冷えを起こします。 ~冷え症対策~ (1)無理な薄着を避け保温に注意しましょう (2)冷たい食べ物、陰性食品(季節外れの果物・野菜類)の食べ過ぎに注意しましょう (3)ストレスを避けましょう (4)できるだけ身体を動かしましょう |
| ツイート |
|
更新日: 2013/08/01 |