きぐすり.com は、漢方薬、女性の健康、サプリメント、ハーブの情報を専門家がやさしく解説しています。
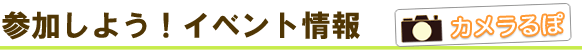

イベントの様子を現場から皆さんに報告します。
自然の中には色んな色の天然の染色原料が眠っています。
特に草木のほとんどに無限の色の素が隠されています。赤色染料、青色染料、黄色染料。
(但し、緑色は葉緑素だけなので黄色染料と青色染料をうまく重ね合わせる工夫が必要で、今回緑はありません。)
今回のイベントでは藍(アイ)がテーマでした。
薄い青色から濃い青色へ。自然な色から自然の優しさを感じる穏やかな時間を過ごせました。
講師には「きぐすり.com」でも、おなじみの比治山大学短期大学部教授 寺田勝彦先生を迎え、3月18日広島市植物公園で開催された草木染講習会。
では、当日の様子をご紹介します。
開催日当日は10時半頃に植物公園に到着。
先ず、11時から資料館1階で草木染展の解説を寺田先生に1時間ほどかけてじっくり聞かせていただきました。これも寺田先生の巧みな話術の賜物でしょうか?
お昼からは待望の藍(アイ)を使った草木染めの実習。
丁寧に一人一人手解きいただけるので、とても充実した講習会となりました。
※写真はクリックすると拡大表示します。
 |
寺田勝彦先生から藍染めについての説明をいただく。 |
 |
藍染めの原料は、もちろん植物の藍(アイ)。
写真はアイの葉を醗酵させて作ったスクモを原料にした藍液。時間の都合上、先生が用意して下さいました。
藍液は空気に触れると青く変色し、青い泡の塊に変わっていきます。染色を繰り返していくと、染色成分が無くなり泡ができなくなると、いくら布を浸けても染まらなくなるそうです。
|
染めの方法により「無地染め」と「絞り染め」の2班に分かれて染色をしました。
「無地染め」のグループ

「無地染め」のグループが、1枚の布を水に浸けます。それは染色の基本だそうです。

無色の布を藍液に浸けます。
水に濡れた布はシッカリ絞っておきましょう。

布を藍液の入ったバケツにドボン!
5分間、空気に触れないよう藍液の中でヒタヒタし続けます。藍液はPHが11という強いアルカリ性なので、ゴム手袋は必須です。

藍液から引上げたらよく絞ります。
アイ染めの場合、媒染液は不要、媒染方法は布を空気中で5分間パタパタさせる空気酸化。
|
|
「絞り染め」のグループ

「絞り染め」のグループは布を輪ゴムや紐、お箸などで絞る。その絞り方は自由。色柄は出来上がってのお楽しみ。

「絞り染め」のグループは、「無地染め」のグループから遅れること5分遅れで、布の水洗い、5分間のアイ染め、5分間の空気酸化と、「無地染め」と「絞り染め」の班が交互に作業を繰り返すという染色の二輪唱。
|
 |
アイ染めの布は空気に触れたとたん緑色に変色。
これにはアレッ?と、何か変だと気付きます。
|
 |
空気酸化の後、布を水に浸けます。
すると、黄色や茶色といった余計な色が洗い流されて、綺麗な青色がクッキリ現れます。
これには一同感激してしまいました。
|
 |
「無地染め」のサンプリング。
色見本に3cm角くらいに切ってもらって、本日の講習会に配布してもらった用紙にペタッと貼り付けて、色見本にしました。残りは染めた人がお持ち帰り。
|
 |
左からアイ染めを1回、3回、5回と繰り返し、乾燥後の染め色の濃さの違いを比較。乾燥すると思ったより薄い染まり具合でした。
濃い藍色に染めるには30回以上染を繰り返さなければならない意味が納得できました。
|

各グループそれぞれ5回染色を繰り返し、最後に布を水で綺麗に洗ってできあがり。
その後、自分の作品を発表。
寺田先生に「絞り染め」の染め上がりを解説して頂きました。布は、染めた人がお持ち帰り。
 - 染め上がりを解説する寺田先生。
 最後に寺田先生の染色の解説と質疑応答があり、気が付けばアッという間に終了の時間。楽しい2時間でした。来年が待ち遠しい~。 最後に寺田先生の染色の解説と質疑応答があり、気が付けばアッという間に終了の時間。楽しい2時間でした。来年が待ち遠しい~。
広島市植物公園では、他にも楽しいイベントがいっぱい。お近くの方はどうぞ。
寺田勝彦先生の四季の色「草木染」のコーナーもどんどん充実させていきますよ。 当日これなくて、草木染に興味がある方は是非こちらをご覧下さい。 寺田勝彦先生の四季の色「草木染」
|