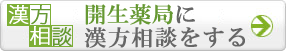きぐすり.com は、漢方薬、女性の健康、サプリメント、ハーブの情報を専門家がやさしく解説しています。
薬局・薬店の先生による健康サポート
食材が薬の材料にもなる
「医食同源」という言葉をよく耳にします。
漢方では薬と食材の間には明確な線引きをせず、普段利用している食材が薬の材料(生薬)として、使われる重要な薬にもなると理解できます。
頻用されるヤマイモ、生姜、シソ、ネギ、ナツメなどがそれに当たり漢方薬を構成する生薬としてもよく利用されています。
他にも食材には体を冷やす寒性・涼性のものと温める熱性・温性の食材があり、体が熱い場合には逆に体を冷やしてくれる寒性の食材を、冷えがある場合は体を温めてくれる熱性・温性の食材を摂るように心がけてバランスをとります。
この考えは中国四千年の歴史の中、世界最古の医学書「黄帝内経素問」陰陽説の教えによるもので、自然界は相反する2つの要素によって成り立ち、天が陽なら地は陰、日が陽で温かいなら月は陰で冷たい・・・・というように、人体でも熱い、温かいなら冷やしてバランスをとり、寒い、冷えるなら温めてバランスをとるという教えで、これを実践して行こうというものです。
他にも陰陽五行説を引用して、季節を春、夏、土用(梅雨)、秋、冬の五季に分け、五季には、その季節ごとに体のバランスをこわしやすい人体の臓があると考えます。春には肝、夏には心、梅雨時には脾(消化、吸収に関わる臓器)、秋には肺、冬には腎と言うように季節と五臓の関連があり、ここで出番となるのが、その季節のトラブルに対して体のバランスをとって改善し快方に導く人間の感じる味、五味なのです。
| 肝 | 心 | 脾 | 肺 | 腎 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 五季 | 春 | 夏 | 梅雨 | 秋 | 冬 |
| 五行 | 木 | 火 | 土 | 金 | 水 |
| 五味 | 酸 | 苦 | 甘 | 辛 | 鹹 |
季節に合った食材を

春にはイライラなど精神のたかぶりを鎮めて、肝臓の働きを助ける梅干しなど酸っぱい味の食材を。
夏には高血圧や動悸などに高ぶりを抑えるニガウリなどの冷やす性質の苦味の食材を。
梅雨時には外気の高温多湿に内臓も影響を受けて吐き気や下痢などの胃腸のトラブルが起きやすくなりますから、脾胃を元気にする、常食するお米など広い範囲の甘味の食材を。
秋には空気の乾燥で咳や皮膚粘膜の乾燥が心配です。呼吸器系を元気にする為にシソ、ネギ、生姜などの辛味(香辛料)を。
さぁ、冬本番です!
冬には、寒さ対策が必要です。
内臓の余分な水分を尿に排泄して、体を温め、むくみをとる天然の塩からい味をとります。
そこには重ねて陰陽説の教えを忘れないことです。
冷え症か温かい人か、体質を考えてバランスをとりましょう。
自分のことは、意外とわからないものです。
そんな時は、漢方薬局に相談を。
漢方の考え方を利用したバランスのとれた食生活をすることは、素晴らしいものです。
毎日の食生活に活用して健康に育んで頂きたいと願っています。
関連ページ
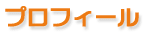
 開生薬局
開生薬局
手嶋 敏子先生-
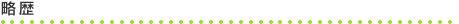
- 漢方薬・生薬認定薬剤師、活水女子大学非常勤講師、
NBC学園講師などの資格を持つ。 - 長崎学さるく・長崎の薬膳を担当するなど、薬膳料理を年数回開催
- 他 食養生に関する講演も行っている。
- 平成21年度薬事功労者厚生労働大臣表彰を受ける。
- 日本薬剤師会、長崎県薬剤師会、日本漢方交流会 会員。
- 漢方薬・生薬認定薬剤師、活水女子大学非常勤講師、

 ▲
▲