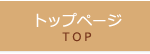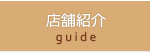私が漢方の世界に足を踏み入れた頃、今から約30年弱も前のことですが、当時も春に花粉症に悩む人はたくさんいました。
当時の花粉症の主症状はクシャミと大量の鼻水が中心だったように覚えています。
しかし東京から地元萩に帰って長全堂薬局を開局して以来感じるのは、花粉症の主症状がクシャミ鼻水から鼻づまりと眼の痒み、そして咳・咽通へと変わりつつあることです。
当然使用する漢方薬も変化します。クシャミ・鼻水の花粉症に対しては小青龍湯などの発表剤が中でした。ところが鼻づまりと眼の痒みに対しては基本的に花粉症症状の激しいときには清熱剤を中心に考え補陰剤を視野に入れながら漢方薬を組み立て、咳に対しては麻黄の配合されている鎮咳剤を清熱剤とのバランスを考えながら組み立てることになります。
小青龍湯もまだまだ使用しますが、その頻度はどんどん減ってきているのです。之に反比例して黄連解毒湯の使用頻度はまさに鰻上り。
この事態は東京と萩の地域差に原因があるのか、日本人の花粉症症状が変化してきているのか、それとも他に原因があるのか、よく判りません。
ただひとつはっきりしているのは花粉症という疾患も変化しているということ、これは間違いないと思います。私たちはこの変化に対応しなくてはなりません。漢方薬も医薬品、社会のニーズに敏感でなくてはならないのです。