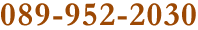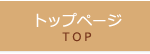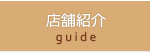先日の愛媛新聞にこんな記事が載っていました。
昔から歯のない人は認知症になりやすいと言われてきましたが、認知症になったから歯を失ったのか、歯を失ってから認知症になったのかよく分からないものでした。
そこで、神奈川歯科大が65歳以上の高齢者4425人を対象に4年間に渡る追跡調査を行いました。
20本以上歯がある人を基準にすると、歯がほとんどない人は1.85倍認知症になりやすく、歯はほとんどないが義歯を使っている人は1.09倍にすぎず、また、歯の手入れを心がけてない人は、心がけている人に比べ1.76倍認知症になりやすいという結果となりました。
歯を失う原因の9割は虫歯と歯周病。
しっかり予防して歯を残す努力をしましょう。
という内容のものでした。
まぁ、この調査だけでは何とも言えないですが、最近、虫歯より歯周病の人が増えていますよね。
もし、歯周病になってしまった場合、クマ笹エキスでうがいするか、クマ笹エキスを指か柔らかい歯ブラシにつけて血が出ない程度に歯肉をマッサージすると良いですよ。
クマ笹エキスに多く含まれている葉緑素の働きで炎症が治まり、脱臭作用で嫌な臭いを除いて、歯周病を徐々に改善していきます。
ただし、歯垢を除く作用はないため、毎食後、しっかり歯磨きをして歯垢を溜めないようにしましょう。
|
体が血圧を上げるのは、身を守るための反応のひとつで、血圧を上げて体の隅々まで血液が流れるように働いています。
このような体の反応に反して、血圧を下げようとするのはどうなんでしょうね? 血圧が上がる原因を追究しないで、血圧を下げる薬を飲み続け、強引に血圧を下げることは、筋肉や脳細胞に影響を及ぼし、 クラクラして歩けない 気力がわかない うつ状態 認知症 などに繋がる可能性があります。 よく血圧を下げる漢方はないか?と尋ねられることがありますが、 血圧を下げる漢方はありません。 漢方はその人の体質や症状によって使い分ける必要があり、その結果、その人にとって必要な血圧に落ち着きます。 だから、血圧が高い人に使う漢方を血圧が低い人に使うこともあります。 |
| ツイート |
|
更新日: 2015/11/18 |
|
「美スト」という雑誌の11月号(観月ありささんが表紙)の
49歳が絶賛する“私に優しい”必需品! の中でタチカワ電解カルシウムが掲載されました。 守り神の女性ホルモンがなくなって、いきなり骨粗鬆症なんてイヤ! ということで、特有の味があるがイオン化され吸収しやすいタチカワ電解カルシウムが レジェンド入りカルシウムに選ばれたようです。 骨がもろくなれば、骨折しやすくなります そして、骨折すれば寝たきりになる可能性もあります。 寝たきりになれば、認知症にもつながります。 そうならないためにもしっかりカルシウムを摂っておく必要があります。 タチカワ電解カルシウム 1本(約15日) 3800円(税別) 試飲できますので、まずは味をお確かめください。 |
| ツイート |
|
更新日: 2015/11/17 |
|
寒くなってきましたが、寒くなってくると血圧が高い人は少し注意が必要になります。
寒くなると体温を逃がさないように血管が収縮するため、血圧が上がりやすくなります。 高血圧は心筋梗塞や脳卒中を引き起こす要因ともなります。 漢方では血圧を下げるというのではなく、全身の調和を整えることを目標とし、その結果、血圧が正常になるとお考えください。 黄連解毒湯 のぼせて赤ら顔、鼻血、眼底出血、イライラして落ち着かない、不眠、頭痛、めまい、耳鳴り、動悸など 婦人の更年期障害に伴う高血圧に多い 後頭部から首筋にかけて凝りやすく、目が充血するものに 三黄瀉心湯 黄連解毒湯に似ていて、便秘する すぐカッとなって怒ったかと思えば、すぐ冷めてしまい、気が移りやすい感情的 九味檳榔湯 下半身がだるく、浮腫む、水太りで、動悸、首や腰に硬直感がある、便秘、こむら返りが起こりやすい 起床時、顔やまぶたが浮腫む、夕方、足が浮腫む インスタント食品やスナック菓子などをよく食べる 高血圧に用いる場合、顔色や皮膚が青白いか瑞々しく見受けられるものを対象にし、降圧の目的でなく、疲労が重なって自覚症状が増悪するものに用います。 桂枝加竜骨牡蠣湯 下腹部に力なく、体は疲れているのに神経だけが高ぶり、ストレスで血圧が上がりやすく、下の血圧が下がりにくい、血圧は少し高いか不安定 腹部の動悸、のぼせ、夢が多く、不眠など 柴胡加竜骨牡蠣湯 みぞおちの辺りが硬く、腹部の動悸、のぼせ、興奮しやすく、驚きやすく、夢が多く、不眠、便秘、小便が少ないなど ストレスで血圧が上がりやすい 七物降下湯 最低血圧が高く、眼底出血を繰り返し、手足の痺れ、疲れやすい、頭痛、鼻血、めまい、耳鳴りなど 真武湯 動悸、雲の上を歩いているかのようなふわふわ感がある、小便少なく、下痢、寒がり、頭が重い感じがするなど 大柴胡湯 みぞおちから脇腹にかけて圧迫感があり、便秘、肩こり、頭が重い、気分が重い、せっかちで肝積持ち 怒りは容易には現さないけど、一度怒れば怒髪天を衝くような意志的な力が強く、感情を抑制するような人 釣藤散 朝方の頭痛が多く、動いているといつの間にか頭痛のことを忘れているのが特徴 側頭部から後頭部にかけての頭痛が多いけど、首筋から頭に衝き上げるような頭痛のこともあります めまい、耳鳴り、のぼせ、気分が沈みがちで物忘れをするなど 下の血圧が高いものによく効きます 桃核承気湯 のぼせる感じはあっても顔は火照らない、足冷え、便秘、便は紫黒色便が多い 生理不順 臍の左下辺りにしこりや圧痛がある 頭痛など 当帰芍薬散 色白で華奢、肌の表面がしっとりして、声は優しく耳当たりが心地よく、しぐさがおっとりしている、ちょっと手を差しのべてあげたくなる日本美人の高血圧に。 美人には当帰芍薬散なら、私は全ての女性に当帰芍薬散を出したくなってしまいます。 貧血、手足の冷え、顔や足の浮腫み 生理不順、お腹の冷え、下腹部痛、頭痛、肩こり、眩暈、動悸などを伴う高血圧に。 女神散 顔は赤く火照り、めまい、立ちくらみ、頭痛、動悸、足が冷える、生理不順、便秘、生理前後に精神症状が強く出てくる 八味丸 夜間頻尿、昼間の尿の回数は多くても量は少ない 手足冷え、足の裏の火照り、口が渇く、下半身がだるいなど 半夏白朮天麻湯 曇りや雨など湿気が多いときに頭痛、頭が重い感じがする、めまい、耳鳴りが起こる 頭痛は額から脳天にかけて甚だしいものが多い 胃腸虚弱、胃内停水、食欲不振、動悸、息切れ、足の冷えなど 防風通聖散 肥満で便秘、腹部膨満感、頭痛、めまい、赤ら顔など 苓桂朮甘湯 立ちくらみ、貧血、耳鳴り、動悸、息切れ、のぼせ、胃内停水、横になると軽減する頭痛など 簡単に書きましたが、漢方はその人の症状に合わせて用いるので、当然、他にもあります。 ご相談ください。 |
| ツイート |
|
更新日: 2015/11/16 |
|
雨が降ってるせいか、今日は非常に寒いです。
寒いと体温が下がって風邪をひきやすくなります。 暖かい格好、しょうが湯など温かい物を飲むなどして体温を下げないよう、気をつけましょう。 さて、いつだったか忘れましたが、風邪に用いる漢方薬を少し書きましたが、もちろん他のもあります。 今回はそれらを紹介したいと思います。 葛根湯 悪寒、発熱、頭痛、汗が出てない状態で首筋から肩にかけての凝りを伴う 葛根湯合香蘇散 葛根湯では胃に障る人に 麻黄湯 悪寒、発熱、頭痛、汗が出てない状態で節々の痛みを伴う 葛根湯と使い方は似ていますが、葛根湯は上半身に症状が現れ、麻黄湯は全身に症状が現れます インフルエンザによく用いられます 桂枝湯 軽い悪寒、発熱、頭痛、自然発汗がある 桂麻各半湯 喉の痛みから始まる風邪。悪寒よりも熱感が強い。自然発汗、咳が出る 1日に2~3回発熱がある 初期だけでなく長引く風邪にも用いられます 小青竜湯 透明な鼻水、くしゃみが多く、薄い痰を伴う咳 悪寒発熱はあってもなくてもいい 苓甘姜味辛夏仁湯 小青竜湯では胃に障る人に 麻黄附子細辛湯 悪寒と言うよりも寒くて仕方がない(特に頭が冷える)、熱はあってもあまり熱感を感じない、頭痛、喉がチクチク痛い 老人や虚弱者に多い 麻黄附子細辛湯合桂枝湯 麻黄附子細辛湯では胃に障る人に 参蘇飲 胃腸虚弱な人の風邪で、桂枝湯や葛根湯では胃に障るという人に。子供や老人、虚弱者、妊婦の風邪に。 急性期を過ぎ、軽い微熱や喉の痛み、咳のみが残る場合に。 香蘇散 胃腸虚弱な人の風邪で、桂枝湯や葛根湯では胃に障るという人に。 軽い寒気やだるさなど軽い症状に。 小柴胡湯 風邪を引いてから4~7日ほど経過したもので、黄色や黄緑色をした粘っこい鼻水、口が苦い、口が粘る、食欲不振、吐き気がする 午前中発熱し、午後悪寒がする、もしくは午前中悪寒がし、午後発熱する 柴胡桂枝湯 発熱、軽い悪寒がして頭痛、自然発汗があり、軽い吐き気、口が苦い、口が粘る、食欲不振などを伴う こじれた風邪に使うと一般的に言われてますが、1週間以上長引いた場合に用いてもあまり効かないことが多い 柴胡桂枝乾姜湯 微熱、喉の乾燥感があって咳が出る、背中に悪寒を強く感じる、体がだるくてすぐ横になりたがる、頭に汗をかきやすく、盗汗もある、食欲不振 小柴胡湯合香蘇散 熱は下がっても気分がさっぱりせず、頭が重い感じがする 麦門冬湯 熱は下がったが、咳が残る人に。昼間の咳が酷く、顔を真っ赤にして咳き込み、最後にはオエーと吐きそうになる 喉の乾燥感があり、喉を湿らす程度の水を飲みたがる、粘っこい痰で切れにくい 麻杏甘石湯 熱は下がったが、咳が残る人に。顔を真っ赤にして汗をかくほど咳き込む 口が渇いて水を飲みたがる 小柴胡湯合葛根湯合桔梗石膏 39℃、40℃前後の高熱があって頭痛、身体の痛み、汗が出てない状態という麻黄湯を用いる場合に似ていますが、それに加えて口が渇く、食欲不振、吐き気を伴う インフルエンザにも用いられます 以上、簡単に書きましたが、これら以外にも風邪に使う処方はまだまだあります。 風邪を引いてお困りの際はご相談ください。 そんなことにならないよう、板藍根を飲んで予防しましょう。 |
| ツイート |
|
更新日: 2015/11/13 |