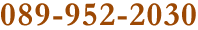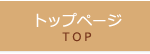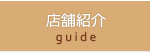今朝、テレビを見ているとヒートショックの話がされていました。
ヒートショックは、温度が急激に変化することで、血圧が急激に上下し、心臓や血管に負担がかかり、負担が大きいと身体が対応できず、脳卒中や心筋梗塞など重大な事故に繋がります。
血管が硬くてもろくなったお年寄りに多くみられてましたが、どうやら若者にもその傾向があるようです。
冷えた脱衣所では血管が収縮して血圧が急上昇してしまいますが、42℃以上の熱いお風呂に入ると、血管が拡張して血圧が急降下しやすくなり、また長く湯船に浸かることで脱水状態を引き起こすことに繋がります。
ヒートショックを防ぐためには、暖かい部屋と脱衣所の温度差は5℃以内にして、お風呂の温度は41℃以下で浸かる時間も10分以内にするのが良いようです。
またいきなり湯船に浸かるのは、急激な血圧の変化を招くので、心臓から遠い足先から徐々にかけ湯をすることが心臓への負担を防ぐことができます。
私は熱々のお風呂が好きなのですが、湯船に浸かるのは全部洗ってからなので、ある程度は防げているのかもしれません。
みなさんもお気を付けください。
| ツイート |
|
更新日: 2019/11/16 |
|
寒い冬は風邪・インフルエンザ、ノロウイルスというウイルス感染に注意が必要です。
罹ってから買いに走るのも良いですけど、しんどい状態で行くのも大変ですよね。 身近に誰かいれば代わりに買いに行ってくれますが、一人だとそうもいかない・・・ そういうときのために常備しておくと良いですよ。 葛根湯 風邪といえば、葛根湯で有名ですが、全ての風邪に対応するわけではありません。 風の初期症状で、悪寒、発熱、無汗であることが必要です。 とは言っても、葛根湯は発汗させながらも発汗しすぎるのを防ぐという、守りながら攻める処方でもあるので、余程の虚弱体質でない限り、使えます。 頭痛は後頭部痛のことが多いです。 肩こりがある場合にも使えます。 麻黄湯 インフルエンザに有効であると数年前から名が有名になりました。 葛根湯と同じく、悪寒、発熱、無汗という条件のもと使います。 ただ、葛根湯と違うのは、麻黄湯は完全な攻めの処方であるため、汗が出ている状態では使えません。 麻黄湯も後頭部痛のことが多いです。 肩こりにも使えますが、どちらかというと麻黄湯は全身の節々が痛むことが多く、葛根湯は上半身に限られる点も違いがあります。 小青竜湯 鼻水タラタラ、咳、喉が痛む場合に。 柴胡桂枝湯 少しこじらせた時期で、食欲がない、だるいなどの症状が出てきた場合に。 頭痛は側頭部痛のことが多いです。 藿香正気散 ノロウイルスなどの感染性胃腸炎による嘔吐、下痢に。 感染性胃腸炎には五苓散や半夏瀉心湯なども使われます。 違いはと言うと、五苓散や半夏瀉心湯は吐いたり下したりするのがスッキリと出ますが、藿香正気散はスッキリしない感じがする場合に使います。 五苓散や藿香正気散は発熱があっても使いますが、半夏瀉心湯は発熱がない場合に使います。 これらに板藍根を併用すると良いです。 手洗い、うがい、板藍根の徹底をし、罹ったら上記の処方を使い分け、尚且つ板藍根を併用すると良いと思います。 ご相談ください。 |
| ツイート |
|
更新日: 2019/11/15 |
|
12月くらいからでしょうかね?
しもやけが出来てくるのは? しもやけって厄介なんですよね。 寒さが原因で血行不良となってしもやけができるのに、逆に温めてあげると痒みが増してきたりして・・・ これは冷えて血管が収縮して血行が悪くなって炎症を起こしているところに、温められることによって血管が拡張して、炎症を起こしているところに流れ込んできて、それが刺激となって痒く感じてきます。 しもやけの予防は冷やさないことですね。 しもやけの漢方薬として一番有名なのは、当帰四逆加呉茱萸生姜湯です。 末端の血流を良くして温める力が強いんですけど、これ不味いんですよね。 あの不味さは呉茱萸でしょうね。 私はこの漢方薬は飲んだことないですけど、呉茱萸の匂いを嗅いだだけでも不味いだろうと予想がつきます。 しもやけに当帰四逆加呉茱萸生姜湯は有名ですが、全てのしもやけに対応するわけではありません。 比較的軽い炎症状態には向いてますが、炎症が強く、腫れて膨らんでいる状態には不向きです。 この場合には桂枝茯苓丸や桃核承気湯が良かったりします。 しもやけができやすい人は今からでも漢方で対策を! ご相談ください。 |
| ツイート |
|
更新日: 2019/11/01 |