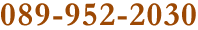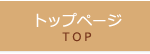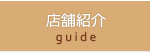1月7日は七草の日です。
7日の朝に七種類の野菜の入った粥を食べるのが昔からの風習です。
七草粥を食べることで、邪気を払い万病を除くという意味だけでなく、正月のご馳走で疲れた胃腸をいたわり、青菜の不足しがちな冬の栄養を補給するという意味もあります。
せりは競り勝つ
なずなは撫でて汚れを除く
ごぎょうは仏の体
はこべらは繁栄がはびこる
ほとけのざは仏の安座
すずなは神を呼ぶ鈴
すずしろは汚れのない清白
という意味らしいです。
これら七草を前日の夜に囃し歌を歌いながら叩き、当日の朝に粥に入れて食べます。
七草粥は食べたことありますが、こうやって食べるのは知らず、恥ずかしい話、私は夜食べてました。
勉強になります。
[ カテゴリー » Topics ]
|
1月6日はケーキの日って知ってましたか?
明治12年の1月6日、東京の上野の風月堂が日本で初めてケーキを宣伝したことに由来するそうです。 もっと別の意味があるかと思ったら、それだけのようです。 ケーキ···クリスマス以来食べてないですね。 甘い物が好きなので、めっちゃ食べたいです。 でも甘い物はカルシウムをどんどん消費させてしまうので、注意が必要です。 聞いた話だと、角砂糖1個で牛乳7本分のカルシウムが失われるらしいです。 ショートケーキだと角砂糖8個も使われるので、牛乳56本分のカルシウムが失われることになりますね。 恐ろしや。 甘い物を食べたときは、しっかりカルシウムを摂りましょう。 吸収に良いカルシウムあります。 試飲もできますので、まずは飲んでみてください。 |
| ツイート |
|
更新日: 2018/01/06 |
|
新年あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。 正月はどのように過ごされましたか? 私のようにだらだら過ごされた方もいることでしょう。 で、体重計にのってみたら2~3kg増えてびっくり! なんてことになってないですか? 忘年会や新年会、おせち料理におもち料理と、普段よりも食事の量が増えて暴飲暴食ぎみ・・・ それに加えて、のんびり過ごしたことで運動不足・・・ これで太らないわけがない! お腹ぶよぶよ 便秘する 体が重い 顔や足がむくむ なんて方はいませんか? 正月太りは水毒が原因と言われています。 脂肪というものは徐々に増えていくもので、短期間で増えた体重は、多くは水分によるもの! まだ本物の脂肪にはなっていません。 余分な水分を排出してあげることで、正月太りは解消されます。 正月休みから普段の生活に戻っても、元に戻らないという方は、代謝が上手くできていないのです。 そういう方には漢方薬の出番なのではないでしょうか? ご相談ください。 |
| ツイート |
|
更新日: 2018/01/05 |
|
今日は冬至です。
1年で最も日が短い日となります。 冬至といえば、かぼちゃにゆず湯ですね。 風邪予防のためとも言われていますが、本当の理由は? 冬至は、1年で最も太陽の力が弱まる日ですが、それ以後は再び太陽の力が強くなることから、一陽来復と言って、この日を境に運が上向くとされ、冬至に「ん」のつく食べ物を食べると「運」がつくと言われています。 にんじん、れんこん、だいこん、うどんなど「ん」のつくものを運盛りといい、縁起をかついでいました。 かぼちゃは「ん」がつかないじゃないか? そんなことはありません。 漢字で書くと南瓜で「なんきん」・・・ちゃんと「ん」がついてますね。 かぼちゃは夏が旬の野菜で、元は南方から渡ってきた野菜であることから、夏や南は陽の気を持つものとして、1年で陰(最も太陽の力が弱い日)に陽を多く含む食べ物を食べるという意味もあります。 ゆずは融通が利く、冬至は湯治という語呂合わせから、冬至にゆず湯に入ると思われていますが、もともとは運を呼び込む前の厄払いするための禊だと考えられています。 ゆずの強い香りが邪気を払うという意味ですね。 また、ゆずが実るまでに長い年月をかけていることから、長年の苦労が実るようにと願いも込められています。 ゆず湯は、血行を良くして冷え性を緩和したり、体が温まることで風邪予防となったり、香りによるリラックス効果となったりと、元気で冬を越すために役立ちます。 ゆずを丸ごと使う場合は、1~2個では香りはあまり感じないので、たくさん入れましょう。 輪切りや半分にカットすると香りも成分も出やすいです。この場合はネットに入れてお風呂に入れた方が良さそうです。 ただし、肌が弱い人はお気を付けください。 今日はかぼちゃを食べ、ゆず湯に入って運を味方につけましょう。 |
| ツイート |
|
更新日: 2017/12/22 |