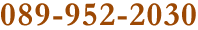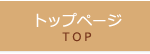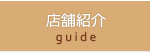今朝も寒いです
冬はこたつでみかんというのが定番ですね。
でもね
みかんって体を冷やす食べ物なんですよね
寒くてこたつに入って暖まってるのに
みかんを食べて体を冷やそうとするのって何か変ですよね
みかんはビタミンCが豊富だから風邪予防になるとか言われてますけど、
体温を下げて風邪予防になる?
食べ過ぎなければそこまで冷やすことはないので問題はないかも?
ただ、みかんが風邪予防というよりビタミンCが風邪予防というのが正解かな?
ビタミンCが入ってたら何でも風邪予防になると思うのではなく、温めるものか、冷やすものかとあうのも考慮したほうが良いのではないかと私は思います。
実は日本に持ち込まれた頃のみかんって温性のものだったのって知ってました?
それを改良して、酸味を減らして甘味を増したために属性が変わったんですよね
甘味は閉じ込める作用があるので
食べ過ぎるとと体の中に余分な水分が溜まり、元々神経痛持ってる人は疼きやすくなるのでご注意を。
うちの母がそうです。
みかん食べたら夜必ず疼きます。
まあ、どんなに良いものでも食べ過ぎたら毒となるので、ほどほどにしておいたほうが良いと思います。
[ カテゴリー » Topics ]
|
昨日からめっちゃ寒くなってきましたね。
体温が1度下がると免疫力は30%下がると言われています。 逆に体温が1度上がると免疫力は5~6倍上がると言われています。 冬に元気で過ごすためには、いかに体温を下げないかが重要になってきます。 ファッション重視より暖かい格好をされることをお勧めしますね。 風邪の邪気は風門と呼ばれるところから侵入すると言われています。 ですから風門にカイロを当てて温めてあげることで、ある程度予防になります。 風門の位置は、首を前に曲げると骨が飛び出ていると思いますが、そこから指2本分下の、そこから左右に指2本分離れたところにあります。 位置は個人差によるため、大きめのカイロを貼ると間違いはないと思います。 風邪を引いたときもこの風門を温めてあげると治りが早くなります。 風邪を引いてから対処するのではなく、風邪を引かないよう早めの対処をお勧めします。 特に年をとると治りが遅いです。 私も昔に比べると長引きますわ。 ですから、風邪を引かないよう、板藍根でうがいをするなどの対策はするようになりました。 体を冷やさないよう、暖かくして冬は過ごしましょう。 |
| ツイート |
|
更新日: 2017/11/18 |
|
味には5つの味があります。
酸っぱい味 苦い味 甘い味 辛い味 塩辛い味 実はこの五つの味は五臓と関係しています。 塩辛い味は腎と関係があります。 腎は生長・発育・生殖を主り、生命エネルギーを蓄えている場所です。 尿の排泄にも関係があります。 腎の衰えは冷えやすくします。 塩辛い味は腎・膀胱の機能を補い、体内の水分代謝を調整する働きがあります。 また、塩辛い味は体を温める作用があります。 血液中の塩分濃度が高まると、エネルギーの燃焼が盛んになり、体温が上昇します。 北海道などの寒さの厳しい地方では、味噌や醤油の塩分濃度が高く、塩をふんだんに使った郷土料理がたくさんあるのも理由のひとつではないでしょうか。 減塩、減塩と言われていますが、天然の塩ではなく、塩化ナトリウムを食塩として摂ってることに問題があります。 天然の塩には塩辛い味だけでなく、苦味も含まれています。 苦味は心臓を守る作用があります。 つまり、塩辛い味と苦い味がある天然の塩は、塩辛い味だけでできた塩化ナトリウムの塩に比べると血圧を上げにくいのです。 とは言っても、摂り過ぎには気をつけましょう。 |
| ツイート |
|
更新日: 2017/11/14 |
|
味には5つの味があります。
酸っぱい味 苦い味 甘い味 辛い味 塩辛い味 実はこの五つの味は五臓と関係しています。 辛い味は肺と関係があります。 肺は気や水を全身に巡らせる働きがあり、また悪い邪気が体内に侵入しないよう防ぐ働きもあります。 辛い味は多分、一番分かりやすいと思いますが、体を温めて巡りを良くし、悪い邪気を追い払う力があります。 昔の人は風邪を引いたらネギを首に巻くということをやってましたが、そういうことなんですね、多分。 |
| ツイート |
|
更新日: 2017/11/11 |
|
味には5つの味があります。
酸っぱい味 苦い味 甘い味 辛い味 塩辛い味 実はこの五つの味は五臓と関係しています。 甘い味は脾と関係があります。 脾と言っても脾臓のことではなく、胃腸といったところでしょうか。 脾は簡単に言えばエネルギーを作り出すところです。 疲れると甘い物が欲しくなるのはそういうことです。 そういえば、ストレスがたまると甘い物も欲しくなりますよね? ちゃんと理由があります。 ストレスを最も受けやすいのは肝。 肝は木に属し、脾は土に属します。 木は土の養分を吸い取って育ちますよね? ストレスで肝が影響を受けるということは、木が弱るということ。 木は土の養分を吸い取って保とうとします。 当然、土の養分は少なくなります。 そうすると土台がもろくなり、木もしっかり立っていることができなくなり、両方とも共倒れになります。 そうならないようにするためにも土台をしっかり保持するためには養分を与えてあげないといけないわけです。 つまりストレスによって崩されかけた土台を甘い物で補強しているんです。 分かりにくい例えですみません。 |
| ツイート |
|
更新日: 2017/11/10 |