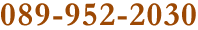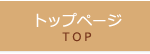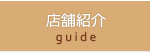当帰は、女性の健康と美容に欠かせない生薬で、貧血や冷え性、生理不順や不妊、更年期障害など、女性に特有の症状によく用いられています。
当帰の語源はいろいろありますが、私がよく話すのは
ある若い夫婦がいました。
奥さんはめちゃめちゃ美人だったんだけど、あるとき病気に罹り、どんどんやつれていって美貌が失われていきました。
すると旦那さんはどうしたと思います?
家に帰らなくなったんですよ。
奥さんが弱っているのに、酷いですね。
最低のクソ野郎です。
さぞかし奥さんも悔しかったでしょうね。
奥さん頑張りましたよ。
自力で薬草を採りに行って煎じて飲みました。
するとみるみる内に体調が良くなり、以前のような美しさを取り戻しました。
その噂を聞きつけた旦那さんは家に帰ってきたんだとさ。
その薬草のおかげで旦那さんが当に帰ってきたので、その薬草は当帰と名づけられました。
これ以外に美しい話もあるんですけど、何故かこればっかり話してしまいますわ。
生理・妊娠・出産・授乳といった大切な機能を持つ女性の体は、男性に比べて多くの血液を必要とします。
女性の健康は血液と深い関わりがあります。
貧血や冷え性、生理不順、生理痛、更年期障害など、多くの女性の悩みとなっている諸症状も血液不足や血行不良が原因になっています。
血液は肌や髪などにも栄養を送って潤してますが、血液不足や血行不良は、潤いのある肌や髪といった女性の美容にも大きな影響を与えます。
当帰が昔から「女性の宝・美容の女王」と呼ばれているのは、不足しがちな血液を補う作用と、体を温め、血液の流れを活発にする作用に優れているからです。
[ カテゴリー » Topics ]
|
みなさんは楊貴妃という女性をご存知ですか?
中国の唐の玄宗皇帝に寵愛され、寵愛され過ぎたために国が乱れ、反乱にまで発展させてしまった傾国の美女であり、中国4大美女の一人に挙げられています。 彼女が元凶だとして処刑されましたが、彼女の虜となり、何でも叶えようとアホなことをしていた玄宗皇帝にすべての原因があると私は思うんですけどね。 そういえば、ファン・ビンビンがドラマに映画にと楊貴妃を演じてましたが、本来の楊貴妃はぽっちゃり体型なんですよね。 昔の中国では、細い女性は不健康とみなされ、ぽっちゃりした女性の方が健康的で愛されてたんですよ、確か。 でも今は細い女性が美女扱いされてますから、ファン・ビンビンみたいな女優さんが演じないと見てもらえないかもしれないしね。 さて、中国4大美女の一人である楊貴妃が愛したお酒があるんですが、それが 楊貴美酒! 温める生薬と冷やす生薬が半々に配合されており、その絶妙な組み合わせで 血液の循環を良くして身体を温め、生理の苦痛を和らげ、血を増して血色を良くし、心を穏やかにします。 生理不順や血行不良、貧血、美容、保健強壮などに効果があると言われています。 作り方は 当帰15g 芍薬8g 牡丹皮7g 茯苓8g 竜眼肉15g 香附子7g 紅花10g 山梔子5g 薄荷5g 柴胡5g 菊花5g 大棗10g ①上記の生薬とホワイトリカー1リットルを容器に入れ、フタをして軽く振り、生薬をなじませます ②日の当たらない涼しい場所に保管し、最初の4~5日は1日1回液を軽くゆすり、浸出を促します ③10日後にフタを開け、グラニュー糖150g、はちみつ80gを入れてよく溶かし、1ヶ月ほどねかせます ④1ヶ月後、濾して別の容器に移します 飲み方 1回20mℓ、1日2~3回食前あるいは寝る前に 薬酒は少量ずつ、毎日飲むのが基本です 美容と健康に興味のある方はぜひお試しください。 |
| ツイート |
|
更新日: 2017/06/13 |
|
杏仁豆腐でおなじみのクコの実
クコの実には、滋養強壮作用や視力回復、肝臓や腎臓の機能を丈夫にする作用がありますが、その他に 紫外線から肌を守る効果があるとして注目を集めています。 紫外線やストレスなどによって活性酸素が体内に発生させますが、この活性酸素は老化を引き起こす原因となります。 クコの実はその活性酸素の発生を抑えてくれます。 クコの実を事前に摂取し続けることで、そもそもシミを作らない体質に導くことができます。 クコの実をそのまま食べてもいいのですが はちみつとクコの実の美人茶というのもお勧めです。 作り方は簡単 クコの実 大さじ2 はちみつ 大さじ2 熱湯 2カップ ティーカップにクコの実とはちみつを入れ、熱湯を注いで2~3分ほど蒸らして完成 分量は好みで変えても良いです。 私は適当に入れて、パンダグラスで頂きました。  ワインにクコの実を入れて飲むのも良いかも♪ これからの紫外線対策にクコの実を取り入れるのもアリかもしれませんよ |
| ツイート |
|
更新日: 2017/06/10 |
|
6月8日、BSプレミアムで「美と若さの新常識」という番組で漢方が取り上げられていました。
栃木県の女性は日常的にハトムギを摂取しているため、非常に肌が綺麗なんだそうです。 小山市はハトムギの産地であり、はとむぎ味噌やハトムギ納豆、ハトムギジェラートまであるそうです。 ハトムギには、アデノシン、パラクマル酸ナトリウム、フェニルアラニン、グアノシンの4つの美肌成分が含まれており、これらが繊維芽細胞の増殖を促してくれます。 老化によって肌のコラーゲンが減ると、シワになります。 そこにコラーゲンを作る繊維芽細胞が増えることで肌は弾力を取り戻します。 古い細胞が残らないで、次々と新しい細胞が生まれてくると、しっとり感が出、シミ・シワの改善になり、美肌・美白に効果が現れます。 1日16gのハトムギを摂取して2ヶ月後にはシミが薄くなったと番組内で紹介されていました。 まぁ、人によって効果の程は違いますが・・・ ハトムギはお茶として、またお米と一緒に炊いて食べれるなど、手軽にできるものなので、お肌が気になる方はぜひお試しください。 |
| ツイート |
|
更新日: 2017/06/09 |
|
6月に入り、ジメジメした嫌な梅雨の時期に入りましたね。
このジメジメした梅雨の時期は、身体がだるい、頭が痛いなど体に不調が起きる時期でもありますが、食中毒菌の繁殖が活発になる時期でもあります。 特に火の通っていない生ものは非常に危険です。 食中毒は大きく下記の3つに分けられます ・カンピロバクターや黄色ブドウ球菌、サルモネラなどの食中毒菌が食品に混入したことによって起こる細菌性食中毒 ・ノロウイルスなどのウイルスが蓄積している食品を飲食したり、人の手を介したりすることで起こるウイルス性食中毒 ・フグや毒キノコなど、動物性・植物性の毒によって起こる自然毒食中毒 ノロウイルスなどのウイルス性食中毒は冬に増えるのに対し、6月頃から増え始めてくるのが細菌性食中毒です。 細菌にとって梅雨は、水分が豊富で、気温が高く、活動には絶好のチャンス! さらに調理器具についた食品汚れがあれば、それを栄養に増殖しまくります。 6月以降に増える食中毒で多いのは、カンピロバクター、黄色ブドウ球菌、ウェルシュ菌です。 カンピロバクターの主な原因食品は、生あるいは加熱不十分な鶏肉や牛生レバーなど、あるいは二次汚染された食品。 潜伏期間は2~3日で、主な症状は下痢(水様便)、腹痛、発熱(37.5~39.5℃)で、頭痛、悪寒、筋肉痛、倦怠感などが現れることもあり、2~3日ほどで回復します。 生食や加熱不十分なものを食べることは控えるべきです。 また熱や乾燥に弱いため、調理器具は使用後はしっかり洗浄し、熱湯消毒して乾燥させることが重要です。 また食肉からサラダなどへの二次感染を防ぐために生肉を扱う調理器具と調理後の料理を扱う器具は区別する、生肉を扱ったあとは手指を十分に洗浄することも重要です。 冷蔵庫内で生肉と他の食品との接触を避けることも重要です。 黄色ブドウ球菌の主な原因食品は、おにぎりや弁当、サンドウィッチ、ケーキなどで、食べた後、唾液の分泌が増加し、次いで激しい吐き気、嘔吐、腹痛などの症状が現れます。 潜伏期間は約3時間ほどと短いのが特徴で、症状のほとんどが24時間以内に回復します。 菌自体は熱に弱く、通常の加熱処理で死滅しますが、毒素は熱や乾燥に強く、食品中に毒素が産生されてしまうと、その後、加熱処理をしても毒素は不活化されず、食中毒の原因となります。 予防としては、食品を扱うときは手指をよく消毒し、手指に化膿性疾患があれば食品を扱わないことが大切です。 食品を10℃以下に保つことで、菌の増殖を抑えることも重要です。 ウェルシュ菌の主な原因食品は、肉類や魚介類、野菜を使った煮込み料理に多く、潜伏期間は6~18時間、腹痛、下痢が主で特に下腹部が張ることが多く、症状としては軽いです。 ウェルシュ菌は熱に強いため、カレーやスープなど作り置きに便利な食品で増殖しやすいですので、調理済み食品を何日も常温で放置しないで、冷蔵庫に保存し、食べる前に加熱するのも重要です。 食中毒を予防するためには ・食品は低温で保存 ・しっかり加熱する ・包丁、まな板、ふきんなどは、熱湯や漂白剤で殺菌する ・食べ物と調理器具、容器は使い分ける ・調理後は早く食べる、または冷蔵庫で保存する あとは板藍根をお茶代わりに毎日飲んでおくのも良いかもしれません。 もし、食中毒になったら、藿香正気散と板藍根を一緒に飲んでみてください。 良く効きますよ。 |
| ツイート |
|
更新日: 2017/06/07 |