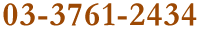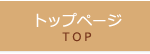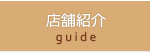肝は腎の支えによって効力が保たれています。
腎は基本的には老化によって衰えます。
いつも我慢強く仕事をされている、
周りに気遣いがあり
前向きで向上心が高い、このような状態は、
長い時間をかけて少しずつ
肝の力を使っていることになります。
そのような方は、肝を酷使したことで
余計に腎が弱まり、
また加齢とともにさらに腎が弱まり、
耳鳴りが起きることがあります。
この場合はジージーと
セミが鳴くような耳鳴りを訴えます。
多くの方は昼間、音がしているところでは
あまり気にならないのですが、
夜静かになるとジージーと低い音が気になるのです。
その結果、不眠になったりイライラしたりします。
また、その不眠・イライラが気になり、
さらに耳鳴りがひどくなることがあります。
これは、自律神経のうちの
交感神経が過剰緊張気味の状態であり、
漢方では、肝の失調と考えます。
耳鳴りを改善する漢方薬は、
補神薬を主とするか、疎肝理気薬を主とするか、
あるいは気を発散させる理気薬を主とするか、
さらには降気薬を加えるかは、
人に依ってみな違います。
それが、個人にあわせて漢方処方をする理由です。
では、具体的にどのような漢方薬を使うのか?
[ カテゴリー » Topics ]
|
前回の耳のお話の続きです。
蝸牛の中は、 リンパ管により3つの部屋に分かれています。 外側には外リンパ液があり、 中には内リンパ液があります。 蝸牛の中には、 小さな外有毛細胞・内有毛細胞があります。 その外有毛細胞を触る 天女の羽衣のようなものがあり、 それをテクトリアルメンブレンと申します。 音を聴くというのは、 蝸牛と中耳の間をくっつけている あぶみ骨・つち骨・きぬた骨が動いて、 その蝸牛の有毛細胞をゆらす仕組みから なっています。 耳鳴りは、そのわかりにくい場所が 老化したためと考えられます。 耳鳴りを訴える方の多くは、 原因不明のことが多いです。 おおむね50歳以下の若い人で、 キーンという高い耳鳴りと同時に 耳の塞がりを訴える方がいます。 私共の経験では、このような方の多くは ストレスが原因であることが多く、 首筋・肩こりも訴えます。 漢方ではストレスは 肝の失調を生むと考えています。 肝の経絡は胸上方から肩、首筋、 耳の周りを通り、目に入ります。 したがって、 疎肝して気の巡りをよくして対応します。 次回は、肝と腎の関係によって起こる 耳鳴りについてお話いたします。 |
| ツイート |
|
更新日: 2020/05/27 |
|
耳は外耳・中耳・内耳から構成されています。
よく、耳の穴を自分で耳かきしすぎて、その結果 外耳炎になる方がいます。 これは、耳鼻科に行くと抗生物質もしくは 軟膏ですぐに治ると存じます。 また、プールに入って中耳にばい菌が入り 中耳炎になる方も見られます。 こちらも抗生物質と点耳薬ですぐに治ります。 それはほとんどの場合、細菌感染が原因でなります。 このとき、治りにくい方と治りやすい方がいます。 これは、その人の治す力・免疫力が問題となります。 この問題は、 コロナウイルスに感染しにくいか・しやすいか、 治りやすいか・治りにくいか ということとも重なることです。 あくまでも一般論ですが、 外耳炎・中耳炎が治りにくく慢性化しやすい方は、 免疫力が弱いといわれています。 このような方は、脾が弱く疲れやすい、 気血不足であることが多いです。 この場合、 気を補い胃腸を丈夫にする漢方薬を使います。 また、体質的に化膿しやすい方もいます。 こちらは漢方では解毒湯タイプと考え、 清熱解毒薬で対応します。 このように、同じ外耳炎・中耳炎においても、 どのような処方が必要かは人によって異なります。 そのため、おひとりおひとり、詳しく体質・症状を お伺いして漢方薬をお選びしています。 |
| ツイート |
|
更新日: 2020/05/26 |
|
コロナウイルス感染拡大の関係で、
当薬局も時短で対応させて頂きます。 この時期、自宅で待機されている方も 多くいらっしゃるかと存じます。 自宅にて運動、ストレッチなどテレビでも 話題になっております。 また、ストレスが溜まって、様々な方法で ストレスを解消されている方も多くみられます。 ストレスがあると漢方では、 肝の失調がおき易くなると考えます。 肝が失調しますと、肩こり、首筋のこり また、心に及んで、不安感を 起こし易くなる事もあります。 また、それが高じて免疫能力の低下を 起すこともあります。 ストレスがあると肝の失調が起こるのですが、 同時に肝は筋肉にも関係がありますので、 こういう時は、ストレッチが良いのです。 筋肉を伸ばすことにより、 肝の失調を軽くさせます。 |
| ツイート |
|
更新日: 2020/04/07 |