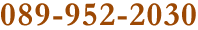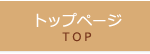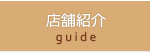ようやく松山も雨が降ってくれましたが、ダムは大して溜まってないとか・・・
雨やくもりの日はだるいですよね。
集中力もなく、頭が回らないなんてこともありますね。
何故、頭が回らないのか?
それは痰が関係しています。
この痰が酷い人は意識不明になることもあり、軽い場合は頭がボーっとしたりします。
痰と聞くと、あの痰を思い浮かべるかと思いますが、漢方の世界では、新陳代謝の低下によって生じる体の中に停滞したネバネバした液体のことも痰と呼びます。
痰は体のあちこちに停滞し、さらに新陳代謝を低下させて様々な病気の原因となります。
現代医学でも原因が分からない病気や、これといった良い治療方法のない自律神経失調症のように、消化系・呼吸系・循環系などの治りにくい病気の多くは、痰が原因であると考えられています。
例えば、胃腸機能が低下している人は水分代謝が悪く、胃腸に余分な水が停滞してますが、最初はサラサラしていた水も、停滞が長引けば、熱によりネバネバした痰に変わってしまいます。
この痰が頭に上がってくると、めまい感がしたり、頭がボーっとして頭が回らなくなったりします。
胸にくれば、胸の詰まりや胸苦しさ、焦燥感などを引き起こしたりもします。
こういう痰がある人は梅雨の時期に不調がくることが多いです。
思い当たる方はぜひご相談ください。
| ツイート |
|
更新日: 2017/06/28 |
|
梅雨に入りましたが、雨が降らないですね。
松山は20年くらい前に水不足になり、断水を経験してますが、もう二度と味わいたくないです。 今晩あたり雨が降ると言われてますが、ガンガンに降ってほしいものです。 日本は海に囲まれ、それに加えて梅雨があります。 梅雨をピークとして湿度が異常に上昇し、食習慣では冷たいものを摂る傾向にあるため、体内に余分な水分が溜まりがちになります。 この体内にある余分な水分は、胃腸機能を低下させ、食欲が出ず、無理に飲食しても胃もたれ、吐き気、酷い時には嘔吐などの症状も現れます。 また、便の状態は、軟便気味、酷い時には下痢や水様便となり、排便してもすっきり感は得られず、便器には排便がへばりついて、きれいに流れない状況になります。 皮膚にはジュクジュクした湿疹が繰り返し現れ、寝ても倦怠感はとれず、濡れたタオルで絞られるような頭痛が続く、長引く重だるい関節痛、胃腸症状を伴う夏風邪がなかなか治らないなど、湿気が影響を与える症状は山ほどあります。 この湿の邪気をきれいに取り除くことが重要です。 この湿の邪気を払うために使われるのが 藿香正気散! 私の好きな漢方薬の出番です。 藿香正気散は、外からの湿気を発散により追い払い、胃腸に停滞した水分を除き、気の巡りを良くし、胃腸の機能を回復させる力があり、発熱悪寒、頭痛、胃痛、悪心嘔吐、下痢などの症状を治します。 藿香正気散の応用として ・夏風邪 悪寒発熱、頭痛、全身倦怠感、無汗、鼻づまり、鼻水、あるいは頭と全身が重だるいという症状に加えて、腹痛、下痢、吐き気、お腹がゴロゴロ鳴るなどの胃腸症状を伴う状態に。 わかりやすく説明すると、暴飲暴食するときに、ガンガン効いている冷房に当たる時の体の不調です。 この夏風邪に藿香正気散は一番よく効きます。 ・水あたり 海外旅行など、飲みなれない水で体調が悪くなり、吐き気、嘔吐、下痢などの症状が出てくる場合に。 症状が出てからの服用でも良いけど、予防として服用するのも効果が期待できます ・腹痛と急性胃腸炎 食中毒、ノロウイルス感染などの時には、激しい嘔吐、下痢、腹痛を起こしますが、こまめに水分を補給する以外は特に対策がありません。 藿香正気散は諸症状を抑える上に抑菌、止痛作用もあります。 ちなみに私は藿香正気散に板藍根を併用して服用します。 ・冷房病 夏は基本的に暑い季節なので、汗とともにエネルギーも消耗しますが、至る所でアホみたいに冷房がガンガン効いています。 風邪には至らなくても全身倦怠感、気持ち的に抑うつ気分で、葛根湯などの強い発汗剤を使うと余計に汗をかきすぎて元気を消耗し、体調が更に悪化する恐れがあります。 藿香正気散は発散作用は穏やかですが、体を温めると同時に、全身の気の巡りを邪魔する湿の邪気を取り除きます。 ・車酔い 乗車前に服用すると予防効果が期待できます その他にもあせもや湿疹、蕁麻疹、帯状疱疹などに塗布するなど用途は様々あります。 まぁ、1回使ってみたら私が藿香正気散を気に入るのが分かると思いますよ。 |
| ツイート |
|
更新日: 2017/06/20 |
|
大豆製品を食べる日本人は、乳がんの罹患率が低くなることが分かっています。
国立がん研究センターが実施した10年間に渡る追跡調査でも、味噌汁を1日に3杯以上飲む人は、1日に1杯未満しか飲まない人と比較して、乳がんになるリスクが40%も低くなるとの結果が出ています。 乳がん細胞は、その表面にある受容体たんぱく質にエストロゲンという女性ホルモンが結合すると増殖のスイッチが入ります。 大豆イソフラボンは、エストロゲンと化学構造が似ており、エストロゲン作用と抗エストロゲン作用の両面を持っています。 エストロゲンの血中濃度が高いときは、大豆イソフラボンは抗エストロゲン作用を示すため、乳がんの発生を予防するのではないかと考えられています。 また、抗エストロゲン作用の他に、抗酸化作用やがん細胞の増殖を抑える作用など、多くの抗がん作用が報告されています。 だからと言って、大豆の食べ過ぎはどうかと思います。 古文献には、大豆を食べ過ぎると気が詰まり、痰を生じて体が重くなり、顔にヘルペスを誘発しやすいと書かれており、食べ過ぎには注意した方が良いですね。 |
| ツイート |
|
更新日: 2017/06/19 |
|
今日の読売新聞に
妊婦の喫煙や受動喫煙によって、生まれてくる赤ちゃんが、アトピー性皮膚炎や乳児湿疹になるリスクが上がる可能性がある と書かれていました。 アトピー性皮膚炎は、強いかゆみを伴う皮膚炎で、免疫の過剰反応であるアレルギーを持つ場合が多く、子どもの場合、比較的よくみられる乳児湿疹が2ヶ月以上続いた場合などに診断されます。 発症には、親から受け継いだ体質が関わっているとの見方もあります。 アトピー性皮膚炎は、痒み、睡眠不足の他、患部からしみ出す液の対処や薬の塗布、見た目の変化などによって生活の質が大きく低下します。 子どもや妊婦に対する喫煙・受動喫煙の影響としては、早産や低体重などの妊娠中や出産時のトラブル、出生後の乳幼児突然死症候群や気管支ぜんそくなどの発症のリスクが高まることがこれまでの研究で指摘されています。 これらに加えて、子どものアトピー性皮膚炎も、母親のおなかの中にいる時期のたばこの煙が関係していることが明らかになってきました。 赤ちゃんが7ヶ月以上の約1500組を対象にした結果、妊娠28週以降に喫煙・受動喫煙が「ない」と答えた妊婦の赤ちゃんが皮膚疾患になる割合が26.6%に対し、「ある」とした妊婦の赤ちゃんは38.0%と明らかに高かった と書かれていました。 明らかに高いのか?なんか微妙な感じがするんですけどね。 まぁ、確かにたばこの煙は有害ですので、気をつけるにこしたことはないですね。 赤ちゃんのアトピー性皮膚炎などは、添加物の過剰摂取の方が大きく影響を与えているんじゃないかと私は思います。 今や添加物が完全に入っていない食事しかしないという人はまずいないですよね。 普通に自炊してても、年間で約2kgは添加物を摂取していると言われてます。 インスタント食品や冷凍食品、お総菜などの加工食品は楽だし、美味しいし、つい買って食べちゃいますわ。 聞くところによると、おにぎり1個に添加物10種類くらい入っているらしいですよ。 おにぎりだけでこんだけ入ってるってことは、弁当だとどのくらいになるんでしょうね? 表示されているものだけが入っていると思ってはいけません。 キャリーオーバーという表示が免除されるものがあるからです。 かまぼこを例にとると、魚肉や調味料のような原料として用いられているものに、元々使用されている添加物があっても、それらをパッケージに表示をしているときりがないということで、表示免除されちゃいます。 キャリーオーバーという機能があるために、製造に携わる人以外は、添加物がどれくらい入っているのか正確にわかる人はいないんじゃないかな? 添加物まみれの食べ物を美味しいと言って食べている小さなお子さんを見ると悲しくなってきます。 もう添加物なしの生活には戻れないため、極力、少ないのを選んだり、摂った分を上手に排出させるようにするしか方法はないかもしれません。 体内にある添加物を排出するのには、葉緑素がたっぷりのクマ笹が良いのかなと思います。 別に野菜や青汁でもいいんじゃない? 違うんですよね。 野菜や青汁に含まれる葉緑素は不安定で、胃酸で分離されて別の物質になってしまうんです。 (緑の野菜をしばらく放置していると黄色く色が抜け落ちるのを思い浮かべていただければいいかと) クマ笹もそうなんですけど、ササヘルスという医薬品は独自の製法で安定化させ、葉緑素としての働きを存分に発揮できるようにしています。 環境汚染を受けない標高1000m以上の高さに自生する国産クマ笹を使用し、着色料、防腐剤、添加物一切入ってない100%クマ笹エキスだから、安心安全です。 添加物と上手に向き合っていきましょう。 |
| ツイート |
|
更新日: 2017/06/18 |
|
昨日、大阪の某中学校のグランドで、体育祭に参加していた生徒18人が熱中症とみられる症状を訴え、うち14人が病院に搬送されました。
1時間に一度は水分補給するよう放送で促したけど、帽子をかぶるよう指示はしてなかったという。 熱中症の原因は、簡単に言えば、汗によって体に必要な水分が奪われることによって内臓や脳の機能が低下することにあります。 人の体は約60%が水分。 そして、体重のたった2%の水分が失われただけでも人の体は脱水状態になり、喉の渇きを感じ始めます。 体が脱水状態になるということは、血液中の水分も減ってしまい、ネバネバした血液となり、血管内でつまりやすくなります。 よく1日2リットルは飲みなさいと言われていますが、ぶっちゃけ、そんな量、飲めたもんじゃないですね。 お年寄りや胃腸が弱い人が無理に摂り過ぎると、胃酸を薄めてしまい、消化不良となったり、胃腸の働きを悪くすることもあります。 また、冷え性やむくみがある人は水分代謝が悪いため、水分の摂り過ぎは反って悪くなることもあります。 なんでもそうなのですが、○○過ぎないことです。 汗で失われるのは水分だけではなく、元気も失われてしまうので、水分補給するときに一緒に飲んでほしいのが、生脈散です。 生脈散に配合されている人参で汗によってエネルギーを補給し、麦門冬で水分を補い体のほてりを冷まし、五味子で汗の出過ぎを抑えてくれます。 スポーツドリンクに溶かしてこまめに飲むことによって、熱中症予防になります。 |
| ツイート |
|
更新日: 2017/06/17 |