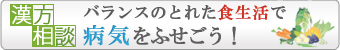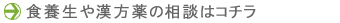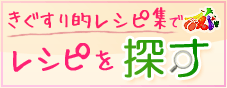きぐすり.com は、漢方薬、女性の健康、サプリメント、ハーブの情報を専門家がやさしく解説しています。
二階堂先生の「食べ物は薬」
アイ - 葉や実は生薬や食品に、葉は藍染染料として広く使われます

- アイ
- 学名:Persicaria tinctoria
- 科名:タデ科
- 和名:アイ
- 英名:indigo plant
- 別名:タデアイ、アイタデ

-
ベトナム南部原産の1年草で、藍染の染料植物として中国から渡来しました。今では徳島県、北海道、青森県などで栽培されています。
茎はよく分枝し、50~80cmの高さに達し、紅紫色を帯びています。
葉は互生し、全縁で有柄の長楕円形をしており、先端が尖り、托葉はさや状をして、茎を抱いており、辺縁に毛があります。
秋になると穂状に紅色で多くの小花を咲かせ、花後、3稜を持つ卵形の痩果となり、中に黒褐色の種子があります。
葉を摘んで乾燥したものが生薬の「藍葉(らんよう)」で、果実を採取して乾燥したものがやはり生薬である「藍実(らんじつ)」です。この藍実は中国最古の本草書である神農本草経の上品の部に記載されており、消炎、解熱、解毒の目的に煎じて服用します。藍葉も同様に煎じて服用すれば解毒の効があるとされており、生の葉の汁液は毒虫刺されや蛇などに噛まれた傷の治療に外用すれば効果があると言われています。
葉は藍色染料として古くから用いられており、生葉を用いることもありますが、一般的には乾燥した葉を室で長期間発酵させて作った蒅(すくも)を藍玉にして行う蒅染めが、高度の技術や手間がかかりますが染料保存の利点があり、徳島県で主として行われています。藍染された布で作った肌着は冷え性や肌荒れに効果があると古くから言われており、抗菌、消臭、防虫などの作用があり、また耐火性もあることから江戸時代の火消しの半纏や、国鉄時代の蒸気機関車乗務員の制服にも使われました。今では衣類だけでなく革製品やインテリアでも広く使われています。
近年抗がん作用や抗菌活性を示す生理活性成分が見出されており、また4つの大学の共同研究により青森県産のタデアイ葉エキスに新型コロナウイルスの細胞への侵入防止作用が見出され、国際的学術雑誌に掲載されました。
葉や実にはポリフェノール、ミネラルや食物繊維が豊富に含まれており、食用としても使われています。実を発芽させて刺身のツマや薬味に、葉は天ぷら、揚げ物、汁の実、お茶などして使われます。かつて徳島市で開催されたアイの料理会では豆腐、雑炊、鮎膳、つみれ、サラダ、煮物、天ぷら、吸い物など多くの料理に供されました。また生の葉の搾り汁には解熱、解毒、魚やキノコ中毒、精力減退、腹痛などに効果があるとされています。その他にも葉の粉末を入れたクッキー、藍の青汁やサプリメントなども商品として見られています。