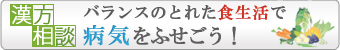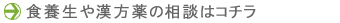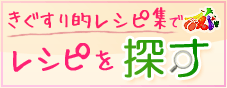きぐすり.com は、漢方薬、女性の健康、サプリメント、ハーブの情報を専門家がやさしく解説しています。
二階堂先生の「食べ物は薬」
オオバコ - 踏みつけに強く、葉を食用に、全草や種子を生薬として利用します

- オオバコ
- 学名:Plantago asiatica
- 科名:オオバコ科
- 和名:オオバコ
- 英名:chinese plantain, amoglossa
- 別名:オンバコ、スモウトリグサ、オバコ、カエルバ、ホウキオオバコ、牛遺(ぎゅうい)、當道(とうどう)

-
日本全国、中国大陸をはじめ東アジア全域の山野にくまなく野生している多年草です。日本で見られるオオバコ属(plantago属)の仲間は数種しか知られていませんが、このplantagoというラテン語は「足の裏で運ぶ」という意味で、「人が歩くところに必ずオオバコがある」ことを示しています。また中国では牛車や馬車が通る道端に多いことから「車前草(しゃぜんそう)」と呼んでおり、踏みつけに非常に強く、人や車が踏みつけるところにはオオバコだけが生えています。太くて短い地下茎から根生葉が四方に広がり、その葉が広くて大きいことから「大葉子(おおばこ)」の漢字が付けられています。
オオバコは双子葉類なので一般に葉脈は網状脈なのに、単子葉類に見られる平行脈になっています。
大きな葉と葉の間から伸びる花茎の先端には小さな花が穂状につき、下から上へと次々に咲いてゆきます。
果実は熟すと蓋つきの器の様な形で、お椀のように蓋が開いて、その中に扁平な黒褐色の小さな種子が入っています。種子の表面には粘液質が多く、水気を帯びると粘り気が出て、靴の裏などに付き、牛馬や人とともに広がって行きます。
主として葉を食用としますが、葉脈が太くて堅いので花が付く前の株から若葉を摘み採り、良く茹でてから水にさらして和え物、浸し物、炒め物や煮付けにしたり、砂糖や、味噌と一緒に煮て食用にします。生のまま天ぷらや、細切して炊き込みご飯にしても用いられます。乾燥葉はオオバコ茶として飲用できます。世界中にはオオバコ属だけで約250種が知られており、日本で野生している近縁種のヨーロッパ原産で、今では日本に帰化したヘラオオバコ(P. lanceolata)、日本で最も大型のトウオオバコ(P. japonica)や日本海側に多い小型のエゾオオバコ(P. camtschatica)なども同様に食用となります。
花期の全草を陽乾したものを生薬の車前草(しゃぜんそう)、成熟種子を車前子(しゃぜんし)と呼び、煎じて下痢止め、咳止めや利尿などに用いられており、牛車腎気丸(ごしゃじんきがん)や竜胆瀉肝湯(りゅうたんしゃかんとう)などの漢方処方にも配合されています。民間薬として鎮咳去痰、降圧、強壮薬や、葉を炙って腫れ物に貼って用いられます。
成分としては花期の全草にイリドイド配糖体のアウクビン、フラボノイドのプランタギニンやトリテルペノイドのウルソール酸などを、種子にはコハク酸やアデニン、コリンや脂肪酸などが含有されています。
カエルをいじめると死んだマネをしますが、オオバコの葉をのせたり、つつんだりすると生き返ったようにピョンと飛ぶのでカエルッパとかゲーロッパなどとも呼ばれています。
以前講義の中でオオバコのように皆さんもいろいろの苦難に負けない、踏まれ強い人間になって下さいと話したものです。