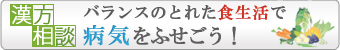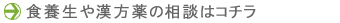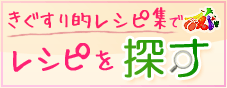きぐすり.com は、漢方薬、女性の健康、サプリメント、ハーブの情報を専門家がやさしく解説しています。
二階堂先生の「食べ物は薬」
サルナシ - 野生果実で最も美味い珍果です

- サルナシ
- 学名:Actinida arguta
- 科名:マタタビ科
- 和名:サルナシ
- 英名:tara vine hardy kiwifruit
- 別名:シラクチカズラ、シラクチヅル、コクワ、ベビーキウィ、ミニキウィ、 ミズカズラ、スイトウボク(水筒木)、イカダムスビ

-
日本、朝鮮半島、中国大陸などの一部に分布し、日本では北海道、東北地方に多く見られる雌雄異株又は雌雄雑居性、つる性の落葉性植物です。
茎はつる性で他の樹木や岩に高くよじ登って生育します。直径が15cm前後と太くなり、樹皮ははじめ毛があって、後に無毛となります。その髄には隔壁があって階段状の空所が見られます。
葉には長い葉柄があり、厚く革質をしており、鋸歯があります。表面に艶があって互生し、大小不整の赤茶色をした葉は黄葉しますが、マタタビのように白色にはなりません。
5月~7月頃に小さな枝の上方に腋生して垂れてくる花序に1~10個くらいの梅の花に似た白い5弁花を下向きに付けます。雄花は数個が群がって付き、一方の雌花は1個ずつ付きます。
果実は淡緑色をした2cmくらいの無毛で小さな液果となり、秋に熟すと緑黄色となり多汁質で香りが強く、かすかな酸味と甘味とがあるもので「珍果」と呼ばれるほど食味が知られており、野生の果実では最も美味いとも言われています。野生動物、とくに哺乳類に好まれ、日本ではサルやクマなどに大量に摂食されて種子散布されます。熟果は生食や、果実酒やジャムなどに加工され、軟らかな若芽は茹でて浸し物、汁の実、和え物、炒め物や天ぷらなどとして食べられます。ビタミンCを多く含み栄養価が高く、タンパク質分解酵素を大量に含んでいるので、疲労快復や強壮の効果が知られ、整腸、補血、解熱作用なども知られています。東北地方では蔓に含まれている多量の樹液を脚気、心臓、腎臓や咳・痰などの薬として飲むことが知られています。
和名の由来は猿梨(サルナシ)で、猿が好んで食べる山の果実から付けられたと言われ、また猿が岩の窪んだ所に果実を蓄えて発酵させて猿酒を作るとも言われ、その主たる果実がコクワ(サルナシの別名)と言われています。蔓は丈夫で腐りにくいことから、杖やもっこなどの材料としたり、筏をしばるのでイカダムスビとも呼ばれたり、徳島の祖谷にある吊り橋「蔓橋(かずらばし)」の材料として有名です。太い幹は床柱、土瓶敷に、樹皮は綱、火縄や脚絆などにもかつては使われていました。太い蔓は吸水能力に富み、中に大量の樹液を含んでいるので山仕事などで喉を潤すため、下部の切り口から飲むことからスイトウボク(水筒木)やミズカズラ(水蔓)の別名が知られています。