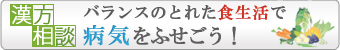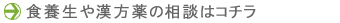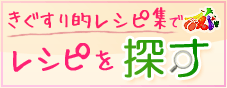きぐすり.com は、漢方薬、女性の健康、サプリメント、ハーブの情報を専門家がやさしく解説しています。
二階堂先生の「食べ物は薬」
トロロアオイ - エディブル・フラワーとして食用に、根の粘液は紙漉きに

- トロロアオイ
- 学名:Abelmoschus manihot .
- 科名: アオイ科
- 英名:sunset hibiscus
- 別名:トロロ、ネリ、クサダモ、黄蜀葵(おうしょっき)、花オクラ
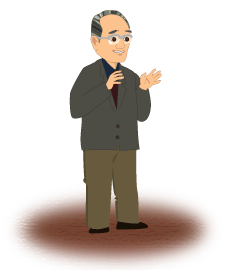
-
中国原産の一年草で、暖地では多年草になります。日本には室町時代に渡来しました。
草丈は1~1.5mで直立して剛毛が生えています。
葉には長い葉柄があり、互生し、掌状で深い切れ込みがあって不規則な鋸状になっています。茎頂に淡黄色で大きな5弁の花を付け、横向きで、やや下向きに開きます。
果実には5本の稜が見られ、かたい毛が生えて長楕円形をしており、先端が尖っています。扁平な形をした種子が果実中に多数入っています。
根は太くて長く、紡錘形をしています。
未熟な果実は茹でて食用にします。また花はエディブル・フラワー(花野菜)として栽培され、花弁をサラダに生のまま用いたり、天ぷらや酢の物にして食べられます。ぬめりがあり、美味しいが一日花なので市場には出ませんが「ハナオクラ」の別名で呼ばれています。
花が終わった頃に根を掘り起こし、地上部を除いて水洗、外皮を除いて乾燥させたものが生薬の黄蜀葵根(おうしょっきこん)で鎮咳,緩下、利尿などの作用が知られています。のどの腫れや痛み、扁桃腺炎などには煎液を用います。その他、催乳作用もあり、火傷の湿布剤にしたり、粉末を丸剤や錠剤の賦形剤としたこともあります。この生薬の有効成分は多量の粘液質(ラムノース、ガラクツロン酸からなる多糖類)です。根の他に花、葉や種子も生薬として知られています。
根から得られる粘液を「ネリ(糊)」と呼び、紙を漉く時にコウゾやミツマタなどの植物繊維を水の中で均一に分散させるための添加剤として利用されています。これにより上質で丈夫な紙になり、紙幣などの原料としても使われています。また和紙漉き以外にも蕎麦のつなぎや、漢方薬の成形などにも利用されています。
葉や茎は媒染剤を用いての黄色、オリーブ色や黄茶色の染色にも使われます。
名前の由来はアオイの仲間である、この植物の根や果実にある粘液をトロロ(イモ)にたとえトロロアオイと呼ばれています。