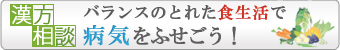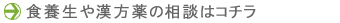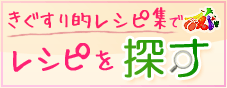きぐすり.com は、漢方薬、女性の健康、サプリメント、ハーブの情報を専門家がやさしく解説しています。
二階堂先生の「食べ物は薬」
チョロギ - 正月の御節料理にも使われるおめでたい食材

- チョロギ
- 学名:Stachys sieboldii
- 科名:シソ科
- 和名:チョロギ
- 英名:chorogi, Chinese artichoke, Japanese artichoke
- 別名:チョロキチ、ネジリイモ、ヨメノゾキ、クビレイモ、トロミ、チョウロギ、ショロキ、チョロク、草石蚕(くさいさご)

-
中国原産の多年草で、17世紀(江戸元禄時代)に中国から渡来し、19世紀末にヨーロッパではフランスにはじめて渡り、その後、アメリカへは20世紀初めに渡って今では世界に広く分布しています。
地方によって多くの別名や、漢字が知られている少し変わった名前の植物ですが、チョロギの名のおこりは朝、露が落ちて、地中に出来た球という意味で「朝露葱(ちょろき)」から来たものとされています。
「長老喜」「長老木」「長老貴」などの縁起の良い漢字も知られていることから、日本では正月の御節料理に黒豆と一緒に、梅酢で赤く染めたものを盛り付けされる、おめでたい食材として使われ、また古くは救荒食物としても使われていました。
茎は直立し、高さは25~60cmほどになり、下向きの毛が生えており触るとざらつきが感じられます。葉は対生し、先端は尖っていて、葉縁には鋸歯があります。
葉腋ごとに花穂を出し、紅~青紫色で唇状の小花を輪生します。
秋に地下茎の先が数珠状又はカイコ様に肥大し、長さ2~4cm程度の塊茎を付けます。これを掘り起こして食用としますが、収穫した時の表面は真っ白で、徐々に黄色味を帯びてきます。生のまま食べることはなく、梅酢で赤く染めたり、塩漬け、砂糖漬け、醤油漬けなどにして食べます。煮るとユリ根に似た食感、味がし、ショウガのような辛味もあります。その他にも吸い物の具や天ぷら、バター炒め、酢漬けなどにする調理法もあります。フランスでは古くからよく使われる食材として知られており、スープ、炒め物、クリーム煮やサラダなど様々な調理法が知られており、日本風のフランス料理には必ず付け合わせとして盛り付けられると言われています。
有効成分としては少糖類のスタキオースが非常に多く含有されており、腸内環境を整える整腸作用が知られています。また中国の「本草綱目」には外からの病の侵入を防ぎ、血の滞りを治し、気を静める効果があると書かれています。その他、生の塊茎を細砕して、すり下ろしたものを打撲の際の患部に直接塗布して用いることも知られています。