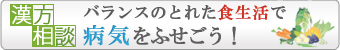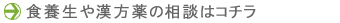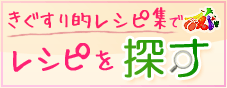きぐすり.com は、漢方薬、女性の健康、サプリメント、ハーブの情報を専門家がやさしく解説しています。
二階堂先生の「食べ物は薬」
ミソハギ - 盆花としてだけでなく食用に、また薬用としても用いられています

- ミソハギ
- 学名:Lythrum anceps
- 科名:ミソハギ科
- 和名:ミソハギ
- 別名:鼠尾草(そびそう)、盆花(ぼんばな)、水掛草(みずかけそう)、精霊花(しょうろうばな)、微萩(みそかはぎ)

-
アフリカ北部やユーラシア大陸などに分布しており、日本では本州より南方の地域で、やや湿った場所や、野山の水辺などに広く自生している多年草です。各地の山野に生えていて、お盆の頃にあざやかな花が比較的長く咲くことから、日本では古くから盆花として用いられています。
茎は1m前後で、地下茎から直立しており、上の方では枝を出し葉は細長く葉柄はほとんどありません。葉は対生して披針形で尖っており、基部は狭くなっています。
花は先端部の葉腋に紅紫色で6弁の小さな花が集散花序として付いています。属名のLythrumはlytron(血)を意味しており、花の色に由来しています。
植物和名の由来としては禊(みそぎ)に用い、萩に似ていることから禊萩(みそぎはぎ)が短くなったとする説や、溝に生える萩から溝萩(みぞはぎ)から転じたとする説と、この植物に喉の渇きを止める作用が知られているので、亡くなった人の渇きを癒すとする説などが知られています。
食用とするには若い芽を摘み採り、軽く熱湯を通してからアク抜きのため水にさらしてから酢の物、和え物や佃煮にして食べます。花はそのまま、ないしは数秒間湯がいてから、サラダなどに添えて食べます。
食べ過ぎると腹痛などを起こすことがあるので注意しましょう。
花の終わる頃に地上部を採取してから陽乾したものが生薬の千屈菜(せんくつさい)で、下痢止め、腸カタル、膀胱炎やむくみなどに煎じて服用します。また冷やした煎液を使ってあせも、股ずれ、湿疹、切り傷などの止血に冷湿布として用いられます。水で煎じたものを夏には冷やし、冬には暖めてお茶として用いたり、夏の喉の渇きを止める目的で服用することもあります。
有効成分としてはタンニン、コリンや、配糖体のサリカイリンが知られています。