きぐすり.com は、漢方薬、女性の健康、サプリメント、ハーブの情報を専門家がやさしく解説しています。
女性の生活と健康
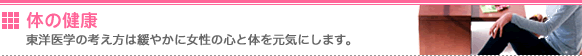
|
| |
| |
|
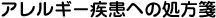
|
 |
| 最も大切なことは、日常生活を見直すことにあると考えています。 |
|
| |
 |
漢方外来にはアレルギー患者が一杯
|
漢方外来をしていると、様々なアレルギー疾患の老若男女が来院します。
まず花粉症。2,3月のまだ寒い時期からスギの花粉の飛散は始まるので、そこから4,5月頃のヒノキの花粉、5,6月のイネ科の花粉まで切れ間なく、鼻炎や結膜炎の患者がやってきます。「今日の天気予報」に花粉情報が入るようになったのはいつ頃からだったのでしょうか。このような情報が必要なほどに、最近の20年間で花粉症の患者は急速に増えていて、今や国民の10人に1人が花粉症といわれています。
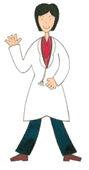 この花粉症も症状に時代的変化が見られます。一昔前までは激しいくしゃみと共に水のような鼻水が出る典型的な1型(即時型)アレルギーの鼻炎が、圧倒的に多く見られました。このタイプには小青竜湯(しょうせいりゅうとう)※や麻黄附子細辛湯(まおうぶしさいしんとう)※などの味が辛く、温める力が強い漢方薬がめっぽう効果的で、一度処方すると毎年必ず花粉が飛ぶ季節には来てくれる、医者にとってはありがたい常連患者さんになります。 この花粉症も症状に時代的変化が見られます。一昔前までは激しいくしゃみと共に水のような鼻水が出る典型的な1型(即時型)アレルギーの鼻炎が、圧倒的に多く見られました。このタイプには小青竜湯(しょうせいりゅうとう)※や麻黄附子細辛湯(まおうぶしさいしんとう)※などの味が辛く、温める力が強い漢方薬がめっぽう効果的で、一度処方すると毎年必ず花粉が飛ぶ季節には来てくれる、医者にとってはありがたい常連患者さんになります。
しかし最近では鼻水より鼻閉の方が強く、同時に激しい眼の痒みも伴うタイプが増えてきており、アレルギーの程度がより強く、熱化してきているのがわかります。そのためステロイド吸入薬や抗アレルギー剤などとの併用を余儀なくされる場合もよくあります。それでも耳鼻科から漢方治療に鞍替えする患者が多いところをみると、西洋薬だけでも快適な生活は送り難いようです。こんな症例には石膏が入った越婢加朮湯(えっぴかじゅつとう)※や麻杏甘石湯(まきょうかんせきとう)※、桑菊飲(そうぎくいん)※など清熱タイプの漢方薬を使います。
花粉症が一段落した初夏の頃になると、今度は痒疹や蕁麻疹、アトピー性皮膚炎の増悪など、アレルギー性皮膚疾患が暴れ出します。現代の住宅環境は密封性が高く冷暖房が完備しているためか、一定の季節にダニなどが繁殖しますし、初夏から夏は昆虫達の季節ですから、虫アレルギーとしての痒疹患者が後をたちません。またアトピー性皮膚炎は汗をかくと痒みが強いため、掻爬してひどい皮膚状況になっている人たちが続出です。時にはトビヒやヘルペスウイルス感染症を併発します。
皮膚病変は患者個々によって複雑なので、パターン化した漢方薬ではなかなか対処できません。一人一人に対して、丁寧な診察や細かく来院してもらっての観察が必要となり、相当時間を要します。
また漢方軟膏や漢方入浴剤、消毒薬など害がなくて、皮膚に効果的なものは様々に利用していきますが、ステロド外用薬は漢方外来では拒否する方も多く、私もできるだけ使用は最小限にと考えています。その他入浴方法や食事の指導も含めると、初診の場合20~30分は十分かかります。
このように手間や時間がかかっても皮膚科を標榜していなければ、悲しくなるほどの低い医療点数でしかありません。でも見て変化がわかりやすいだけに、改善すると何人もの患者仲間を紹介してくれるため、受診疾患としては断トツに多いのが現状です。医者冥利と経営の狭間に悩みながらも、皮膚科疾患はいつの間にか好きな分野になってしまいました。
|
|
|
 秋も深まり冬が近づいてくると、呼吸器疾患が増えてきます。典型的な気管支喘息だけでなく、その類縁疾患である咳喘息などもよく来院します。 秋も深まり冬が近づいてくると、呼吸器疾患が増えてきます。典型的な気管支喘息だけでなく、その類縁疾患である咳喘息などもよく来院します。
すでに気管支拡張剤、ステロイド、抗生物質などを他の医院で処方されているのに、咳が改善しないというような訴えが多いのですが、少し休息を入れて小青竜湯※、麻杏甘石湯※、竹茹温胆湯(ちくじょうんたんとう)※、麦門冬湯(ばくもんどうとう)※、参蘇飲(じんそいん)※などを処方しながら、生姜(しょうが)や紫蘇(しそ)、羅漢果(らかんか)などの入ったお茶なども勧めます。
しかし吸入ステロイドが喘息の標準治療薬となってからは、重症喘息患者が漢方医に来院することは、明らかに以前よりも減ってきています。
|
|
|
|
|
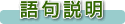
※小青竜湯(しょうせいりゅうとう)
身体を温め胃腸機能も高めることによって、余分な水湿を取り除き、鼻水や咳、痰などを改善します。
※麻黄附子細辛湯(まおうぶしさいしんとう)
元来は冷え性の老人などのカゼ薬として、身体の内外を温めて改善する薬ですが、くしゃみを伴うアレルギー性鼻炎には即効性があります。
※越婢加朮湯(えっぴかじゅつとう)
局所の熱化した水湿を取る漢方薬です。眼の痒みや鼻閉などに効果があります。時には関節にたまった水腫を取り除く薬としても使われます。
※麻杏甘石湯(まきょうかんせきとう)
熱を取りながら肺の働きを高めて、咳や痰を改善すると共に鼻閉や眼の痒みにも効果があります。
※桑菊飲(そうぎくいん)
元来は粘稠な痰を伴う気管支炎などに効果がありますが、眼の痒みにもよく効きます。
※竹茹温胆湯(ちくじょうんたんとう)
粘稠な痰や咳がしつこく続き、のどもいがらく痒いような場合に効果的です。特に夜間にひどくなる場合によく効くとされています。
※麦門冬湯(ばくもんどうとう)
痰がのどにこびりついて取れないような、乾いた咳に使われる漢方薬です。喉を潤しながら咳や痰を治めます。
※参蘇飲(じんそいん)
元来は粘稠な痰を伴う気管支炎などに効果がありますが、眼の痒みにもよく効きます。
|
|
| 文:河崎医院付属淡路東洋医学研究所 日笠久美先生 |
 |
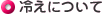
|
「最近疲れが取れないのよね」と思ったりすることがありませんか? |
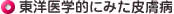
|
皮膚科の診療をしていますとよく遭遇する質問があります。 |
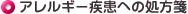
|
最も大切なことは、日常生活を見直すことにあると考えています。 |
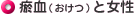
|
漢方はお血(おけつ)の改善を援助する「縁の下の力持ち」です。 |
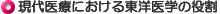
|
西洋医学的疾患概念や病態の把握は東洋医学におけるそれとおおきく異なります。 |
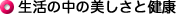
|
四季の変化、月ごとの変化、さらに一日の中でも体は環境によって変化しています。 |

|
変化する食生活の改善・・・・摂取する脂質の種類 |

|
漢方と、補助療法としてのアロマセラピー |
|
|