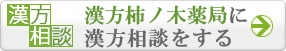きぐすり.com は、漢方薬、女性の健康、サプリメント、ハーブの情報を専門家がやさしく解説しています。
薬局・薬店の先生による健康サポート
低体温:体温を自ら作り出せない状態

人のからだは他の恒温動物と同じように、自ら体温を作り出すようにできています。
体温にはからだを温めることで新陳代謝を促したり、抵抗力や治癒力を高めるなど、生命活動そのものを支える役割があります。
この体温を継続して作り出せない状態(低体温)が続くと、倦怠感や疲労感をはじめ、鈍痛や冷感、分泌異常や排尿異常などの不調が現れるようになります。体温に伴って現れるこれらの症状は、総称して低体温症と呼ばれます。
体温は老化と共にわずかに低下していきますが、最近では過度なダイエットや運動不足、過剰な冷飲食を通じて、若くして低体温に陥る方も少なくありません。
体温を整えて、健康的な毎日を
健康な人の基礎体温はおよそ36.5度。これを下回ると体が冷えやすくなるだけでなく、免疫力が低下することで風邪やインフルエンザを患いやすくなり、心身はとても疲れやすくなります。
人のからだは、疲労を繰り返したり、年齢を重ねたりする事で自らを温める働きが衰え、冷えやすくなります。その逆に、温まる事で元気になり、からだのあらゆる活動が活発になり、抵抗力や治癒力も上昇していきます。
低体温の改善:効率よく温まるからだ作り
体温の産生・維持を支えているのが、全身の筋肉や消化器官の働きです。
筋肉は人体最大の発熱器官として、脂肪とともに体温維持に貢献しており、消化器官も飲食物の消化・吸収を通じて体温の産生を担います。
漢方では筋は肝が養う、肉は脾が養うと考えられています。低体温を改善するには、からだを温めることに加えて、肝・脾の養生を通じてからだの陽気を高めて、効率よく温まるからだ作りを心がけることも大切です。

 ▲
▲ 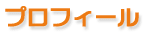
 漢方 柿ノ木薬局
漢方 柿ノ木薬局