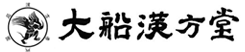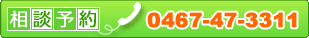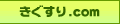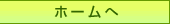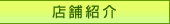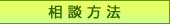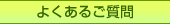杜仲は一科一属一種(トチュウ科トチュウ属)の落葉高木で、漢方では樹皮を用います。樹皮の切片は粘りがあり繊維質の糸を引くのが良品とされています。
中国最古の薬学書「神農本草経」には、「精気を増し、筋骨を堅くし、志を強くし、陰下癢湿、小便余歴を除く。久しく服用すれば身を軽くし、老いに耐える」と書かれています。
<杜仲の名前の伝説、その1>
李時珍著「本草綱目」によると、昔、杜仲という名の人がいつも、ある木の樹皮を煎じて飲んでいました。すると、活力がみなぎってきて、杜仲はやがて仙人になったとされています。仙人の真偽は別として、仙人となった杜仲は霞を食べ、秘薬(樹皮)を摂り、雲に乗って空を自由に飛び、美女との出会いを楽しんだと言われています。
その秘薬が杜仲と呼ばれるようになりました。
<中国の民話「杜仲の名前の由来、その2」(山東省)のお話>
中国の南方の山々の中にある杜家冲という部落に、樹齢が二千年にもなる大樹が生えていました。付近に住んでいる巫女が万病を治せる木だと言っていたので、多くの病人が木の下でお参りし、線香の灰と削り取った樹皮を持ち帰りました。そして、その樹皮と灰を煎じて飲むと病気が治るのでした。
軟骨病(骨が弱る病気、現代の骨粗鬆症)の病人もその樹皮を煎じて飲んだところ、すっかりよくなり、歩くことができるようになりました。人々はその木を「神樹」と呼んでいました。
この樹皮は杜家冲の人達が薬効を発見したので「杜冲(ドゥツォン)」と名付けられましたが、後の人々が「にすい」を「にんべん」に変え、「杜仲(ドゥジョン)」と呼ばれ日本語読みでは「杜仲(とちゅう)」となりました。
<杜仲茶のお話>
昭和50年代、長野県では桑に代わる推奨作物を探していました。そこで中国の杜仲が候補に上がりましたが、杜仲の樹皮は収穫から再生まで時間がかかる上に、杜仲の木の幹の樹皮部分は薬事法で一般販売が禁止されていました。そこで、薬事法に触れないで販売できる杜仲の葉をお茶にすることが考えられました。
そこで、富山医科薬科大学の和漢薬研究グループの難波教授に依頼し、動物実験をした結果、降圧、利尿等の作用があることがわかりました。杜仲の葉は苗を植えてから2年位で収穫でき、その後も毎年収穫できます。長野県は県の推奨作物として杜仲栽培を農家にすすめました。
日本人の発案による杜仲茶は、外国でも販売されるようになっています。
|
更新日: 2018/04/15 |