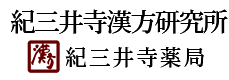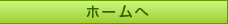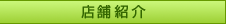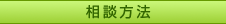今回は、東洋医学において花粉症はどう考えられているかを
簡単にご紹介いたしましょう。
» 続きを読む
頭痛・咽喉痛・鼻水etc・・・これらの症状が起こり
花粉症の時期でもないとき、皆様は『風邪』と表現していませんか?
そう、東洋医学においても、花粉症は風邪の一種として捉えています。
元々、東洋医学にアレルギーなんてものは存在しませんからね。
現代医学的に言えば、これは風邪症候群と日本では言われていますが
英語圏の病名で「Cold syndrome(コールドシンドローム)」は
寒冷症候群になってしまいますし
海外でも定義は曖昧で、一般的に海外の医学書では
上気道感染症という表現が適切となっており
風邪という病名は医学書には無いと言えます。
つまり、風邪という病名は
「風邪(ふうじゃ)」という東洋医学の言葉が語源なわけですね。
風の邪は、東洋医学では春に起こりやすいと考えられており
旧暦で考えた場合、2月頃~4月末ぐらいが春ですから
丁度花粉症の時期と同じですよね?
他にも風の邪は、肝の病を引き起こしやすいとされており
ここで言う肝は、確かに肝臓の事なのですが
昔から『肝を冷やす』という表現があるように
肝の病は精神疾患等も引き起こすと考えるのが
実に東洋医学らしい考え方です。
ちなみに、東洋医学では春の季節は、四獣神 で考えた場合
で考えた場合
青龍にあたり、これを語源にしたかどうかは定かではありませんが
皆様がよくご存じで
病院等でも花粉症によく処方されている漢方薬の代表格として
小青龍湯があります。
こんな占いじみた手法で使ってみても効果が出てしまうのが
東洋医学の奥深さと言えましょう。
もちろん、ちゃんと東洋医学の知識を身につければ
多様な花粉症に対応することが可能ですので
小青龍湯だけが花粉症の漢方薬ではなく、他にも様々な漢方薬がありますし
それらを事細かな症状に応じて扱いこなせなければ
本当の意味で漢方薬が扱えるとは言えないわけなんで
猫も杓子も小青龍湯なんていうのは
落語の葛根湯医者 にも劣る行為なんですけどね。
にも劣る行為なんですけどね。
しつこい花粉症で悩まれている方は、是非、本当の漢方薬をお試しください♪
頭痛・咽喉痛・鼻水etc・・・これらの症状が起こり
花粉症の時期でもないとき、皆様は『風邪』と表現していませんか?
そう、東洋医学においても、花粉症は風邪の一種として捉えています。
元々、東洋医学にアレルギーなんてものは存在しませんからね。
現代医学的に言えば、これは風邪症候群と日本では言われていますが
英語圏の病名で「Cold syndrome(コールドシンドローム)」は
寒冷症候群になってしまいますし
海外でも定義は曖昧で、一般的に海外の医学書では
上気道感染症という表現が適切となっており
風邪という病名は医学書には無いと言えます。
つまり、風邪という病名は
「風邪(ふうじゃ)」という東洋医学の言葉が語源なわけですね。
風の邪は、東洋医学では春に起こりやすいと考えられており
旧暦で考えた場合、2月頃~4月末ぐらいが春ですから
丁度花粉症の時期と同じですよね?
他にも風の邪は、肝の病を引き起こしやすいとされており
ここで言う肝は、確かに肝臓の事なのですが
昔から『肝を冷やす』という表現があるように
肝の病は精神疾患等も引き起こすと考えるのが
実に東洋医学らしい考え方です。
ちなみに、東洋医学では春の季節は、四獣神
青龍にあたり、これを語源にしたかどうかは定かではありませんが
皆様がよくご存じで
病院等でも花粉症によく処方されている漢方薬の代表格として
小青龍湯があります。
こんな占いじみた手法で使ってみても効果が出てしまうのが
東洋医学の奥深さと言えましょう。
もちろん、ちゃんと東洋医学の知識を身につければ
多様な花粉症に対応することが可能ですので
小青龍湯だけが花粉症の漢方薬ではなく、他にも様々な漢方薬がありますし
それらを事細かな症状に応じて扱いこなせなければ
本当の意味で漢方薬が扱えるとは言えないわけなんで
猫も杓子も小青龍湯なんていうのは
落語の葛根湯医者
しつこい花粉症で悩まれている方は、是非、本当の漢方薬をお試しください♪