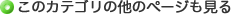きぐすり.com は、漢方薬、女性の健康、サプリメント、ハーブの情報を専門家がやさしく解説しています。
地図から学ぶ、生薬(きぐすり)のふるさと
「植物分類学の父」牧野富太郎博士とは
「植物分類学の父」と呼ばれる所以

- 牧野富太郎博士
牧野富太郎博士は、植物に対する類い希な好奇心をもち、日本全国を縦横無尽に渡り歩きながら生涯に約40万枚とも言われる大量の植物標本を採集した。
当時の日本は、自国の植物相(フロラ)がまだ解明できていない状況にあった。つまり、日本にはどのような植物がどこに生えているかまだ完全には把握ができていなかったと言うことである。
牧野博士の採集した標本と彼の研究は、日本の植物相の解明に大きく貢献し、次第とそれが明らかにされていったのである。
故に牧野博士は日本の「植物分類学の父」と呼ばれるに至ったわけである。
牧野博士の記載したヤマトグサは国内で日本人により初めて新種が発表された植物として有名である。
牧野富太郎博士の業績
牧野博士の業績は主として3つあげることができる。
ひとつは分類学の研究そのもので、多くの未記載種を発見し、日本のフロラ解明に貢献し、分類学のレベルの向上に業績を残した。
日本産の植物で牧野博士が命名した植物はリンネに次いで多い。
もうひとつは、植物画の技量が天才的であったことである。
多くの西洋に並ぶまたはそれを越える植物画を世に送り出している。
最後に忘れてはならないのは、植物の一般教育普及活動である。
全国を回り、植物の勉強会、観察会を多く開催し、各地に教え子を作った。
 |
| 有用植物図説 (ゆうようしょくぶつずせつ) |
|---|
また、野生植物のみならず、農作物や薬草、園芸植物など有用植物にも多大な興味を示し、それに関する様々な論説を書いている。例えば、漢名「杜若」という薬用植物を、日本ではカキツバタにあてることがあるが、これはショウガ科のアオノクマタケランのことであると書いている。
植物名の漢名と漢字名と混同されているものを整理し、正しい使い方を個人で出版していた「牧野植物混々録」の中でしばしば指摘している。牧野植物図鑑の索引は漢名でも引けるようになっているのは牧野博士ならではのことであろう。
牧野博士は植物分類学の基本であるフィールドを非常に大切にした。
また、そのフィールドは野山から田畑、人家の庭にまで及んでいる。
植物学者にしては珍しく、野生植物、栽培植物の区別無く全ての植物に関心を持ち研究を行った。栽培植物の研究でも知られ、多くの栽培品種に学名を付けている。
全ての植物に分け隔て無い愛情を注いだのが牧野富太郎といえるのではないだろうか。
- はじめに
- 日本の生薬(きぐすり)を学ぼう
- 忘れ去られた石菖[1]~石菖との出会い~
- 忘れ去られた石菖[2]~石菖って?~
- 忘れ去られた石菖[3]~石風呂の文化~
- 忘れ去られた石菖[4]~茶や花の文化の中へ~
- 忘れ去られた石菖[5]~聖なる場所~
- 「おきぐすりのふるさと」富山
- 小豆島のオリーブの魅力
- 種子島におけるガジュツの収穫
- 鞆(とも)の保命酒
- 熊本の川“緑川、白川、黒川”色々
- 日本に一つ日本一の味噌の天神
- ハスって、な~に?
- 熊本名産「からし蓮根」
- 薬用に用いる「ハス」
- 牧野富太郎
- 伊吹山の薬草[1] ~伊吹山にはなぜ薬草が多いのか?~
- 伊吹山の薬草[2] ~日本武尊は伊吹山の荒神にトリカブトで反撃されたか~
- 伊吹山の薬草[3] ~コンブリ~
- 伊吹山の薬草[4] ~甘茶~
- くすり屋の町 道修町
- 除虫菊
- 世界の生薬(きぐすり)を学ぼう
- 茯苓の産地を訪ねて~1~
- 茯苓の産地を訪ねて~2~
- ローズヒップに出逢う旅:チリ
- ベトナム桂皮