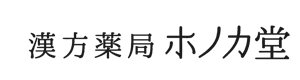梨 (寒性・潤・降・肺と胃)
「梨は百薬の長」と呼ばれ、お隣の韓国でも梨を1年中保存し、料理やお菓子の甘味に使用します。梨は喉や肺を潤し、声がれや咳を止める効果があります。また、カリウムが豊富で利尿作用もあります。
リンゴ (平・潤・降・五臓六腑)
リンゴは身体に養分を補い、陰陽のバランスのとれた果物です。さらにリンゴの有効成分は、加熱に強く、様々な調理法があります。リンゴは陰虚にとても良い果物ですが、リンゴを毎日2個食べ続けると、リンゴ酸などの刺激によって胃腸の粘膜を傷つける恐れがあるので控えめにしてください。リンゴといえば整腸作用ですが消化不良の下痢や便秘のどちらにも効果があります。
柿 (寒性・潤・収・降・心と肺と大腸)
「柿が赤くなると医者が青くなる」ということわざは「柿が色づく頃は気候がよく収穫したものを食べて、病人が少なくなるので医者が困る」という意味ですが、中医学的には滋陰効果が強く、熱を収め、喉の渇きを解消してくれ、肺を潤し、痰を少なくします。(肺が熱を持ち乾燥して咳が出るのを止めてくれる。)津液を生み出し、胃の津液が不足しムカムカしたり口が乾くのを防ぐ。生の柿は消化の良いものではなく胃腸を冷やすので、どの体質の方も食べすぎはよくありません。
詳しい内容と薬膳レシピは、ほのか薬局養生訓22年10月