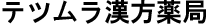月経前になると「イライラする」「気分が落ち込む」「むくんだりニキビができる」というような症状は、40~80%の女性が経験しているといわれています。
 このような排卵から月経開始までの時期に現れる精神的・身体的に不快な症状を総じて月経前症候群(PMS)といいます。
このような排卵から月経開始までの時期に現れる精神的・身体的に不快な症状を総じて月経前症候群(PMS)といいます。PMSの症状は人によって様々です。「怒りっぽくなる」「理由もなく悲しくなってくる」というような精神的なもの、「頭や胃が痛む」「吐き気や嘔吐がある」「めまいやほてりが現れる」といった身体的なものなど、数多くの症状があります。
したがってPMSは排卵のある女性であれば、誰にでも起こりうる症状で、決して特別なものではありません。
しかしながら、PMSは月経の周期ごとに反復して現れるのですから、非常に煩わしいものでもあります。
また、症状の程度も個人差が激しく、症状が現れてもさほど気にならない人もいれば、日常生活も困難になってしまう人もいます。
このように精神症状が顕著で職場や学校、家庭などの日常生活に支障のある重症型を月経前不快気分障害(PMDD)といいます。PMSの症状を訴える女性のうち約5%がPMDDと診断され、適切な治療が必要とされています。
欧米ではPMSの研究が進んでおり、専門的な治療体制が整いつつありますが、日本国内でPMSという言葉が知られるようになったのはここ数年のことであり、社会的認知度は低いといえます。
そのため、本人は症状を自覚していながらも、それがPMSのせいだと気づかず、周囲の方もそのような女性を前にし戸惑うこともあるでしょう。
特に月経のない男性にしてみればPMSを理解することは難しいかも知れませんが、薬物治療と並行して少しでもPMSの理解を深めていただくことも大切だと思います。
【養生方ならびに西洋医学的治療薬】
軽症例では、食事療法(カフェイン・アルコール・塩分・糖分の制限、ビタミンやミネラルの摂取)、適度な運動によって改善することもあります。
このような方法で軽快しない場合は、ホルモン剤や抗うつ剤などの薬物療法が必要となりますが副作用の面で問題があるようです。また、対症療法として痛みに鎮痛剤、むくみに利尿剤なども用いられます。
【代表的漢方医学的治療薬】
漢方ではPMSやPMDDの原因を血の変調とみなし改善する漢方薬を処方します。
また、東洋医学的にみると血は肝と密接な関係がありますので、肝の状態を整える漢方薬を用いることもあります。
・加味逍遥散(かみしょうようさん)
イライラ感などの精神症状が顕著で、のぼせたり、発汗したりする人に用います。不眠の傾向もあります。食欲不振など胃腸症状はほとんどありません。
更年期障害にもよく使われる処方です。
・柴胡桂枝湯(さいこけいしとう)
だるみがあり、食欲もあまりありません。
時に吐き気や微熱を伴ったりします。にきびや吹き出物などの皮膚疾患を訴える方もいます。
・四逆散(しぎゃくさん)
気分の落ち込みが強く、時にうつ状態になります。
食欲は比較的ありますが、胃痛や腹痛を訴える場合があります。