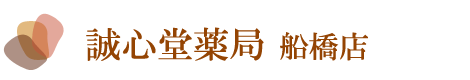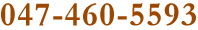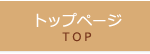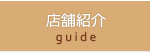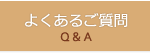今回は生理の量が少ないのはなぜ?といった症状がある場合、その原因を考えていこうと思います。
生理の量が少ないことを、過少月経といいます。通常生理の量は20~140mlくらいの量が適切とされていますので、
20mlより少ない場合が該当します。
ただ、出血量を測ることはできないため、実際には通常の出血量と比べて少ないかどうかで判断するのが一般的です。
考えられる原因は、
①年齢とともに低下する女性ホルモンの分泌量の変化
(エストロゲン:卵巣ホルモンは子宮内膜を厚くする作用がありますが、これが出なくなってくると内膜が薄くなり、月経量も少なくなります
②女性ホルモンのバランスの乱れ
2種類の女性ホルモンのうち、エストロゲン:卵巣ホルモンは子宮内膜を厚くする作用、プロゲステロン:黄体ホルモンは内膜をはがして子宮の中をキレイするという作用を持っています。エストロゲンは十分出ているのに、プロゲステロンが出ていないと、月経量が少なくなることが考えられます。
③子宮頸部から排出する量<卵管からお腹のなかに逆流する経血量
④流産手術など、子宮内の手術をしたことがある方
子宮の内側がくっつき、子宮内膜の面積が減ってしまう「子宮内腔癒着症」の可能性があります。
検査
超音波検査や血液検査によるホルモン分泌量の測定が行われます。
超音波検査では、子宮や卵巣の異常を確認することができます。
血液検査では女性ホルモンの分泌量や性腺刺激ホルモン、プロラクチンの分泌量をチェックします。
治療
ホルモン剤の投与が行われます。排卵が起きていない場合には排卵誘発剤が使用されるケースがあります。
子宮内膜炎のような病気がある場合には、手術によって根治的な治療が行われることもあります。
では、漢方ではどうするのか?
漢方薬では、血流を整えることで月経の乱れや不調を整えます。
ホルモンは正常に分泌されていれば血液中に含まれているものです。血流にのって患部に到達することにより本来の作用を発揮します。
体質で判断すると『血虚』、『腎虚』、『痰湿』、『瘀血』の状態が考えられます。
まず血虚証ですが、
血虚証・・・人体に必要な血液や栄養が不足している体質。
次に腎虚証は、
血が不足しているため、経血量が減ります。
腎虚証・・・エネルギーや栄養の基本物質である精を蓄えるところで、腎の機能が低下した証。
生活の不摂生、過労、慢性病による体力低下、加齢などにより、この証になります。
痰湿証・・・体内に痰湿(過剰な水分や湿気)がたまっている証。
多食、食事の不摂生、過度の飲酒などにより、この証になります。
痰湿が血の流れを阻害するため、経血量が少なくなります。
血瘀証
血流が鬱滞しやすい体質。
精神的ストレスや、冷え、体内の過剰な水分、生理機能の低下などにより、この証になります。
血瘀が血の流れを阻害するため、血流量が少なくなります。
以上の可能性を踏まえて問診することにより証を決定して適切な漢方を組み立てていきます。
以上です。
ご参考になさって下さい。