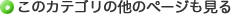きぐすり.com は、漢方薬、女性の健康、サプリメント、ハーブの情報を専門家がやさしく解説しています。
地図から学ぶ、生薬(きぐすり)のふるさと
~聖なる場所~
水に関わる信仰
石菖は湧水地や川辺などの清流地に自生しており、それほど珍しい植物ではありません。
むしろ生命力の強い植物といえます。
湧水地は、霊水・聖水の湧き出る場所として地域の人々から崇められていた場所が多いようで、龍神様九頭竜神などの水の神様が祀られています。
石菖は、こうした清らかな水の象徴として、位置づけられていたように感じます。
従って、現代の日本人が、石菖を顧みなくなったことは、清らかな水の大切さをないがしろにしていることにも繋がるのではないでしょうか。
それは日本人のアイデンティティーの欠如にも繋がることでもあります。
先述のように、石菖は、水の湧き出る湧水地に存在しています。

- ▲ 湧水地の石菖
そこでは蛍を観察することも出来ます。
また付近には水や川に関わる神社やお寺が多くあり、古くから人々が水に関わる信仰を行っていたことがうかがわれます。
石菖はヘビの化身?!
水に関わる信仰にはヘビや龍が頻出します。

- ▲ 神社の手水の龍をおおう石菖 伊豆松崎町 伊那下神社
これは、私見ですが、石菖はヘビの化身なのではないでしょうか。
確かに石菖の根茎の部分をよく見るとヘビによく似ているのです。
『諏訪大明神御本地縁起』には、石菖とヘビや龍神に関わる内容が記載されています。
この縁起では、ヘビに転身させられた主人公が、石菖の生えている池に浸り、朝日を浴びることで、人間に復活する筋立になっています。
ここではヘビは水界の化身とみなされており、水辺に生息する石菖(湧水地)は、現界(此の世)と異界(あの世)をつなぐ存在(場)でもあります。
水は人間が生活する上で必要不可欠なものです。
縄文の遺跡などをみれば川や湧水地の近くにその痕跡を見つけることができます。
川は古来より人間の生命や魂の原郷とされてきました。
そして川の水が湧き出る(此の世に生まれる)湧水地は、異界に通じる聖なる場所(畏怖すべき場)でもあったのでしょう。
また、その場が蛇と関わるという伝承は、意外にも現代の私たちの日常生活の水に関する器具の名前に、痕跡として残っています。「蛇口」です。
聖なる場所
多くの石菖の群生する湧水地が、霊水としてその土地の人々から尊ばれているのも偶然ではないでしょう。
ヘビに変身した者(異界に居る)は、石菖の生えている池という此の世とあの世の境界の場を通して浄まり、光を浴びることで人間の姿として復活することとなります。
湧水地が異界に通じる聖なる場であり、それに蛇が関わる・・・。
また香りという存在自体が、此の世とあの世(宗教儀式でのお香)、男女(性フェロモン・香水)など、何か二つのものをつなぐ媒介物でもある。
香りのする石菖はこうした意味からも境界という場を象徴しています。
石菖(香り)とヘビ・龍神そして水との関わりは実に興味深いです。
- はじめに
- 日本の生薬(きぐすり)を学ぼう
- 忘れ去られた石菖[1]~石菖との出会い~
- 忘れ去られた石菖[2]~石菖って?~
- 忘れ去られた石菖[3]~石風呂の文化~
- 忘れ去られた石菖[4]~茶や花の文化の中へ~
- 忘れ去られた石菖[5]~聖なる場所~
- 「おきぐすりのふるさと」富山
- 小豆島のオリーブの魅力
- 種子島におけるガジュツの収穫
- 鞆(とも)の保命酒
- 熊本の川“緑川、白川、黒川”色々
- 日本に一つ日本一の味噌の天神
- ハスって、な~に?
- 熊本名産「からし蓮根」
- 薬用に用いる「ハス」
- 牧野富太郎
- 伊吹山の薬草[1] ~伊吹山にはなぜ薬草が多いのか?~
- 伊吹山の薬草[2] ~日本武尊は伊吹山の荒神にトリカブトで反撃されたか~
- 伊吹山の薬草[3] ~コンブリ~
- 伊吹山の薬草[4] ~甘茶~
- くすり屋の町 道修町
- 除虫菊
- 世界の生薬(きぐすり)を学ぼう
- 茯苓の産地を訪ねて~1~
- 茯苓の産地を訪ねて~2~
- ローズヒップに出逢う旅:チリ
- ベトナム桂皮