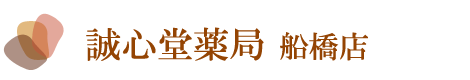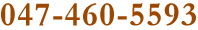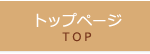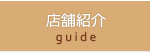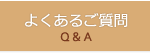誠心堂薬局船橋店 関根です。
今回は前回の話の続きを述べたいと思います。
以前の記事で、着床の原因を調べる際に血液検査には、多数の検査項目がありますというのをお話ししました。
①免疫学的に問題ないか、
②血液凝固に問題ないか、
③代謝に問題ないか、
④甲状腺の異常はないか、
⑤黄体機能不全の異常はでていないか、
⑥夫婦の染色体異常はないか
という項目です。
今回は、細かい検査項目についてお話していきます。
具体的には、
①免疫学的に問題ないか
・抗カルジオリピン抗体IgG、抗カルジオリピン抗体IgM、抗CL・β2GPⅠ抗体、ループスアンチコアグランド(LA)、抗PE抗体、IgG、➡抗リン脂質抗体 (自分を傷つける抗体反応や血液が固まりやすくなる作用があります)
・抗核抗体➡自己抗体がどの程度存在しているかを示します。
・Th1/Th2比➡通常、Th1/Th2比は8~12が正常範囲で、Th1が強くなる10.3以上だと胚への拒絶が強くなり、着床障害や着床後の胚の発達拒絶による流産を招きます。
②血液凝固に問題ないか
・APTT、PT、凝固第Ⅻ因子、プロテインS活性、プロテインC活性、➡血液が固まりやすい状態かどうかを調べます。
③代謝に問題ないか
・HbA1c➡HbA1c8%以上で胎児の先天奇形が20~30%と高率になることが明らかになっています。妊娠前のHbA1c(正常値4.6~6.2%)の目標値は7%未満、できれば6.2%未満を目標にします。
・ビタミンD値➡良い卵子を作り、また受精卵が子宮に着床させやすくする作用があります
・亜鉛値➡着床に関係する多くのホルモンに亜鉛が必要です。卵胞刺激ホルモンや黄体化ホルモンの働きを高めてくれます。
④甲状腺の異常はないか
・TSH、FT4➡潜在性甲状腺機能低下症で甲状腺ホルモン補充を行ったほうが着床率は上昇します。
⑤黄体機能不全の異常はでていないか
・P4➡子宮内膜を着床しやすいように変化させます。
⑥夫婦の染色体異常はないか
・夫婦染色体➡卵子、精子が創られる減数分裂の過程で一定の割合で正常な染色体と、変化した染色体ができ、そのうち変化した染色体の卵子、精子が受精・着床すると流産となることがあります。
以上の検査結果によって治療の必要性を判断します。
治療方法は以下の通りです。
・子宮内膜改善薬(シルディナフィル膣座薬)
・抗凝固療法(低用量アスピリン)
・血糖コントロール
・甲状腺ホルモン調節
・タクロリムス内服
・子宮内膜掻把術
・経膣的腹腔鏡
を行います。
ERA検査、EMMA検査、ALICE検査については、
TORIO検査で異常があった場合、どういう治療をするの?
https://www.kigusuri.com/shop/seishindo-funabashi/topic/1668636600.html
を参照してください。
もし、着床がうまくいかず、これからの治療について不安や心配がある場合は、検査のことについて知っておくと良いと思います。
以上、着床検査についてでした。