歴史的要素も含んで組香の基本であり、その色々な変化形について経験を積まなければならないのが、前に記した「十炷香(ジュッチュウコウ)」ですが、未経験の人も含めて手軽に楽しめる組香に源氏物語を題材とした「源氏香」があります。
 源氏香之図帖 写真提供:香文化資料室 松栄堂 松寿文庫
源氏香之図帖 写真提供:香文化資料室 松栄堂 松寿文庫
源氏香の方法
一から五までの香木を各5包づつ合計25包用意し、それを良く打ち交ぜた後、その中から20包を取り除いて5包を残します。それを順に聞いて十炷香と同様に出た順の答えを決めるのですが、答え方として、先ず5歩の縦線を引き、5回炷かれた香が同香であるか別香であるかを、縦線の上部を横線で結んで、下図の様な形を作って答えとします。
5の組合せは全部で52通りあり、これを源氏物語54帖に当てはめ結び付けたのは、日本人の感性の表れと言えましょう。即ち、54帖中巻頭の「桐壷」と巻末の「夢浮橋」を除いて答えの形と帖の名称とを対応させてあります。
例えば、一の香と二の香が同じで三の香以下が全て異なる場合は、
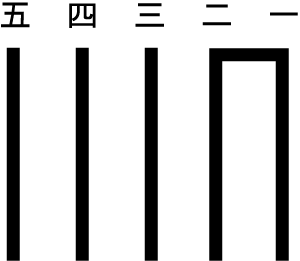 で、巻3の「空蝉」となります。
で、巻3の「空蝉」となります。
又、一の香と五の香が同じ、二の香と三の香が同じ、四の香は異なる場合は、
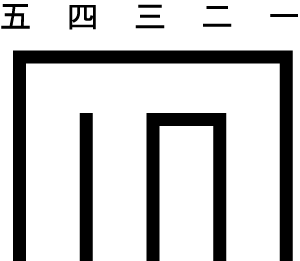 で、この形を書くか、巻38の「鈴虫」と記します。
で、この形を書くか、巻38の「鈴虫」と記します。
「源氏物語」自体、世界的存在の文学であり、これを題材とした「源氏香」は香道の面でも国際性豊かな組香と言えましょう。その方法が判り易く、世界共通の数字を使い、同時に答の記号の文様が「5」の組合せで幾何学的に作られて居る点、図形的にも数学的にも優れた日本の優雅さと優秀さを示す興味深いものとされて居ます。
この組合せについては室町時代から色々と試みられましたが、現在の様式が確立したのは、江戸時代の享保年間(1716-1735)とされています。
現在、用いられている「源氏香之図」は、下図の様になって居ます。
