お寺の主に廊下の角などに、良い香りのする球形の香炉が吊るされていることに 気付かれた方もおられるでしょう。
これは「吊香炉」と呼ばれて居り、「吊香炉」の中は三重のジャイロスコープの 様になっていて、どの様に揺れても中の火皿は水平に保たれる仕組みになっています。

「吊香炉」が、記録に載せられたのは秦の「始皇帝」の頃とされています。 これを、始皇帝の馬車の中に吊るして香の香りを楽しみ、 その香りは馬車が通り過ぎ、はるか後にも漂ったとの事です。
これを、徳川時代に日本で小型の漆器としたものが、「袖香炉」で、 和服の袖の中に入れて、どの様に日本舞踊として踊っても、 上品な香の香りが辺りに漂う様にした芸術品へと発展させました。
体から良い香りを放っていたとされる美人?
紀元前5世紀の西施(セイシ)、8世紀の楊貴妃(ヨウキヒ)、18世紀の香妃(コウヒ)など、 中国には常に体から良い香りを放って居たとされる美人の話が多くあります。
これを『挙体芳香』と呼んで、美人の一つの条件としました。
その為、それに対抗する為の手段として、常に香を焚き染める方法が 日本でもとられましたが、古代中国では、漢方の智恵から、 良い「香り薬」を服用する手段が考え出されました。
これが『芳気方』です。
これについては、霊気方(レイキホウ)、葛氏方(カッシホウ)、如意方(ニョイホウ)、 枕中方(チンチュウホウ)、録験方(ロクケンホウ)等の文献がありますので、 ここでは詳細は省かせて頂きます。
「薫君」と「匂宮」
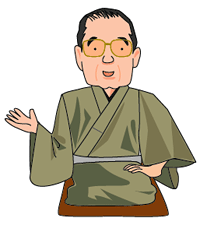
『源氏物語』には光源氏の妻「女三之宮」と光源氏の友人「柏木」との間の不義の子であり生れながらに芳香を放つ「薫君(カオリノキミ)」と、光源氏の孫に当たり次代の皇太子であり「薫君」に負けまいと最高の薫物を常に焚きしめていた「匂宮(ニオイノミヤ)」の話が出ています。
これは、仏教で言う『一切香集』の世界である極楽浄土の象徴が「薫君」であり、 俗世に生きる人間像の象徴が「匂宮」であるとの説もあります。