きぐすり.com は、漢方薬、女性の健康、サプリメント、ハーブの情報を専門家がやさしく解説しています。
和の香り
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 | 参考 | 香関連 | 主な歴史的背景 |
|---|---|---|---|
| 538 | 百済より仏教伝来 | ||
| 553 | 香木が大阪泉に漂着 | 香の流れ参照 | |
| 592 | 飛鳥時代(~645) | ||
| 593 | 聖徳太子(574~622)の摂政(~622) | ||
| 595 | 香木、淡路島に漂着 | 香の流れ参照 | |
| 600 | 第一回遣隋使 | ||
| 607 | 第二回遣隋使、小野妹子渡隋
法隆寺創建 |
||
| 630 | 第一回遣唐使 | ||
| 645 | 白鳳時代(~710) | ||
| 663 | 白村江の戦い | ||
| 667 | 大津宮に遷都 | ||
| 698 | 薬師寺創建 | ||
| 710
(和銅3) |
奈良時代(~784) | 平城京に遷都 | |
| 712
(和銅5) |
説 | 古事記成る | 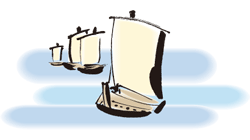 |
| 713
(和銅6) |
風土記撰進の詔
~715播磨、721常陸、733出雲、成る |
||
| 720
(養老4) |
説 | 日本書紀成る | |
| 752
(天平4) |
東大寺大仏開眼法要 | ||
| 753
(天平5) |
鑑真和上(688~763)渡来 | 香の流れ参照 | |
| 759
(天平11) |
唐招提寺創建 | ||
| 783
(延暦7) |
説 | 萬葉集成る | |
| 794
(延暦13) |
平安時代(~1192) | 平安京に遷都 | |
| 811
(弘仁2) |
説 | 竹取物語成る |  |
| 905
(延喜5) |
古今和歌集成る | ||
| 984
(永観2) |
頃 | 柄香炉(供香)・鞠香炉・火取母(翫香)登場。
薫香合始まる。 |
|
| 1008
(寛弘5) |
源氏物語を一條帝(980~1011)に献上 | 源氏物語の香り参照 | |
| 1192
(建久3) |
鎌倉時代(~1333) | ||
| 1202
(健仁元) |
「薫集類抄」(最古の薫物指南書)成る | ||
| 1334
(元享3) |
頃 | 十炷薫(後の十炷香)に文学的要素導入 | |
| 佐々木道誉(1306~1373) |
薫物から香合せへ参照 |
||
| 1336
(延元元) |
室町時代(~1467) | ||
| 足利義政(1436~1490) | はじめに参照 | ||
| 志野宗信(1445~1523) | 香合せから組香へ参照 | ||
| 三條西實隆(1455~1537) | 香合せから組香へ参照 | ||
| 1467
(應任元) |
戦国時代(~1573) | ||
| 1478
(文明10) |
六種薫物合せ行われる | 薫物から香合せへ参照 | |
| 1500
(明慶9) |
頃 | 香木の種類を伽羅・羅国・真南蛮・真那伽に設定 | |
| 1501
(文亀元) |
伝 | 足利義政、蘭奢侍拝領 | |
| 1573
(天正元) |
安土桃山時代(~1600) | ||
| 1574
(天正2) |
伝 | 織田信長、蘭奢侍受領 | |
| 1600
(慶長5) |
伝 | 徳川家康、蘭奢侍受領 | |
| 1603
(慶長8) |
江戸時代(~1867) | ||
| 東福門院(1607~1670) | 組香について(1)参照 | ||
| 1681
(天和 元) |
伝 | 香木に佐曾羅・寸聞多羅を加える | 香木の種類参照 |
| 1716
(享保元) |
頃 | 源氏香成立。盤物流行 | 組香について(2)参照 |
| 1867
(慶應3) |
大政奉還 | ||
| 1868
(明治元) |
東京に遷都 | ||
| 1877
(明治10) |
伝 | 明治帝、蘭奢侍受領 | |