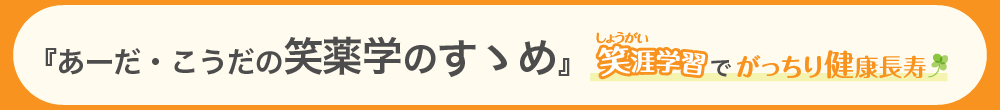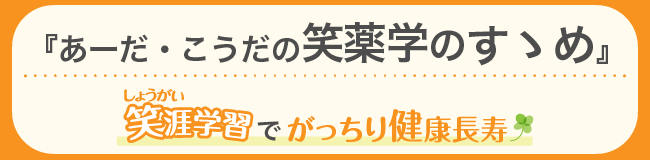③穀物動物論 「臼歯持つ人は粒食う動物よ」「粉砕し、唾液と混じえて飲み砕かせる穀物が最良である」
(現代のサプリメント社会に提言)
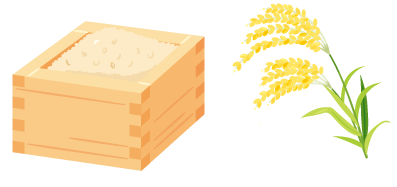
消化のことを「こなす」と言いますが、これは、よく噛んで「粉なす」ことからきている言葉で、左玄の提唱する玄米食では、先ず、よく噛むことが要求されるし、食べ過ぎることはありません。
④一物全体食論 『なるべく菜類の皮肌を脱除せざるを良しとす』
食品には陰陽の別はあっても、生きているものはすべてそれなりに陰陽の調和が保たれているものだから、全体を食べるのが理想なのである。それを食べた人体もバランスを崩されることはない。野菜や果物、その他のあらゆる食物についても同じことが言える。
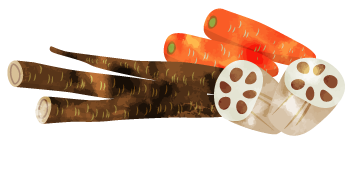
⑤身土不二論 『郷に入りては郷に随ふ食養法を実行す可き』
『春苦味、夏は酢の物、秋辛味、冬は脂肪と合点して食へ』
「身と土、二つにあらず」、つまり人間の体と人間が暮らす土地は一体で、切っても切れない関係にあるという意味です。言葉の起原は大昔の仏典にありますが、左玄の食養会が食のルーツとして確立しました。その土地、その地方に先祖代々伝わってきた伝統的食生活には、それぞれ意味がある。「郷にいっては郷にしたがえ」ということである。今や食材に季節感がほとんどなく、自然との調和に関しては後退の一途をたどっている。
この他、頭寒足熱は、いつまでも若々しく長寿をもたらす。脱塩も健康保全には重要で、入浴、運動(駆け足)、寒涼発汗、お茶を飲む効用も上げています。

石塚左玄 の功績 食養とマクロビオティック 万人に通用する健康術はない
食養生の歴史で、石塚左玄が特に大きな影響を与えた人に、桜沢如一と西勝造、二木謙三がいます。桜沢如一は食養をマクロビオティックと名付けて世界に広め、西勝造は健康法の一つに食養生や断食を取り入れました。この二人は医者ではありませんが、健康法の指導者として活躍したため、後の指導者に大きな影響を与えております。医者の二木謙三は、二分間煮や玄米菜食を勧めました。
食養生を行うとき、ある流派に盲目的に、はまってしまうと、健康になるはずが不健康になることがあります。理論とか法則であるなら、絶対的なものがあるかも知れませんが、人間の体を対象に何かを実践するときには、個体差を考慮する必要があり、万人に通用する方法というものはありません。このため、本に書いてあることを信じてそのままやっていると、良い影響ばかりでなく、悪いことも起こりうるということです。往々にして、個々の理論はもっともでも、全体の調和とは結びつきません (要素還元主義)。


神田 博史先生
詳しいプロフィールはこちら >
略歴
厚生省国立衛生試験所 生薬部
元 広島大学 薬学部 准教授・薬用植物園園長
元 安田女子大学 薬学部 教授・薬用植物園園長
元 広島国際大学 薬学部 教授・薬用植物園園長
元 広島国際大学 医療栄養学部 教授
内閣府地域活性化伝道師